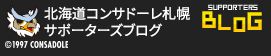読書管見・小松成美『中田英寿 誇り』
2007年08月06日
小松成美『中田英寿 誇り』(幻冬舎、ISBN:9784344013391) W杯2006・ドイツ大会から一年とちょっと。中田英寿の引退の真相、大会中の代表に起こった出来事を綴ったノンフィクション。正月に読んだ『敗因と』とあわせて読んでおくのも良かろうということで購入。
もちろんあわせて読むことの意味は、『敗因と』に出てこなかった中田英寿の言葉を読むことにありました。
(注意:ここから先は内容に触れています)
で、読む前には「中田英寿側」に立った本書と中田の出てこない『敗因と』の読後感には大きな違いがあることを予想していたのですが、実際読み終えてみると、代表そのものに対する見方はほとんど変わりませんでした。本書が過度に「中田英寿擁護」に傾いていないからであると同時に、『敗因と』もまずまずニュートラルな視点から書かれていたんだなぁ、と改めて思った次第です。 世間で言われているほど自己中心的ではないけれど、一度決めたら絶対に曲げない、という人物像は良く知られていることとして、私自身の新知見としてはマルタ戦のハーフタイムについてと左足の怪我、それとペルージャ時代のエピソードですね。「『福西を代えろ』と進言した」という噂はクロアチア戦のものだとばかり思っていましたし、ローマ移籍に至る過程にそんな困難があったとは知りませんでした。
取材は大会を三ヶ月後に控えた2006年6月からスタートしていますが、最後の方で、ヨーロッパへの移籍から引退に至る過程とそれに伴う困難が綴られています。ノンフィクションの構成としては、これら過去のエピソードをW杯の進行とパラレルに綴っていくという手法もありだったのでは、と思います。クロアチア戦とブラジル戦の間にこの過去のエピソードが入っているのですが、ちょっと長すぎる。 もう一つノンフィクションとしての本書について。作者の小松成美は中田英寿を10代の頃から取材してきた人です。といっても私は前作『鼓動』は読んでいませんが。とにかく彼女自身にとっても中田との関わりにおいて節目となる作品だったわけで、取材対象に対する思い入れが控えめながらもそこかしこに滲み出ています。 この「対象への近付き方」ってのがノンフィクションを生かすか殺すかの分かれ目の一つだと私は思っていて、対象への愛情のないノンフィクションは読んでいて苦痛だし、一方で対象をべた褒めするのも辟易モンです。本書は、筆者自身の愛情・思い入れはちょっと勝ちすぎているんだけれど、文章にそれが過度に出ていないという、ギリギリのところでバランスが取れていると感じました。
中田英寿個人に焦点を当てた本書よりも代表そのものを扱った『敗因と』の方がチームの内情を多角的に描写できており、彼個人にではなくドイツにおける代表について知りたいという方は後者だけでよろしい。中田本人に興味を覚えるという人はこちらをどうぞ。
読書管見・『敗因と』
2007年01月15日
金子達仁・戸塚啓・木崎伸也『敗因と』(光文社、ISBN:4334975127) サッカーW杯2006・ドイツ大会における日本代表の「内部崩壊」、その真相に迫ったノンフィクション。 まず断っておかなければならないのは、この本は「チームの内情」に焦点を絞った内容になっているため、ドイツにおける代表の戦いぶり、とりわけ戦術的な部分についてはほとんどページを割いていません。だからピッチ上での代表について読みたい人にはお薦めしません。が、それを差し引いても読む価値はあると思います。些か「ゴシップ記事集成」めいたところはありますが。
(ここから先は内容に触れています)
本書は三人のライターによる分筆形式をとっており、関係者に対するインタビューを基に構成されています。一見するとそれぞれバラバラのことを言っているように見えますが、よく読むと何となく一本の線が引かれているように見えます。私なりにその線を手繰りながら各章の内容を簡単に紹介し、併せて感想も書いてみます。
- プロローグ「最期」
ブラジル戦終了後の「900秒」と、中田英寿のチームメイトであったアドリアーノのインタビューを中心に構成されています。読み返すたびに、あの時のやり場のない怒りが蘇ってきます。「こんなハズじゃなかったのに…」という言葉も。 ピッチにひっくり返っている中田英寿のもとに宮本を除いて代表の選手達が行こうとしなかったこと、これが今大会の代表を象徴していたことが示されています。 導入としてはまずまずだと思います。ただ、ここで中田英寿を巡るエピソードを中心に据えてしまったのは、読者の誤読を招く元になってしまっているのではないでしょうか。実際ネットを泳いでみるとこの本を「ヒデ批判」あるいは逆に「ヒデ擁護」と捉えたレビューが多く見られました。そうしたステレオタイプのチーム批判に抗いたい、という構想があったとすれば(実際そうだと思うのですが)、もう少し書きようがあったのではないでしょうか。
- 第1章「愛憎」
フェネルバフチェ監督となってからのジーコへのインタビュー及びオーストラリア戦のレビュー。本人の理想と日本サッカー、代表選手とのズレが語られています。 ジーコがいかに日本サッカーを想っているのかは分かりました。でも、やはりタイミングが悪かったな、と思います。ジーコが思うほど日本は成熟していなかった…
- 第2章「団結」
藤田俊哉・三浦淳宏・土肥洋一へのインタビュー。ベテランのサブメンバーから見たチームと、「リーダーの不在」がチーム崩壊の一つの要因であったことが示されています。 個人的に一番胸に迫るモノがあったのはこの章です。
- 第3章「確執」
「海外組」と「国内組」の溝が形成されていく過程が述べられています。 リーダー不在による「グループ」の形成、ケガによる長期離脱が招いた中田英寿の孤立、中田浩二の役回りなどに加えて、ジーコへの不満からスケープゴートにされていく中田英寿・宮本恒靖・アレックス。アレックスはプレーでも孤立していたのでそうではないかとうすうす感じていましたが、宮本については僕は知りませんでした。
- 第4章「七色」
ヒディンクへのインタビュー。監督としてのジーコとの器の違いを語りたいようですが、ちょっとインタビュアーの存在が勝ちすぎている嫌いがあります。「自分が彼の本音を引き出した」と、感じても書いてはいけないと思います。
- 第5章「晩餐」
クロアチア戦3日前の日本料理屋での出来事と、大会後のエピソード。 「例の『日の丸サイン事件』が起きた日」とされていますが、これが誤解であることは、僕は『サッカー批評』で土肥が語っているのを読んで知っていましたから、さしたる驚きはありませんでした。むしろ、「どうしようもなくなってなお何とかしようとする中田英寿」と「一般のファンを平気でシカトする中田英寿」のコントラストというか、この人の特殊さが印象的です。念のために付け加えておきますが、それが良いとか悪いとかが言いたいのではありません。
- 第6章「齟齬」
「DFラインの高さ」をめぐる対立について書かれています。 守備の基礎的な約束事ができていたトルシエのチームで大会中に起きた対立が、「高いラインを要求する監督と必要以上に上げたくないDFライン」の間で起こったものであり、従ってピッチ上ではディフェンダー同士の微調整で済むレベルであったのに対し、今大会の対立が「前と後ろ」という、文字通りチームを二分するレベルでの話になってしまったため容易に解決できなかったという指摘は非常に明快で説得力があります。余談ですがこの点を指摘しているのは中田浩二で、オシムが彼を招集してくれる日を僕は心待ちにしています。
- 第7章「消極」
クロアチア戦。この「クソゲーム」を伝えたクロアチアとドイツの実況ブースを中心に、「アタッカーの不在」という戦術的な敗因のひとつを挙げています。
- 第8章「落涙」
ブラジル戦。あらためてこうして文字にされてみてみると、いかに絶望的な戦いをしていたかを思い知らされます。
- 第9章「敗因と」
「敗因は、ひとつではない。」 さまざま挙げてきた敗因と思しき要素を前にして、それでも敗因を一つに求めるべきではない、という主張ののちに、「彼らの戦いが胸に響かなかった理由」の一つとして「目標と負荷」の欠如を、前園真聖の回想から指摘しています。 全体を読み終えて。本としては好き嫌いが分かれるでしょうね。さっきも書きましたが基本的に「ゴシップ本」ですから。でも、代表選手だろうが何だろうがサッカーやるのは所詮人間であり、人の絆を結べないチームは絶対に勝てない、ということがよく分かる一冊です。 最後の指摘は確かにそうかなと思います。何となく「前よりはいけるでしょ」と僕も思っていたふしがある。そして、そういう温い(ぬるい)雰囲気が、彼らだけでなく協会にも、周囲にも蔓延していたという指摘は、札幌をサポートする我々も耳を傾けるべきなのかも知れません。だからといって選手を手厳しく批判しろとか殺気立った応援をしろとか、そういうわけではありませんが、「うねり」みたいなものを生み出していかないと、ですね。 札幌も、ある意味で代表と同じような経験をしたチームと言えます。「こんなハズじゃなかった」で終わらないように、今年はいい年にしたいものです。
読書管見・沢木耕太郎『杯(カップ)―緑の海へ』
2006年05月23日
沢木耕太郎『杯(カップ)―緑の海へ』(新潮社 ISBN:4101235163) ワールドカップまであと17日。「オレたちには札幌がある」と言いながらもさすがにそろそろ皆さんも気になりだした頃だと思いますが、今回紹介するのは4年前、日韓大会の観戦記です。 作者の沢木耕太郎は、この世代の男性の多くがそうであるようにサッカーの競技経験がありません。ですから本書での試合に対する分析も技術的な内容にはほとんど触れていません。しかし陸上競技・ボクシングをはじめとしてスポーツの観戦経験は豊富なので、チームの状態や大会の流れに関する考察には「そうかな」と思わせる部分があります。例えばジダン一人に頼るところが大きかったフランスのグループリーグ敗退から、チームの地力よりコンディションを必要とする現代サッカーの特質を説くくだり、逆に一発勝負の決勝トーナメントでは慎重に戦う相手をねじ伏せる真の力が問われるという見解など、今回の大会を見るにあたっても考えておかなければならない点が指摘されています。
ただ作者自身が「あとがき」で「観戦記であると同時に旅行記」であると述べているように、日韓大会を、それも韓国に軸足を置いて見て回った体験記である点にこそ本書の価値があると思います。とりわけ韓国における体験は、大会期間中ずっと日本にいて、しかも韓国人の知り合いを持たなかった私にとっては新鮮でした。また、旅の過程でのエピソードは、作者が日韓大会をいかに見たかということと同時に、出会った人がいかに見たか、ということも我々に伝えてくれます。 今回、ドイツ大会を迎えるにあたって再読してみたのですが、4年前のことを思い出す良いきっかけになりました。メンバー発表の時のトルシエの振る舞いや、小野伸二の病気のことなど、忘れていたことも随分ありますね。前回が地元開催だったことも、ともすれば意識の片隅に追いやられがちです。そういえばアルゼンチン-イングランド戦……の日に大通公園に両チームサポを見物に行ったなあ。試合はテレビで見てました(笑 「サッカーずれ」していない人が書いているので「素人くさい」という意見と「平易で読みやすい」という意見とに分かれると思いますが、ワールドカップのレポとしてではなく、我々と同じ「体験者」の話として読むのが良いんじゃないでしょうか。もっとも常人には不可能な、羨ましい体験ですけど(笑)。
あと、(数日前からこっそりリンク集には加えていたのですが)別荘を建てたので、ココは札幌・サッカー全般・スポーツに関する話題、サッカーに関係のあるブック・シネマレビューに限定することにしました。ですから、サッカーはちんぷんかんぷんだけれど安否確認にココを使っているという方は別荘を覗いた方がいいんじゃないでしょうか。 「本館より別館の方が立派」という温泉宿みたいなことにならないよう、こちらもきちんと書いていきますので、今後ともご愛顧の程を。ヒマを持て余している方は別荘にもおいで下さい。
読書管見・近藤篤『サッカーという名の神様』
2006年05月15日
以前に書いておいたレビュー。もう少しチームの調子が良いときにアップしようかと思って取っておいたのですが、「実は今アップした方がいいんじゃないか」と思ったので、載せます。
近藤篤『サッカーという名の神様』(NHK生活人新書175・NHK出版 ISBN:4140881755) 筆者はフリーのフォトジャーナリスト。『Number』等に掲載されたコラムと、若干の書き下ろしをあわせたエッセイ集。筆者が訪れた国で起こったこと、聞いたこと、サッカーをめぐる様々な風景が、控えめな筆致で描かれています。 本書を読んで気付いたことは、「結局、世界中どこでもサッカーバカは似たようなこと考えてるんじゃない?」ということです。筆者が出会う人々はそれぞれサッカーについていろんな語り方をしているのですが、どれも日本の居酒屋で一度は聞いた気がする語り方ですし、「ファウルしてもいいからとにかく止めろ」というイタリア式の思考法は実は私のそれと結構重なっていたりします(笑)。本書を読んで「ああオレだけじゃなかったんだぁ。良かった」と思った方は、相当病んでいます、サッカーに(笑)。 ブラジルを訪れて筆者が得た「現役サッカーオヤジの人数×真剣度=その国の代表チームの強さ」という公式は、オヤジに片足突っ込んだ私を大いに勇気づけてくれました。「選手が試合の途中でへこたれることを好まず、自分たちもへこたれることを好まな」いイングランドのサポーター。「へこたれそうになった選手は罵倒される代わりに、応援され、応援され、そして応援され」るスタジアムに行ってみたい、そして札幌もそうなって欲しいとも思いました。 トリニダード・トバゴにおけるW杯最終予選を描いた一文が最も印象に残りました。サポートの仕方とか、方法論とか、そういうものを越えた根っこのところで「楽しむ」ことが出来ている世界がある…。とにかく、いろいろ示唆を与えてくれる一冊です。
…と、ここまでが以前に書いた内容。で、あらためて読み返してみて考えたことがあるので書きます。 ここで私は「根っこのところで「楽しむ」ことが出来ている」とトリニダード・トバゴについて形容していますが、「楽しむ」という言葉の意味について、さっき中田英寿がこんな意味のこと言っていたんですね。
「楽しむ」ってのはいい加減にやるという意味ではもちろんなく、厳しいトレーニングやプレッシャーを全部受け止めた上でのことだ。
別にトリニダード・トバゴの観客に対する憧憬が間違っていた、と言うわけでもないし、「「楽しむ」とは論」をぶつつもりもないのですが、どうも私は根底のところで中田の言う「いい加減」な気持ちを持っていたのかも知れません、少なくとも昨日の試合までは。それがこのエントリーにも滲み出ているような気がしたんです。イングランドみたいなスタジアムになって欲しいと言っておきながらへこたれてるじゃないか、と。
昨日、この悔しさを糧にしなければならないと選手に向けて書いたのですが、どうやらこのことを肝に銘じなければならないのは私のようです。それとサポ全部。あんた達は「勝たせたい」のか「勝つところを見たいだけ」なのかどっちなんだ?後者ならチェルシーかどっかのファンやってろ!
読書管見・『パリは燃えているか?』
2006年04月03日
ラリー・コリンズ/ドミニク・ラピエール(著) 志摩隆(訳)『パリは燃えているか?』(上)(下)(新装版・早川書房 ISBN:4152086270(上)・4152086289(下)) 以前紹介した『さもなくば喪服を』のコンビ、コリンズ・ラピエールによるノンフィクション。映画化されており、そちらを御覧になった方もおられるのではないでしょうか。 1944年8月25日、パリ解放。「敵の手に落ちる時にはパリの全てを爆破せよ」という指令に悩むドイツ軍パリ大司令官フォン・コルティッツ、ナチスドイツの手からパリを、祖国を取り戻すべく奔走するシャルル・ドゴールとその部下達、パリ解放により進軍が遅れることを憂慮しドゴールと対立する連合軍の元帥ドワイド・アイゼンハワー、そしてラステンブルクの地下壕に潜むアドルフ・ヒトラー…。しかし、本作の真の主人公はパリ解放を願い、またパリ防衛を遂行するために戦った市民・兵士一人一人であると言えるでしょう。 本書には、1000人に及ぶ人々に対するインタビューの結果得られた「8月25日」に関わるエピソードが収められ、それらがリアリティ溢れるストーリーを織りなしています。登場するのはごく普通のパリ市民からレジスタンス、ドイツ兵とさまざま。「彼らにとってのパリ解放の意味」が実に丁寧に描写されており、歴史上の大事件の背後にある人々の営み・意思といったものを鮮やかに描き出しています。 そこに関わる全ての人々にとって、パリ解放はそれぞれ独自の意味を有していた。その意味に向かった彼ら「一人一人の行動の集積」としてのパリ解放…。なるほど、先にこっちを読んでいたから受け止め方がああなったわけだ。昨日の『タイタンの妖女』と、ここでつながりました(独り言)。 『さもなくば喪服を』に比べてかなり細かい場面割りが施されており、展開のスリリングさはこちらの方が断然上。訳文調に弱い、外国人の名前を覚えるのがちょっと…という方は、あまり一つ一つのエピソードに拘泥することなく流れに任せて読んだ方がよろしいかと。 もう一つ、こっから下は本当の独り言。「巻末特別エッセイ」で作家の柳田邦男さんが言っている次の部分が印象に残ったのでメモ。 書く対象の事件が大きなものであれば、事件発生のホットな時点で、各種のマス・メディアがセンセーショナルに大きく報道する。時にはうんざりするほど、過剰な情報が流される。(中略)ところが、五年、十年と経つうちに隠されていた秘密文書が見つかったり、沈黙していた関係者が口を開いたりすると、事件の姿形や内実が通念化していたものとかなり違うものであることがわかったり、感動的な秘話が明らかにされたり、事件の歴史的な意味が分かったりする。だから、事件当時に取材した記者が《あの事件については自分がみな知っている》と思いこんでいても、後になってノンフィクション作家による事件の再発掘や再検証をした作品を読むと、そこには知らなかった事実がぎっしりと詰まっていたということが、しばしば起こるのだ。しかも、年月が経っていても、かえって人物の一人一人が生き生きと描かれるようになる。 このことはノンフィクション作品が担っている役割と重要性を示すものだ。その意味で、ノンフィクション作家は、ジャーナリストと歴史家の両方の領域に片足ずつを突っこんで仕事をしている表現者だと言えるだろう。 「ノンフィクション作家が羨ましい」と時々思ってしまう自分を見透かされているような気分。そんなこと考えてちゃ仕事にならんぞ、と自分に戒め。
読書管見・『タイタンの妖女』
2006年04月03日
カート・ヴォネガット・ジュニア(著)浅倉久志(訳)『タイタンの妖女』(早川書房 ISBN:4150102627) お笑いコンビ・爆笑問題の太田光がもっとも感銘を受けた本としてしばしば紹介しているSF小説。さっき「はてな」で検索かけてみたら、やはり『爆笑問題のススメ』最終回を見て購入した人が多いようです。私もそのクチですが。 すべての時空にあまねく存在し、神のごとき全能者となったウィンストン・N・ラムファードは、戦いに明け暮れる人類の救済に乗り出す。だが、そのために操られた大富豪コンスタントの運命は悲惨であった。富を失い、記憶を奪われ、太陽系を星から星へと流浪する羽目になったのだ。最後の目的地タイタンで明かされるはずの彼の使命とはいったい何なのか?(裏表紙紹介文より) 本作が言いたかったこと、漫画版『風の谷のナウシカ』とちょっとだけ重なっているところがあるように思います。(以下、ネタバレあり)
「時間等曲率漏斗」の中に落ち、過去・未来と現在を自由に行き来できるようになったラムファードは、自分の計画のために、アメリカ随一の富豪、コンスタントを屋敷に招き、自分が「見てきた」コンスタントの将来を伝える。それは「火星に連れて行かれ、ラムファードの妻との間に子供をもうけ、その後水星・地球を経た後土星の衛星タイタンにたどり着く」というものだった。ラムファードの「予言」を拒もうとする彼の妻ビアトリスとコンスタント。しかし… コンスタント、ビアトリスのみならずラムファード、果ては人類全体の営みまでもが結局他人に利用されていたに過ぎなかった、しかも何とも下らない目的のために。このことが最後に明かされるのですが、それを受けてビアトリスは次のように語っています。 「『わたしは決して』」とビアトリスは自分の著書を朗読した「『トラルファマドール星の力が、地球の事件となんらかの関係を持ったことを、否定するものではない。しかし、トラルファマドール星に奉仕した人びとは、トラルファマドール星がその事件にはほとんどなんの関係も持たぬと言いうるほどの、極めて個性的な方法で彼らに奉仕したのである』」 人間はたとえ誰かに操られ、利用されても、それでも自分の意志で生きているんだ、それでいいじゃないか…。こう作者は言いたいのではないでしょうか。
これと似たテーマををシリアスに描いたのが漫画版『風の谷のナウシカ』であるような気がします。漫画版『ナウシカ』では「汚染された大地と生物を取り替える計画の一環として腐海が造られ、人類も科学者達によって腐海に適応するように造り替えられ、地球の浄化が終われば清浄な世界に耐えられない彼らは用済みになってしまう存在である」という設定になっています。このことを知ったナウシカは、浄化が終わった後の世界を再生する知恵が保存されている「墓所」を破壊するのですが、その際に「たとえ誰かに造られた存在だとしても生命は生命の力で生きている」という意味のことを言っています。 まぁ、本作と『ナウシカ』の設定する「利用する誰か」は根本的には違うのですが、長くなるのでやめます。
爆笑・太田はこれを読んで号泣したと聞きます。何のために生きているのか、そうした疑問を抱えていたときに読んだからだそうです。確かにいいこと言っているよな、と思いつつもそこまで感銘を受けなかった私は、とにかく生きていくしかないことを分かっているのか、それとも単にお気楽なだけなのか、よく分かりません。が、きっと明日からも下らないことで笑い、ちょっとしたことで怒りながら生きていくことでしょう。
読書管見・生島淳『世紀の誤審』&WBC・日本-アメリカ
2006年03月13日

生島淳『世紀の誤審 オリンピックからW杯まで』(光文社、ISBN: 4334032591)
柔道・フィギュアスケート・サッカー・ラグビーなど様々な競技の、主に国際大会における「誤審」の事例とその原因を、単に試合の中だけではなく競技の特質や背景に存在する問題にまで踏み込んで解説した一冊。
「誤審の傾向と対策」について類型化した第九章はなかなか示唆に富んでいて興味深い。対策に挙げられた「観客が競技を見る目を養うこと」は、まさに身につまされる思いです。が、今日はこの対策についてではなく、「国際大会における誤審の傾向」について書かれている内容を紹介し、あわせてWBC・アメリカ戦で起こった「誤審」について私見を述べてみたいと思います。
国際大会で誤審が起こりやすい原因の一つは、「審判も各大陸・世界各国から集められることにある」と生島さんは言っています(第二章)。例えば柔道では間違いなく日本が審判のレベルでは世界のトップです。発祥の地ですから当たり前というのもありますが、「国内で繰り広げられるレベルの高い試合を数多く裁くことが審判の技術向上を助けている」というのが彼の分析です。
ところが、オリンピックなどの国際大会になると、審判にも各大陸枠というものが存在するため、普段レベルの低い試合しか裁かない審判が重要な試合を任されることになる。これが原因となって、記憶に新しいシドニー五輪・篠原-ドゥイエ戦の「誤審」などの事態が生じやすくなる、ということのようです。サッカーのW杯でも同じような事態はよく起こりますね。
二つ目の原因は、「観客の反応」です。典型的な例として、ソルトレイクシティー五輪のスピードスケート・ショートトラックが挙げられています(第五章)。アポロ・オーノ選手の「演技」に過剰に反応した観客の声に審判が惑わされ、韓国の金東聖選手を失格にしてしまった、あのジャッジです。後にサッカーW杯・日韓大会の韓国-アメリカ戦で、ゴールを決めたイ・チョンス選手がこのジャッジを揶揄したパフォーマンスを行ったことで皆さんの記憶にも残っていると思います。本書のこの下り、アメリカの観衆・マスコミの「困ったちゃん」ぶりが詳細に分析されていて面白いです。
もう一つの原因は、「審判も人間なので先入観を持つことは免れない」ということです。例えばMLBで活躍した長谷川滋利投手の話が載っています(第五章)が、「コントロールが良い」という評判を持つ投手に対しては、球審はアウトサイドのストライクゾーンを広く設定してしまう傾向があるそうです。「このピッチャーが自信を持って投げ込んでくるのだからストライクだろう」と。可能な限り排除すべきですが、人間ですからそういう先入観は常につきまとうもの。長谷川投手自身もこれに助けられて戦ってきた選手ですし。同じような傾向はラグビーにも当てはまるそうで、「弱小国と目されるチームが反則を多くとられる傾向がある」ことが、数字と共に示されています。
さて、翻ってWBCの二次リーグ・日本-アメリカ戦。日本はサヨナラ負けを喫しましたが、この試合、明らかな「誤審」がありました。
プレーのあらましは下記の通り。「」内は「試合直後のマスコミの報じ方」です。
3対3の同点で迎えた8回、日本は1死三塁のチャンスに岩村明憲三塁手(東京ヤクルトスワローズ)がレフトフライを打ち上げ、西岡剛二塁手(千葉ロッテ)が三塁からホームに生還。タッチアップが早かったというアメリカ側のアピールプレー(西岡選手がいた三塁に送球してベースタッチ)に対し、「二塁塁審(三塁塁審はフライの捕球を見ているため、三塁ベースには二塁塁審がカバーにまわる)はセーフの判定」。しかし「米国ベンチ側の抗議を球審が認めて判定が覆り」ダブルプレーが成立、得点は認められませんでした。
私は敗因としては「7回の攻めの拙さ」の方が大きかったと思っていますが、そのことを差し引いてもこの「誤審」が大きな問題であることに変わりはありません。
この場面、まず「球審が判定を覆した」ことについては、こちらの最後の部分で二塁塁審には判断の権限がないとの説明がなされており、「覆した」というのとは少し違うようです。確かに球審は捕球する外野手と三塁ランナーを同時に視野に収めることは出来ます。ですからここでは「誤審」は起こっていない。
【追記】エントリーアップ時に書き忘れていたことを二つ。
「二塁塁審の権限ではない」という説明が合法的なものであるかどうか、ルールブックなどで確認したわけではありません。
また、「いったん下された判定が覆された」という表現、報道を読むと「ホームインが取り消されたこと」を指すのか、「アピールプレーに対する二塁塁審のジャッジを球審が取り消したこと」を指すのかはっきりしません。前者だとすれば、少なくとも西岡選手がホームを踏んだ時、球審はホームインを認める「セーフ」のジェスチャーをとっていなかった気がします。その後画面が切り替わってしまったので、最後まで球審がホームインを認めなかったのかは分かりません。
【追記の追記】
やはり「二塁塁審の判定を球審が覆した」ということで間違いないみたいですが、どうも「二重に越権行為があった」ようです。
次に「西岡選手のタッチアップが早かったか否か」ですが、私が言う「誤審」はこの判断です。VTRを見る限りではレフトが捕球してからスタートを切っているように見えます。日本にとって不幸だったのは、このフライが浅かったということです。外野からの返球が大きく逸れ、結果的に俊足の西岡選手は滑り込むことなく悠々とホームベースを踏みました。しかし、「浅いフライの時にはランナーは早くスタートを切りがち」という先入観が審判の判断を狂わせたのかも知れません。
もう一つ先入観として、「日本がスモールベースボールを標榜している」ことも審判の頭の中にあったのではないでしょうか。「スモールベースボール」とは、バント・盗塁・進塁打などを駆使して、1点を確実に狙いに行く戦術を指します。ホームランなどの長打が期待できない日本がとらざるを得ない戦術ですが、これが「日本は打てる手は何でも打ってくる」と脳内変換された時には、こうした細かいプレーに厳しいジャッジが下されることになってしまう。
この試合が実質「アメリカのホームゲーム」であることも影響したかも知れません。優勝候補であるアメリカがまた敗れることがあれば、大会自体が大変なことになります。ただし、「背後での圧力」を短絡的に指摘する論調に、私は与する気にはなれません。根拠のない「圧力」云々で同情するのは、アメリカのホームゲームであることを認めた上で、おそらくこうした事態すら想定して戦っているであろう選手の「覚悟」に対し礼を失していると思います。第一、「じゃあ日本でやるゲームで有利な判定が下されることはないのか」と聞かれたら、それを否定する自信は私にはありませんし。
結局今回の「誤審」は、日本がまだまだ「弱小国」と見なされていることが災いしたと言えそうです。逆の立場だったらアメリカに対してああいう判定は下されないと思います。「おそらくサッカーW杯・ドイツ大会でも同じような事態が起こるのではないか」と私は思っていると共に、覚悟もしています。少なくとも、韓国は「復讐」を受けることになるだろうという生島さんの意見(第九章)は、残念ながら現実となる可能性が高い。
「残念なことだが、誤審はこれからもなくならない(まえがき)」以上、我々は常日頃から「観客の目が肥えていれば、誤審は防ぐことが出来るのだ(同上)」と言う生島さんの言葉を噛みしめて観戦するしかありません。もちろん、札幌の試合においておかしな笛が吹かれれば不満の声を上げることも忘れずに。そのことがスポーツ文化の定着につながることを信じて。
選手は一所懸命戦いました。アジアラウンドの韓国戦のようなひ弱さは感じなかった。こうした素晴らしいゲームと、そして「誤審」をも積み重ねることで、本当の意味での真剣勝負をアメリカに挑む資格が得られると信じたいものです。
読書管見・L.コリンズ/D.ラピエール『さもなくば喪服を』
2006年02月17日

ラリー・コリンズ/ドミニク・ラピエール(著) 志摩隆(訳)
『さもなくば喪服を 闘牛士エル・コルドベスの肖像』(新装版・早川書房 ISBN:4152086432)
スペインの生んだ伝説の闘牛士、"エル・コルドベス(コルドバ人)"マヌエル・ベニテスの半生を綴ったノンフィクション。
マヌエル(マノロ)・ベニテス。1960年代のスペインで国民的人気を博した闘牛士。本書は、彼のマドリードでのデビューを軸に据え、彼及び彼の一家の遭遇した貧困、スペイン内戦、マノロの故郷からの追放、「マレティリャ(小さな旅行鞄。転じて闘牛士志望の若者のこと)」としての長い日々、故郷パルマ・デル・リオ凱旋などにまつわるエピソードで構成されています。
特に、彼が闘牛士としてのデビューを果たした故郷パルマでの闘牛の場面は本書における一つのクライマックスであり、私が読んだ・見たスポーツの場面に関する描写でこれほど息を呑むような思いをしたのは、『一瞬の夏』のソウルでの試合・映画『運動靴と赤い金魚』の「マラソン大会」以外にありません。ここを読んで、あらためて巻頭のモノクロ写真を見るとその凄味が伝わってきます。
そして、マノロはこのデビュー戦を境に「狂った夏」へと突き進んでゆくのです。
「狂った夏」とは、彼が一気にスターダムにのし上がってゆく過程に冠せられた形容ですが、「なぜ国民を『狂わせる』に至る英雄になり得たのか」という問いに対する答えが、本書の序盤から周到に用意されています。
第一に、マノロのような若者が数多く存在したこと。マノロと共に故郷を追われ、その後の行動を共にしたものの、一人前のマタドールとなることは出来なかったフアン・オリリョ。物語の途中、幾度となく登場するマレティリャ達。角傷を受け死に行く若者…。マノロは貧困から這い上がろうとする者達のシンボルだったのです。
第二に、変わりゆく闘牛界・開かれてゆくスペインという国の象徴として彼が登場してきたことが挙げられます。英雄的闘牛士達の死の後を継ぎ、伝統的な優雅さではなく型破りな手法と類い希な勇気を披露する彼の登場は、内戦とそれに続くフランコ政権による「停滞」から脱却しつつあるスペインという国の縮図でもあった。何か我が国における力道山を彷彿させます。もちろん直接見たことはありませんが。
本書の構成は、マドリードの闘牛場での一日と、マノロが闘牛士になるまでの道のりを交互に展開するというものになっています。ある象徴的出来事と、それまでのその人の歩みを交差させ、最後にその出来事にストーリーを収斂させてゆく、現在ではノンフィクションの「王道」となった手法です。マドリードで相対する牡牛の「欠点」を即座に見抜く卓越した能力から、いかにしてそれを身につけたかを語る次章へ。これから起こる悲劇を予感させながらも故郷への凱旋とデビューに話を移し、「狂った夏」における輝かしい成功の物語の後に、再び悲劇の舞台へと読者を引きずり込む…。
タイトルにも用いられている、エル・コルドベスが故郷で闘牛士としてデビューする際に姉に語った次の一言は、これ以上ない程美しく、それでいて何とも胸に迫るものがあります。
「泣かないでおくれ、アンヘリータ、今夜は家を買ってあげるよ、さもなければ喪服をね」
余談その1。オフィシャルブログなので、一応札幌に関係のある気配を漂わせておこうかな、と(笑)。
「英雄的存在」というのは、その人の資質だけでなく、時代背景など様々な要素が絡み合って「生み出される」ものだ、と思います。つまり、優れた選手であると同時に大衆がシンパシーを感じることの出来る歩み方を彼がしているかというのが、ただの良い選手と英雄的存在を分ける要素の一つなんでしょう。その意味で、三浦知良が、Jリーグ誕生といういい時期に日本に帰ってきたこと、「ドーハ」とフランス大会でのメンバー落ちという二つの「悲劇」によって広く大衆に知られる存在たり得ている一方で、奥寺康彦など「カズ以前の名選手」はサッカーファンの間でしか認知されていない。別に英雄扱いされたいという理由だけで選手はやっているわけじゃないでしょうけど。
で、人気のためには英雄的存在がいた方がいいわけで。若貴世代引退後の大相撲はあの通り。プロ野球は長嶋・王を失ってからじりじりと人気を下げ、イチローが出てきたと思ったら向こうに行っちゃうし、挙げ句病に倒れた長嶋さんに未だにすがりつこうとする「人々」…。
いなくても競技そのものの魅力で売れば良いのかも知れませんが、「これからを担う大事な存在」である子供にはそれが通用しないのではないかと思います。現に「カズさん」でサッカーを始めた世代が今Jリーグに入ってきていますからね。札幌にもそろそろそうした存在が欲しいところです。ただ、「選手を育てて売る」事に徹しないと生き残れそうにない札幌がそうした選手を持つことが出来るかどうかは難しい問題だと思いますが。
中田英寿以降の日本サッカー、今のところそうした英雄的存在を持たない札幌…。うーん。
余談その2。本書のBGMに、と考えて購入したのはNHKスペシャル「映像の世紀」のサウンドトラック(2枚)。本作を手掛けた作曲家・加古隆氏はドラマ「白い巨塔」のテーマでもおなじみ。一闘牛士の半生を綴る物語であると同時に、20世紀初頭から中期にかけてのスペインという国の歩みをも語る本書には、やはり20世紀を素晴らしい構成で語ったNスペ史上に残る名作「映像の世紀」のテーマが相応しいだろうと。理由はもう一つ。お気づきの方もおられるかと思いますが、メインテーマのタイトルは、コリンズとラピエールによるもう一つの名作のタイトルに用いられた言葉から来ているというのも選曲の理由です。
そう、タイトルは、「パリは燃えているか」。
こちらも近々読もうと思っているのですが、長いんだよなこれが(笑
読書管見・桂米朝『落語と私』
2006年01月21日

桂米朝『落語と私』(ポプラ社 ISBN:4591089673)
著者は戦後上方落語の復興に尽力した「四天王」の一人、人間国宝・三代目桂米朝。落語の技法や楽しみ方・歴史に、自らの落語に対する認識等を織り交ぜて綴った落語論。以前も書きましたが、中学生の頃から米朝さんが好きで、ラジオでこの人の落語をよく聞いていました。
最近秘かに落語がブームになっているようです。本書はもともと中高生向けに書かれたようですが、ちょっと聞いてからこの本を読むと、落語の奥の深さが理解できるのではないでしょうか。
落語はやはり寄席に行って鑑賞するのが一番、と米朝さんは言います。
落語のネタを収録した本はたくさんあり、私も持っています。しかし、「落語は文学とは違う」と米朝さん。それは演者の腕次第で名作とされている話がくだらないものに聞こえることもあれば、話としてはあまりうまくできていないものでも面白くできる。その意味で文学とは言えないのではないか、というのが米朝さんの考えです。
例えば落語の入りによくある、「こんにちは」「おう、こっちへおはいり」。これを文字だけで見るのと、噺家が「演じる」のとでは雲泥の差がある。「おはいり」を笑顔でやれば待ちわびていた客が来たことになるし、しかめ面でやれば「またヤなヤツがきよったで」ということになる。厳かに発声すれば説教の一つでも垂れてやろうと待ちかまえていたことになる。噺家の表情の作り方で全く異なった意味が付与されるのです。また、ここを見るだけでちゃんと稽古したかどうかが分かる、とも米朝さんは言います。(【独り言】…うーん、何だか報道の読み方に通ずるものがあるような気がします。)
こうした「表情と言葉の融合」なら講釈師や舞台俳優などでもできますが、噺家の特色は、扇子と手ぬぐいという限られた小道具を使って様々な所作を具現化してしまうところと、複数の人物を一人で演じきってしまうところにある、と米朝さんは続けます。
例えば扇子。仰々しく腰のあたりから引き抜けば刀になるし、ちょっと広げて立てて置けばお銚子。手ぬぐいは帳面にもなり、財布にもなり…拍子木をトンと鳴らすことで場面の転換・時間の経過を示す。こういう小道具と、それを用いた所作が現実味溢れる演出を生んでいるのです。
また、講談などは演者自身が話を語る形式をとっていますが、落語は噺家が複数の人物を演じわけるとともに場面説明にほとんど言葉を費やさない。基本的に「枕」と呼ばれる前置きが終われば噺家=語り部自身が顔を出すことは極度に少なくなる。
だからこそ、寄席で見ることで、表情の作り方・間の取り方が伝わり面白味がますのだ、と言うのには、なるほどの一言です。
一方で、数ある古典芸能と落語は本来肩を並べるべきものではない、とも言っています。落語に登場するのは平凡な人々で、別に何か教訓めいたものを示すわけでもない。「これは嘘ですよ、おどけばなしなんです。だまされたでしょう。アッハッハッハ」…。これが落語本来の姿勢だ、と。私なんかはこうした姿勢にこそ大きな魅力を感じます。
この本によって、「落語は今で言うところのマルチメディアだ」という自分の考えが明確に整理出来ました。言葉と所作と小道具と。お囃子という音楽による演出もある。歌舞伎・浄瑠璃・狂言といった既存の芸能のいいところをとって登場してきた、江戸期における「最先端」の話芸。現代まで生き残っている理由がよく分かりました。
読書管見・沢木耕太郎『凍』
2005年12月30日

沢木耕太郎『凍』(新潮社 ISBN:410327512X)
『新潮』2005年8月号に「百の谷、雪の嶺」というタイトルで全文掲載された作品。登山家の山野井泰史・妙子夫妻がヒマラヤの高峰・ギャチュンカンに挑み、壮絶な体験の末に生還するまでを描いたノンフィクション。
この本が「2005年で二番目に感銘を受けた本」となったのは、「誰か・何かと共に歩むこと」の一つの理想型というものを教えてくれたからです(以下、ネタバレあり)。
…まぁ、ノンフィクションにネタバレも何もあったものではないのですが、山野井夫妻、ギャチュンカン登頂のエピソードをあらかじめ知っている人とそうでない人とでは読み方が違うと思うので。ちなみに私は知らないで読みました。
本書は、ギャチュンカン北壁への挑戦を語りつつ、登山家としての山野井泰史・妙子の半生を描くという構成になっています。二人とも日本を代表するクライマーでした。「でした」というのは、ギャチュンカンからの生還の際に二人とも凍傷で指を何本も失っているからです(妙子はギャチュンカン登頂以前にすでに両手両足20本のうち18本の指を第二関節から失っていましたが)。ただ、それでも彼らは、かつてのように登ることはできなくなったものの登山は続けており、その意味では今もなお現役のクライマーではあるのですが。
当初はギャチュンカンの北東壁を目指していたものの、現地で困難さを認識した山野井は、北東壁をあきらめ北壁を選択、ソロ(単独登頂)ではなく妙子と共に登ることになります。卓越したクライミング技術と状況判断能力を持つ山野井、屈強な肉体と精神力を兼ね備えた妙子。二人はお互いを理解し合い、助け合い、山に挑んでいきます。不調のため頂上を目前にアタックを断念する妙子と、彼女に「いい頂」を登らせてやりたかったという想いを抱えつつ登る山野井…。
こう書くと「夫婦愛」を描いた作品のように思われるかも知れません。しかし、そのような生やさしい感情が通用しない世界であることは、下山時に雪崩に襲われ滑落した妙子がロープで宙づりになった際のくだりが表してくれます。
お互いの体をロープでつないだ状態で雪崩の直撃を受け、妙子は50m下に滑落。山野井はロープを引き続けながらも妙子が死んでいる場合を想定し、ロープを少しでも長く残すため妙子の体のところまで降りていき、彼女の体に近いところでロープを切(り、妙子の死体を1000m下に落下させ)るシミュレーションを頭の中でやってのける。一方妙子は、宙づりの状態から何とか岩場にとりつき、声の届かないところにいる山野井に生きていることを伝えるために、冷静に体からロープを外す…。
そこにあるのは「麗しい夫婦愛」などではない。彼らは山に登り始めると基本的に「自分を守る」ことを最優先に考え、行動している。自分が動けなくなればパートナーをも死に追いやることになる、そのことを常に念頭に置いた上でお互いを信頼し、サポートし合っている。相手を想う気持ちと、まず自分が生き残ることを考える冷徹な判断と…。登山の世界では常識なのでしょうが、我々の生活にも通ずるものがあると思います。
「美しい、でもこれは難しいな」というのが、彼らの関係に対する率直な感想です。まぁ、彼ら自身がとんでもない精神力の持ち主ですから。指無くしても結構平然としていますからね。誰もが山野井夫妻のようにストイックにとはいきませんが、チームをサポートすること、誰かと共にありたいと願うこと…。その前に、まず、自分が自分の足で立つ、歩む。当たり前のように思えるけれど、忘れがちなことですね。あらためて気付かされました。
登山は登頂よりも下山にこそ危険が伴う、というのは知識としては持っていましたが、それを圧倒的な迫力で、しかし仰々しい表現は控えた筆致で伝えてくれる後半部分はかなり読み応えがありました。「登ることと降りることは表裏を為している」という登山の構図や「頂から降りることの難しさ」に対する描写が、かつて筆者が『敗れざるものたち』や『王の闇』で描いた世界を象徴している、というのは深読みしすぎでしょうか。前半の、登山のスタイルや用具などに関する細かい叙述が煩わしいと感じる人もいるかとは思いますが、このような細かい描写は彼の文章のスタイルなので我慢して読むしかありませんね。筆者久々の「人物に焦点を当てた」ノンフィクション長編、ごちそうさまでした。来年は「一瞬の夏の続き」に期待。(文中、敬称略)
山野井泰史さんのプロフィール・登頂歴などについてはこちら
http://www.evernew.co.jp/outdoor/yasushi/yasushi1.htm
山野井さんには『垂直の記憶』という著作があり、読み比べてみようと思って先日入手しました。さらに本レビュー作成中に偶然付けたテレビで、山野井さんが、1/14(土)からNHKで放送される「氷壁」(全6回/原作:井上靖)というドラマの技術指導をされていることを知りました。私はこういう「サイン」を大事にする質なので、これからも山野井さんについて色々調べてみたいと思っています。
読書管見・木村元彦『オシムの言葉』
2005年12月26日
 木村元彦『オシムの言葉』(集英社 ISBN:4797671084)
木村元彦『オシムの言葉』(集英社 ISBN:4797671084)
サブタイトル「フィールドの向こうに人生が見える」。この言葉が、この本の、オシムという人の全てを言い表しているように思えます。
いうまでもなく、イビツァ(本名イヴァン)・オシムは、90年ワールドカップでユーゴスラビアを率い、チームをベスト8に導いた後、EURO92を控えた時期に始まった内戦を受け代表監督を辞任、海外のクラブを渡り歩いた後に、市原(現在千葉)の監督として来日。限られた戦力を最大限に活かすその指導法で、千葉をJリーグカップ優勝に導いた名将です。陳腐な表現ですが「名将」以外に思いつかない。「知将」はちょっと違う気がします。
この本は、「千葉でのチーム作り」と、「指導者としての祖国での経験・内戦により被った苦難」の二つのテーマに基づき書かれています。千葉というチームの戦術について語る資格はないし、実際に見ればいいだろう(再来年対戦する時に)、ということで、「なぜ千葉の選手はオシムを信じてあれだけ走ることができるのか」を知るために読んでみました。
「オシム語録」などという名称を与えられ、その独特な語り口が注目を集めるオシムですが、この本を読むと、単に奇をてらってのことではなく、全ての言葉に何らかの意味を、メッセージを込めて発していることに気付かされます。時にはマスコミを通じて選手にメッセージを送るためであったり、また時には浮き足立つ周囲に警告を発するためであったり、あるいはメディアの「幼稚さ」に対する叱責であったり、と。
こうしたメッセージを、それぞれの場面に適した形で発することができるようにするには、やはりその人の歩んできた人生がものをいうのだと思います。内面から出た言葉だからこそ、そこに込められた心も相手に伝わるのだ、と。
「叱る」と「怒る」の違いはそこに相手を思う気持ちがこもっているか否かだ、と常日頃思って行動しているのですが、オシムの言葉は「叱る」のお手本のようだと思いました。そして内面から出た言葉であるからこそ、真似のできないものだ、とも。まずは自分自身の内面を磨いて、それからですね。
その人間性をどこで身につけたのか。傍観者はやはり内戦に伴うつらい経験にルーツを求めたくなるのですが、オシムはそれについて次のような言葉で語っています。
「確かにそういう所から影響を受けたかも知れないが……。ただ、言葉にする時は影響は受けていないと言ったほうがいいだろう」
オシムは静かな口調で否定する。
「そういうものから学べたとするのなら、それが必要なものになってしまう。そういう戦争が……」(p.129)
このくだりを読んで、彼の人間性をほんの少し垣間見ることができたように思います。
以下、レビューとは関係のない余談。2006年ワールドカップの抽選。セルビア・モンテネグロ(SCG)は「スペシャルポット」なるものに入れられ、アルゼンチンのグループに入った。これは「同じグループにヨーロッパは二か国までしか入らない」という原則を逆手に取った「いじめ」以外の何者でもない。SCGは他のヨーロッパ諸国より高い確率(2/3)でブラジル・アルゼンチンと同じ組になるようにしむけられただけ。いまもってヨーロッパの「鬼子」扱いである。政治とサッカーは別物、などと綺麗事を言うつもりはない。これが現実。
以下、またしても余談。発売日・読了日から随分日が経ち、すっかり乗り遅れた感のある本レビューにはやはりおまけが必要だろうということで、コレ↓
左がオシムのサインです。我がサッカー仲間であるところの「ジーコと握手したことのある、「コロンビアの英雄」の名をハンドルネームとする、千葉在住、でも増田と柳沢にダメ出しばかりする鹿サポ」な方に、わざわざ練習場まで行って入手していただいたものです。コレ↓がアップ。
で、問題です。右のサインは誰のものでしょうか?(コレ↓)
上記「うんたらかんたら」の方と身長体重が全く同じ(ヒントにならんなこりゃ)、「オシムの申し子」のものだそうです(私も分かりませんでした)。
読書管見・五木寛之『みみずくの夜メール』
2005年12月01日

五木寛之『みみずくの夜メール』
(幻冬舎 ISBN:4344407008)
頭がオーバーヒート気味・「ちょっと思い詰めすぎかな」と思った時にお薦めの本。
タイトルは「ヨルメール」と読みます。朝日新聞に連載されていたエッセイの文庫版。
この本を読んでまず感じたのは、五木寛之という作家は、結構いい加減な人なんだな、と(笑)。
例えばこの人、歯を磨くことが大嫌い。「歯を磨かないと恐ろしいことになる」と聞かされてもこんな感じ。
「一日やすみ、二日なまけして、週末となる。仕方がないから日曜日の午後、一週間分まとめて磨いたりする。テレビを見ながら一時間以上もゴシゴシやっていると、歯ぐきから血が出てきて、すこぶる痛い。(「歯垢と健康の挟間に」)」
イヤ、そりゃ痛いでしょ(笑)。挙げ句の果てに、
「それにこりて、最近では気がむいたときに、ちょっとだけ磨くことにした。これが妙に具合がいいのである。(同上)」
などと言い出す始末(きれい好きの人、五木さんに代わってゴメンなさい)。
他にも作家のくせに筆無精だとか、夜更かしばっかりしている(これは作家だから仕方ないのか。でも読めば分かるけどヒドイんですよ、この人の夜更かしは)とか。ああ、いい加減(笑)。
でもそれは、ただだらしないだけという「いい加減」ではなく、ありのままの自分・ありのままの周囲を受け止めながら生きてゆくのが上手いという意味での「いい加減」さだな、と。今の自分に欠けている部分だと思います。「人間、いろんな生き方があって良いじゃないか」と諭されている気分がします。
私にとって一番堪えたのは、どうしてもウマの合わない人間もいる、ということを書いた「人の性格は直らない」の、この部分ですね。
「真情あふるる直言、苦言も、ありがたくはあるが、正直に言って、うっとうしいのだ。
気持ちが萎えているときなど、ことにそうである。相手の意見が、的を射たものであればあるほど、うんざりする。」
でも五木さん、あなたも若い頃は「人の顔色も見ずにズバズバ言いたいことを言う」タイプだったんですよね?ボクも変われますかね?
あ、そうか、エッセイって「固まった答えを提示するものではありません」でしたね(笑)。
読書管見・沢木耕太郎『彼らの流儀』
2005年11月26日

沢木耕太郎『彼らの流儀』
(新潮社 ISBN:4101235120)
「ノンフィクション作家」と紹介されることの多い彼ですが、コラムも結構書いています。これがその一つ。対象に真摯に向き合い、かといって過度にのめり込まない彼のスタイルは、長編もさることながらコラムでこそ活かされるのではないか、と思っています。
『彼らの流儀』でも、「発光体は外部にあり、書き手はその光を感知するに過ぎない」(「あとがき」より引用)という彼のコラムに対する定義が貫かれています。
スーパースターを父に持った野球選手の想いとそれを見守る母を描いた「ナチュラル」、大晦日に新しい手帳の連絡先に誰の名前を書き込むか考える独身女性の心を綴った「手帳」、あるヨット乗りの自死をめぐる「来信」と「返信」、有名人の芸名と同じ名前を持つ男性の率直な感想からなる「我が名は…」…
ただ、私にとって最も心に残っているのは「表紙」と、それにまつわる私の体験です。
数年前、何事も上手くいかずふさぎ込んでいた時期がありました。「どこかに答えはないか」。本棚を引っかき回す日々が続いていました。そしてこの本を手に取った時、あっ、と思わず声を挙げてしまったのです。「この馬…」
表紙に使われている絵には、向こうからやってくる列車と黒い馬が描かれています。その馬が、列車に向かって駆け出していることに、それまでの私は気付いていませんでした。よく見もせずに、じっと佇んでいるだけだと思い込んでいたのです。あるいは私の心がそう見させていたのかも知れません。
そうではなかった。馬はなぜかは分からないけれど、列車に向かって駆け出したのだ…
あなたの目には、この馬がどのように映りましたか?
「クレイになれなかった男」の今
2005年11月10日
 内藤利朗/写真 沢木耕太郎/文『カシアス』
内藤利朗/写真 沢木耕太郎/文『カシアス』
(スイッチ・パブリッシング ISBN:4884180151)
昨日、逝ってしまった人の話を書きました。その時、この人の話も併せて一つの文章にしたかったのですが、うまくまとめられそうにないのでやめました。
カシアス内藤という人の話です。
私は、さる友人に紹介されて以来、沢木耕太郎さんの一連の作品を読み漁っています。その中に『一瞬の夏』という作品があります。カシアス内藤というボクサーの再起のプロセスを描いたノンフィクションです。しかし、ただその過程を取材したというものではなく、沢木さんはカシアス内藤のジムの移籍問題やマッチメークまで携わっており、トレーナーのエディ・タウンゼント、カメラマンの内藤利朗と共に一つのチームとして「一瞬の夏」を駆け抜けていくのです。私より上の世代には、自らの青春を重ね合わせて読んだ方もおられるのではないでしょうか。
沢木さん同様、内藤利朗さんもこの過程を収めた『ラストファイト』という写真集を出版していたのですが、それが再編集され『カシアス』というタイトルで出版されていたことを偶然知り、昨日買ってきました。
カシアス内藤があるボクサーのトレーナーをつとめたこと、ジム開設を目指していることは沢木さんの作品や雑誌の記事で読んで知っていました。『カシアス』にはその過程を記録した写真が新たに収録されています。加えて沢木さんの文章も載っているのですが、それを読んではじめて知りました。
カシアス内藤がガンに冒されていたことを。
読んだ時はビックリしたのですが、その後ネットなどで調べたら、根治できなかったものの日常生活を送れるまで回復した彼は、念願のジム開設に成功したようです。ジムのHPを見て、今年の24時間テレビで取り上げられたことも知りました。見れば良かった。
志半ばにして倒れた者もいれば、文字通り何度も倒されながらも立ち上がる者もいる…
「クレイになれなかった男」というのは、沢木さんがはじめてカシアス内藤について書いた文章のタイトルです。その中で「いつか、いつかと思いながら、そのいつかがやってこなかった男」として、また『一瞬の夏』で「いつかを再び目指し、再び敗れた男」として描かれた彼が、ガンを乗り越えて漕ぎ着けたジム開設は、その「いつか」になったのでしょうか。
『敗れざる者たち』(文春文庫、「クレイになれなかった男」収録作品)
ISBN:4167209020
『一瞬の夏』(上)(下)(新潮文庫)
ISBN:4101235023(上) 4101235031(下)
E&JカシアスボクシングジムHP
http://okepi.com/cassius/
プロフィール
性別:男 年齢:30歳代半ば 出身:兵庫県西宮市甲子園 現住地:北海道札幌市 サッカー歴:素人。たまにフットサルをやる程度 ポジション:アウェイ側B自由席 2007/12:加齢に伴い年齢を実態に即した形に書き換えました
最新のエントリー
リンク集
- Jリーグ公式サイト
- コンサドーレ 「梟名」への日記 ~ 12 EQUAL 11 PLUS 1 ~
- CS12番目
- WEBOSS STAFF BLOG
- FANTASISTA!!
- SapporoLoversHeart
- FTの《ミネルヴァの瞳》
- ろまん燈籠
- L’AUTOGOL
- CONSADOLE SAPPORO OFFICIAL SITE
- 旅とコンサ
- フットボールクロニクル オブ サッポロ
- US10周年記念誌制作企画
- TO ALL OVER
- 元多摩日記
- I BELIEVE…一喜一憂
- LOVE さっぽろ
- コンサ海賊チャンネル
- Sapporo on my mind
- Arsenal on my mind
- 青から赤黒
- BEER WEB HOKKAIDO/北海道地域情報サイト
- Jリーグ ファンサイト[ J's GOAL ]
- サッカー オンラインマガジン 2002world.com
- Space MasaMaru Part3
- わからないということだけ(別荘)
- 赤黒業務日誌
月別アーカイブ
コメント
検索