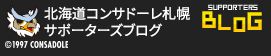読書管見・『パリは燃えているか?』
2006年04月03日
ラリー・コリンズ/ドミニク・ラピエール(著) 志摩隆(訳)『パリは燃えているか?』(上)(下)(新装版・早川書房 ISBN:4152086270(上)・4152086289(下)) 以前紹介した『さもなくば喪服を』のコンビ、コリンズ・ラピエールによるノンフィクション。映画化されており、そちらを御覧になった方もおられるのではないでしょうか。 1944年8月25日、パリ解放。「敵の手に落ちる時にはパリの全てを爆破せよ」という指令に悩むドイツ軍パリ大司令官フォン・コルティッツ、ナチスドイツの手からパリを、祖国を取り戻すべく奔走するシャルル・ドゴールとその部下達、パリ解放により進軍が遅れることを憂慮しドゴールと対立する連合軍の元帥ドワイド・アイゼンハワー、そしてラステンブルクの地下壕に潜むアドルフ・ヒトラー…。しかし、本作の真の主人公はパリ解放を願い、またパリ防衛を遂行するために戦った市民・兵士一人一人であると言えるでしょう。 本書には、1000人に及ぶ人々に対するインタビューの結果得られた「8月25日」に関わるエピソードが収められ、それらがリアリティ溢れるストーリーを織りなしています。登場するのはごく普通のパリ市民からレジスタンス、ドイツ兵とさまざま。「彼らにとってのパリ解放の意味」が実に丁寧に描写されており、歴史上の大事件の背後にある人々の営み・意思といったものを鮮やかに描き出しています。 そこに関わる全ての人々にとって、パリ解放はそれぞれ独自の意味を有していた。その意味に向かった彼ら「一人一人の行動の集積」としてのパリ解放…。なるほど、先にこっちを読んでいたから受け止め方がああなったわけだ。昨日の『タイタンの妖女』と、ここでつながりました(独り言)。 『さもなくば喪服を』に比べてかなり細かい場面割りが施されており、展開のスリリングさはこちらの方が断然上。訳文調に弱い、外国人の名前を覚えるのがちょっと…という方は、あまり一つ一つのエピソードに拘泥することなく流れに任せて読んだ方がよろしいかと。 もう一つ、こっから下は本当の独り言。「巻末特別エッセイ」で作家の柳田邦男さんが言っている次の部分が印象に残ったのでメモ。 書く対象の事件が大きなものであれば、事件発生のホットな時点で、各種のマス・メディアがセンセーショナルに大きく報道する。時にはうんざりするほど、過剰な情報が流される。(中略)ところが、五年、十年と経つうちに隠されていた秘密文書が見つかったり、沈黙していた関係者が口を開いたりすると、事件の姿形や内実が通念化していたものとかなり違うものであることがわかったり、感動的な秘話が明らかにされたり、事件の歴史的な意味が分かったりする。だから、事件当時に取材した記者が《あの事件については自分がみな知っている》と思いこんでいても、後になってノンフィクション作家による事件の再発掘や再検証をした作品を読むと、そこには知らなかった事実がぎっしりと詰まっていたということが、しばしば起こるのだ。しかも、年月が経っていても、かえって人物の一人一人が生き生きと描かれるようになる。 このことはノンフィクション作品が担っている役割と重要性を示すものだ。その意味で、ノンフィクション作家は、ジャーナリストと歴史家の両方の領域に片足ずつを突っこんで仕事をしている表現者だと言えるだろう。 「ノンフィクション作家が羨ましい」と時々思ってしまう自分を見透かされているような気分。そんなこと考えてちゃ仕事にならんぞ、と自分に戒め。
プロフィール
性別:男 年齢:30歳代半ば 出身:兵庫県西宮市甲子園 現住地:北海道札幌市 サッカー歴:素人。たまにフットサルをやる程度 ポジション:アウェイ側B自由席 2007/12:加齢に伴い年齢を実態に即した形に書き換えました
最新のエントリー
リンク集
- Jリーグ公式サイト
- コンサドーレ 「梟名」への日記 ~ 12 EQUAL 11 PLUS 1 ~
- CS12番目
- WEBOSS STAFF BLOG
- FANTASISTA!!
- SapporoLoversHeart
- FTの《ミネルヴァの瞳》
- ろまん燈籠
- L’AUTOGOL
- CONSADOLE SAPPORO OFFICIAL SITE
- 旅とコンサ
- フットボールクロニクル オブ サッポロ
- US10周年記念誌制作企画
- TO ALL OVER
- 元多摩日記
- I BELIEVE…一喜一憂
- LOVE さっぽろ
- コンサ海賊チャンネル
- Sapporo on my mind
- Arsenal on my mind
- 青から赤黒
- BEER WEB HOKKAIDO/北海道地域情報サイト
- Jリーグ ファンサイト[ J's GOAL ]
- サッカー オンラインマガジン 2002world.com
- Space MasaMaru Part3
- わからないということだけ(別荘)
- 赤黒業務日誌
月別アーカイブ
コメント
検索