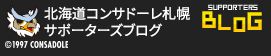その気持ち、分かる(笑)―『オフサイド・ガールズ』
2008年02月01日
『オフサイド・ガールズ』(公式サイト)
映画の日ということで、シアターキノで『オフサイド・ガールズ』を観てきました。
イランでは、宗教上の理由から男性のサッカーの試合を女性がスタジアムで観戦することは禁止されています。本作は、そんなタブーを犯してまでも、W杯ドイツ大会アジア最終予選・イラン-バーレーン戦をスタジアムで観ようとする女の子たちを通して、イランにおける「女性の不自由さ」を描こうとした作品です。
【注意】ここから先は内容に触れています。
冒頭、スタジアムへ向かうバスの中で、ひとり張り詰めた表情で座っている女の子。帽子を目深にかぶり男物のシャツを着ているものの、女性であることは一目瞭然。案の定、ダフ屋にふっかけられてまで買ったチケットで入場を試みるものの失敗。逮捕(!)されスタジアム内の収容スペースへ。そこには同じように捕まった女の子たちが。
見張りの兵隊に試合が観たいと訴えるものの聞き入れられず。スタンドから聞こえる歓声と、時折兵隊が入れてくれる実況を頼りに、試合展開に思いを馳せる彼女たち。途中、トイレに入った一人の女の子が逃げ出したり、捕まった女の子の叔父がやってきたり。やがて見張りの兵隊たちとも少しずつ心が通い始め、さぁこれから後半!というところへ、兵隊たちの上司、「隊長」が現れて…
舞台はアザディ・スタジアム。個人的には中の様子に興味津々でした。と言ってもこの映画、上に書いたとおり彼女たちは試合観戦は叶わず、したがって試合の映像もほとんどありません。観られるのは通路とかトイレの中とかばかり。それでも十分w 有名なメイン・バックスタンドの掛け合い(何て言っているのか意味は忘れてしまいました)も聞こえます。
禁を犯してまで試合が観たい、という気持ち、よく分かります(笑)。私も札幌の試合を観るためにズルしたことは数知れず。違法行為は行ってませんよ。許される範囲のウソ、だけです(苦笑)。ただ、彼女たちが挑む壁は宗教上の問題であって、その点は大いに違いますが。
可笑しいのは、「なぜ観てはいけないのか?」と彼女たちに噛み付かれた兵隊たちがみんなろくな答えを返せないこと。彼らは彼らで「上司の命令だから仕方ないんだ。田舎に帰れば家族だって、家畜だって養わなきゃならないし…」てな悩みを抱えているわけです。田舎から出てきた男の兵隊が、都会の自由奔放な女に手を焼く。「男と女」に加えて、この「都会と田舎」という対立軸も作り手は見せたかったのかも知れません。
一人一人の人物描写に不十分なところがあり、ストーリーに深みが若干足りないかな、と。護送車(といってもただのマイクロバス)の中でラジオで予選突破を聞いてみんなが狂喜乱舞する中、冒頭に出てきた女の子だけが泣き出してしまうのですが、その涙の「理由」をもう少し効果的に物語の中で使えば良かったのではないか、と思います。
テーマはなかなかに深いのですが、とりあえず「サッカー映画」の範疇に入るものとして観たので、ゴールや勝利による興奮・歓喜というのは程度の差こそあれどこの世界でも同じなんだな、というところで。
電影有声・『ZIDANE:ジダン 神が愛した男』
2006年09月20日
『ZIDANE:ジダン 神が愛した男』(2006フランス・アイスランド/監督:ダグラス・ゴードン/95分)
公式サイト
ワールドカップ2006を最後に現役を引退したジネディーヌ・ジダンを追ったドキュメンタリー。 2005年4月23日、リーガエスパニョーラ第33節・レアル・マドリー-ビジャレアル、この試合で17台のカメラを使ってジダン一人を追い続けた映像がひたすら流れつづける。試合展開そっちのけでジダンばかり追っているので、ゴールの瞬間が映っていなかったり、マドリーの出来が悪い前半はほとんど歩いているジダンしか映っていないなど、「ジダンの華麗なプレーとマドリーのスター達を見たい」という向きには全くお薦めできない作品です。「サッカーとロックとモダンアートを融合させた」斬新な映像感覚も、正直あまり伝わってこなかったばかりか、開始直後の映像処理には少々具合が悪くなってしまいました。が、それを差し引いても興味深い点がいくつかありました。 (ドキュメンタリーでこんなこと言うのも何ですが、ここから先は内容に触れています)
まず、撮影がピッチレベルで行われたため、ジダンの息づかいから選手が芝生を踏みしめる音、ボールを蹴るときのインパクトの音、はては観客席のたった一人の手拍子まで拾っており(背景にぼんやり映っていた観客の手と音がシンクロしていたから間違いありません)、スタンドでは感じられない臨場感があったと思います。 さっきも書いた通り、カメラはジダンだけしか追っていないので試合展開は全く分かりません。審判が笛を吹いても何が起こったのか分からない(笑)。ただ、おかげで「ジダンでもボールを触っている時間はこんなものなのだな」というのがよく分かりました。90分の試合の中で一人の選手がボールを保持する時間はほんのわずかです。この試合、ジダンは本当にプレー機会が少なかったのはマドリーのサッカーの質が低いせいもあると思うのですが、後半、見事にロナウドの同点ゴールをアシストして見せました。いくらジダンといえども限られたプレー機会で決定的な仕事をしなければならない。そのことを実感するとともに、逆に言えばあれだけボールに触る機会が少なかったにもかかわらず仕事をしてしまうあたりはさすがだなと思いました。 この映画は日本では7月以降に公開されているようなのですが、本国フランスではどうだったのでしょう?このことはどこかで誰かが書いていた気がしますが、ワールドカップ前だとすると、映画のラストは非常に暗示的です。この試合、相手ゴール前で起こったもめ事でジダンは退場になります。本人が絡んだプレーではなかった気がしますが、小競り合いにあとから入っていってレッドカードを受けてしまうのです。 ドイツでの決勝のことを思うと、映画のラストの言葉、正確には覚えていませんが、「魔法はいつか解ける。それも不意に」という意味の言葉がまるで予言のように思えてきます。 華麗なプレー集、とはいきませんが、思わず笑ってしまうぐらい素晴らしいとラップをはじめとした彼の高い技術は堪能できます。シアターキノ、明後日で終わっちゃいますけど。
電影有声・『THE 有頂天ホテル』
2006年03月15日
『THE 有頂天ホテル』(2005年日本/監督:三谷幸喜/136分)
時は<すべての人にとって特別な日である大晦日>。舞台は<迷路のようなホテル>。その中で<働くホテルマン>と<訳ありの宿泊客>が織りなす最高の奇跡-。(オフィシャルHPより)
「誰も見たことのない極上のノンストップエンターテイメント!」という触れ込みの本作。展開はかなりスピーディー。登場人物も多く、それぞれの人物に関わるエピソードが複雑に絡み合い、「怒濤のように」展開し、「大晦日のカウントダウンパーティー」に収斂してゆく、というのが監督の狙いだったのでしょうが、スピード感を求めるあまり、かえって一つ一つの場面の印象が希薄になっている感が否めません。(以下、ネタバレあり)
印象が希薄になってしまった原因は二つあるのではないかと思います。一つは核になる人物・エピソードが欠けている上に、一人一人の登場人物の心情描写が決定的に不足していたこと。「かつて舞台関係の仕事を志していたホテルの副支配人」(役所広司)が物語の中心に見えましたが、物語は別に彼を中心に回ってゆくわけではありません。あまりにも多くの人物を絡めようとして、そして彼らをスピーディーに動かそうとしすぎたのではないでしょうか。とりわけ客室係(松たか子)は何に悩み、何で吹っ切れたのか分かりません。冒頭、アシスタントマネージャー(戸田恵子)が副支配人のネクタイを直してあげる場面で彼女が同僚以上の感情を彼に抱いていることが示されたので、私はてっきりこの二人のエピソードが軸となって進んでいくものと思って観ていました。肩すかしをくらった気分です。
二つ目は、コメディタッチのヒューマンドラマを目指しているようですが、やはり私には「どっちつかず」という印象しか残りませんでした。感動させる場面の後に笑いを入れる。これはコメディでは王道と言える手法ですが、「しっかり感動させてからひと笑い、で次の場面に移る」というメリハリが利いていなかった気がします。これもスピード感を求めてのことでしょうが、いま自分は笑うことに集中すべきなのか、ストーリーと登場人物の心情を理解することに努めればよいのか、迷い続けたまま終わってしまいました。三谷さんの監督作品ではないですが、彼の舞台作品を映画化した『笑の大学』ではそこのところが非常に良くできていたので、本作品の中途半端さが余計残念です。ただ、『笑の大学』は基本的に二人だけの物語なので、このメリハリがつけやすいというのもありますが。
場面場面では笑えるところもありました。演歌歌手(西田敏行)がバスローブの腰ひもで死のうとするところや、気弱な筆耕係(ホテルの案内掲示などを書く人のこと・おだぎりじょー(注))が書く「謹賀新年」は笑いの王道的手法です。「受賞パーティー」で、カメラがパーンしてきたら案の定戸田恵子がシカのかぶり物してた、ってところも「やっぱり来た」と思った人は多いのではないでしょうか。
そう、コメディって笑うタイミングが予測できる構成になっている部分が多くないと笑えないんだと思います。だから上記の場面はちゃんと笑わせてもらいました。タメがあって、「ココで来るぞ~ホラ来た!」という。私が「吉本新喜劇」な世界で育ったからでしょうか。
話のスピードと観客の予測する速さとがミスマッチを起こしていたように思います。もうちょっとゆっくり笑わせてよ、じーんとさせてよ、三谷さん。
(注)「おだぎりじょー」:「意味はないけれどムシャクシャしたから」オリエンタルラジオが言ってた通りにひらがなにしてみました。
電影有声・『戦場のフォトグラファー』『CAPA in Love&War』
2006年02月05日
『戦場のフォトグラファー ジェイムズ・ナクトウェイの世界』(2002年スイス/監督クリスチャン・フレイ/101分)
『CAPA in Love&War』(2003年アメリカ/監督アン・メークピース/85分)
私には絶対できないと思っている職業の一つに「戦場カメラマン」というものがあります。言うまでもなく、戦場に赴き、当事者の視点に限りなく近づき、時には目を覆いたくなるような現実をカメラで切り取って世界に向けて発信する…。
「いい写真が撮れないとしたら、近寄り方が足りないからだ」
この言葉を受け継ぎ現代の戦争・貧困に迫るフォトグラファー、ジェイムズ・ナクトウェイの実像に迫る前者。この言葉を遺した「先駆者」ロバート・キャパの生涯を描いた後者。何年か前にシアターキノで「戦争映画特集」として同時に掛かっていた二作品をあらためて観てみました。
『戦場のフォトグラファー』
コソヴォ・ルワンダ・インドネシア・パレスチナ・アメリカ…。ニューヨークを拠点に、世界に存在する戦争・貧困を撮り続けるナクトウェイ。本作では、彼のもつカメラにCCDを取り付けて撮影し、対象との距離・撮影しているときの彼の表情などを織り込んでいます。この「カメラに取り付けられたカメラ」が、彼の対象との「距離」を如実に物語ってくれます。コソヴォでは息子を亡くし悲嘆にくれる母親のまさに目の前でシャッターを切り、パレスチナでは暴徒とともに行動し催涙ガスをもろにくらう様が生々しく描かれる…。
こうしたジャーナリストの姿勢に疑問を感じられる方も多いと思います。「目の前で展開されている悲劇を、どうして冷静に撮影などできるのか、自ら手を差し伸べようと思わないのか」。同感です、肝心なときに逃げ出してしまうような多くのジャーナリストに対しては。
映画の中で、彼と共に仕事をした人物が、「彼は『関係者』なのだ」という表現を使っています。暴徒に襲われ、山刀で切り刻まれようとする男を目にして、彼は暴徒に何度も頭を下げて、20分もの間、地面に這い蹲って男の助命を嘆願した、というのです。自分も興奮した暴徒に殺される危険があるというのに。その男は結局助かりませんでした。
他の取材においても、彼は対象に心を開き、対象が心を開いてくれるように接しています。世界の現実を伝えるために写真を撮る、そのためには物理的な「距離」だけではなく心の「距離」も縮めなければならない。「いい写真が撮れないとしたら、近寄り方が足りないからだ」。映画冒頭に出てくるキャパの言葉は、このことを意味しているようです。
このように対象に心を傾け、なおかつ「仕事」をこなすなど、並の精神ではできないことです。実際、彼は前述の「暴徒に切り刻まれた男」の写真を自らの手で撮っています。しかしそれを撮すこと、写真を通じて「世界の現実」を伝え人々を動かすことを、彼は自らに使命として課したのです。意志の強さ、いや、使命感が彼を突き動かしている…。
彼の言葉で、もっとも印象に残ったものです。
「我々(カメラマン:筆者注)は現実を見なければならない。見て、行動しなければならない。我々がしなければ、誰がする?」
ここまで観て、「以前見たとき、ボクは誤解をしていたのではないか?」という、最近抱き始めた予感は確信に変わりました。私はナクトウェイを「冷徹なフォトグラファー」としてしか記憶していなかったのです。決して彼は冷徹さだけで成り立っているフォトグラファーではなかった…。
誤解が生じた理由を確認するために、次にキャパを描いた二作目を見ました。
『CAPA in Love&War』
本名アンドレ・フリードマン。ハンガリー・ブダペスト生まれ。ユダヤ人であることから政治的迫害を受けドイツ・ベルリンへ亡命。やがてドイツからも脱出しフランスへ。ここで写真を仕事としていくために「米国人カメラマン」ロバート・キャパを名乗るようになってから、彼は優れた作品を世に送り続ける。暗殺前のトロツキー・「崩れ落ちる兵士」・オマハビーチ上陸…。
彼はスペイン内戦・日中戦争・対独戦などを、従軍カメラマンとして経験していますが、それは自分を「ジプシー」にしたファシスト達に対する彼自身の闘いだったのかも知れません。その闘いが終わり、ユダヤとしてのルーツであるイスラエルでの取材中に負傷。しばらく一線を退いていたものの1953年に再びインドシナの戦場へ戻り、そこで地雷を踏んで帰らぬ人となりました。
この作品は、生前のキャパと交流の深かった人々に対するインタビューと、彼自身の残した言葉を中心に構成されています。証言者は一様に「彼が如何に愛すべき人間だったか」を語っています。と同時に、若い頃から故郷を離れ、また「アンドレ・フリードマン」から「ロバート・キャパ」という、自らが作り出した人間になったことからくる「寂しさ」を抱えた人間だったということも。
写真の善し悪しを論ずる知識など持ち合わせていないのですが、彼の写真の中で、私はとりわけ人の笑顔を撮ったものに強く惹かれます。特に子供を撮した写真はどれも活き活きとしていて、「これが戦場カメラマンの撮ったものか」と疑わずにはいられないほどです。これも彼の持つ「寂しさ」の裏返しなのでしょう。
とにかく、キャパという人は良い意味での人間くささを強く感じさせる人です。戦争を撮ることの葛藤を素直に吐露したり、酒と女に情熱を傾けたり…。本作は、そのキャパの人間としての魅力に焦点を当てた作品だったと言えるでしょう。
終わってから、やはり誤解の原因は「観た順番」にある、ということが確認できました。以前、シアターキノでは、『CAPA』→『戦場のフォトグラファー』の順に観たのです。しかも続けて。人間ロバート・キャパの魅力を軸に据える前者を観たあとでは、ナクトウェイのストイックさが「冷徹」と映ってしまったのは仕方のないことかも知れません。
ただ…、順序を変えてみたものの結局今回も続けて二作品見たことにかわりはないので、今度は『CAPA』について誤解を犯していそうで怖いのですが(笑
ようやっと本ブログ2本目の映画レビューです。開設時にはもう少し多めに書けるかなと思っていたのですが。まぁ、ゴローちゃんのマネをして「月イチ」を目指す(注)ということで…(笑
(注)「ゴローちゃんのマネをして「月イチ」を目指す」
テレビ朝日の「スマステ5」で稲垣吾郎が「月イチゴロー イナガキセレクション5」なるコーナーを「月1回」で担当しているので、これ幸いと一ヶ月に1本ぐらいでいいか、と思って立てた目標。「まず結論ありき」の悪しき例。
電影有声・『皇帝ペンギン』
2006年01月02日
『皇帝ペンギン』(2005年フランス/監督リュック・ジャケ/ 86分)
皇帝ペンギンの暮らしを、南極の美しくも厳しい自然の映像と共にドキュメンタリータッチに綴った作品。日本語吹き替え版もあるようですが、蠍座で掛かっていたのは字幕版。やはり愛を囁くにはフランス語が一番だなぁ、と(笑
ひょっとしたら外れているかもしれませんが、移動する生き物としての「皇帝ペンギン」を描くというのが監督の意図の一つだったのではないでしょうか。
ご存じの通り、皇帝ペンギンは冬の始まりに冬営地=子育ての場に集まり、パートナーを見つけ、産まれた卵をオスが暖める間にメスは餌を求めて海に潜り、孵化した後はメスがその餌で子供を育て、オスは弱った体を回復させることと子供のさらなる成長のために餌を求めに行く、というサイクルで子孫を増やします。ここまでは知っていたのですが、今回この映画では、一連の行動を「行進」という語で綴っています。
各々が冬営地に向かう「行進」。卵を産んだ後のメスが餌を求め、厚い氷に閉ざされた地帯を乗り越え、海に戻れる場所を目指す「行進」。子供がはじめて氷を踏みしめる「行進」。そして夫婦の別れと子供の独り立ちに向けた「行進」…。
ある種のペンギンは何千キロもの距離を移動するということを『渡り鳥』という別の映画で知ったのですが、皇帝ペンギンにおいても移動は生きることと不可分なものだったのです。
歩く姿がユーモラスと人気を集めるペンギンですが、この映画での歩く姿はまるで「求道者」のよう。陽炎の彼方を歩く彼らの姿は、まさに何かを求めて一心に歩く「求道者」のそれに思えてなりませんでした。
一方で忘れがちですが、彼らは「鳥」であり、他の鳥にとっての飛ぶことに相当するのが「泳ぐ」という行為。餌を求め、また独り立ちしてはじめて海に入った時の彼らの何と素早く、活き活きとして、そして優雅なことか。
自然の厳しさ、美しさを描いた、とても良い映画だったと思います。
余談その1。ブログ設立当初から「映画」というカテゴリーを設け、映画好きを装っていた私ですが、実は今回が蠍座デビューでした。何となく敷居が高い感じがしたので、今まで行くことができませんでした。実際行ってみると、エントランスが広く、喫茶スペースが十分にあり、映画の前に集中・予習するにはうってつけの環境。
狭いスペースに人がひしめくシアターキノでは、「見ず知らずの人だけど間違いなく映画好きの人々」と空間を共有できている実感を得ることができますが、それとは違う良さがあるなぁ、と感じた次第です。
余談その2。人間もアフリカ大陸を起源とする種であり、移動を繰り返すことでこの地球を覆い尽くす生息地域を持つ生き物になりました(とされています、現在最も有力な説では)。移動する先の無くなった人類が次にどこへ向かうのかはわかりませんが、少なくとも個人レベルでは移動に対するモチベーションが遺伝子レベルで根付いているように思います。そして他の動物と決定的に違うのは、人間は移動することで自らの知る世界を広げることができるという点です。どこか知らない世界へ行くことで、知らないことが見えてくる、そして気づかなかった自分も見えてくるのではないか…
つまり何がいいたいかというと、ハイ、旅がしたくなってきたのです。時間も金もないくせにw
プロフィール
性別:男 年齢:30歳代半ば 出身:兵庫県西宮市甲子園 現住地:北海道札幌市 サッカー歴:素人。たまにフットサルをやる程度 ポジション:アウェイ側B自由席 2007/12:加齢に伴い年齢を実態に即した形に書き換えました
最新のエントリー
リンク集
- Jリーグ公式サイト
- コンサドーレ 「梟名」への日記 ~ 12 EQUAL 11 PLUS 1 ~
- CS12番目
- WEBOSS STAFF BLOG
- FANTASISTA!!
- SapporoLoversHeart
- FTの《ミネルヴァの瞳》
- ろまん燈籠
- L’AUTOGOL
- CONSADOLE SAPPORO OFFICIAL SITE
- 旅とコンサ
- フットボールクロニクル オブ サッポロ
- US10周年記念誌制作企画
- TO ALL OVER
- 元多摩日記
- I BELIEVE…一喜一憂
- LOVE さっぽろ
- コンサ海賊チャンネル
- Sapporo on my mind
- Arsenal on my mind
- 青から赤黒
- BEER WEB HOKKAIDO/北海道地域情報サイト
- Jリーグ ファンサイト[ J's GOAL ]
- サッカー オンラインマガジン 2002world.com
- Space MasaMaru Part3
- わからないということだけ(別荘)
- 赤黒業務日誌
月別アーカイブ
コメント
検索