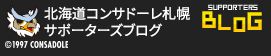そんな「ジャーナリズム」なら
2007年07月13日
Jリーグ担当記者が書く朝日新聞のサイトに、大分トリニータの担当記者が書いたコラムが掲載されている。 http://www.asahi.com/sports/column/TKY200707110469.html 正直に言う。こんな悲しい思いのする記事を久しぶりに読んだ。 感情的になりたい気持ちを抑えながらもひとつひとつ反論していきたい。 先日のJ1、九州石油ドームで開催された大分対Fマリノスの試合。試合後にゴール裏のサポーターが座り込みを行い、不振にあえぐ現状に抗議した。その後大分フロントはサポーターズカンファレンスを行ったが、その一連の事件におけるサポーターの存在について批判をしている……というのがこのコラムの大まかなところ。 自分は大分のサポーターではない。しかし、同じフットボールを応援するものとして思うこと、言いたいことがあるし、自分の応援する札幌というクラブと土地にも繋がる部分があると信じて書く。
このコラムの冒頭では、フットボールの試合を映画に例えて書いている。 >映画をサッカーに置き換えてみる。お金を払って観にいく、という興行と割り切れば、 >私はサッカーも同じだと思う。 まずここから違和感を憶えてしまう。そもそも映画とフットボールなど本質的に置き換えることなんてできない。それはなぜかというと映画はスクリーンを通して見届けるという受動的な行動であるのに対して、フットボールは観客がリアルタイムに、主体的にかかわっていくものであるからだ。すでにできあがっている映画に歓声を送ってもシナリオは変わらないが、リアルタイムに進行するフットボールの試合は歓声や応援でシナリオはどのようにも変わる。そして、フィナーレを「応援するクラブの勝利」に繋げるのがサポーターの役目だと思う。それをどう「割り切って」見に行けというのだろうか?と逆に教えを乞いたいくらいだし、そんな割り切った人間ばかりが集まったゴール裏があるとしたらそれはもはやゴール裏の意味を成さない。ただの「集団」でしかない。 >チームが負け込むと、平気でスタンドに1時間でも2時間でも居座る。 >「社長出てこい」「強化部長、責任取れ」などと怒鳴り散らす。 >選手バスを取り囲み、出て行くのを妨害したサポーターも、これまで担当してきた >複数のチームで見てきた。 (略) >フロントの「つるし上げ」を生き甲斐にしているような、はき違えたサポーターも >実際にはいる。頭を下げさせ、「どうだ、オレが言ってやった」とばかり、 >いい気になっている。 確かに、こういう人間がスタジアムにいることは同意する。札幌にも、もちろんいる。 ひょっとしたらこれを書いている自分自身もその一人なのかもしれない。だって、ここでこうやって新聞記者を「つるし上げ」て「いい気になって」いると思われることもあるだろうから。でもこの人は自分のこのブログを批判できないはずだ。なぜなら、フットボールを映画に例えている冒頭の部分で >酷評をブログにつづる手もある。 って書いているのだから。まあ、そもそもこんな泡沫ブログなんてのは気にしませんよね? そして、もうひとつ大きく疑問に思うのは以下のところ。 >それは、チームへの「愛の裏返し」とは、とうてい思えず、模範的な応援を繰り広げた >サポーター全体の質も下げる。 >試合中にゴール裏で応援するも、ヤジるのも勝手だ。 >しかし、試合終了のホイッスルがなった時点で、 >払った入場チケットの対価は本来、完結し、精算されるべきだ。 だとすると、フットボールはどこまでも「興行」でしかありえないのだろうか?模範的な応援というのは何だろうか?そもそも応援に「模範」なんてないはずなのに。 まあ、おそらく記者氏の考えるサポーターの理想像、「模範的な応援」というのはこんなものだろう。 ―勝っても負けても拍手と前向きな声援に溢れ、どんなにフロントが迷走しても一切の異論を唱えず応援し続ける。礼儀正しく、試合が終わればさっさと帰る。好き好んできたのだから文句も言わず、粛々と― こんなゴール裏、こんなサポーターは機械人形の群れと同じだ。 批判を言うことも許されず、ピッチの外で行われた公式の会合でも責任を問うこともできなければ、サポーターはどこで意見を表明すればいいのだろうか?それとも、そんなことはしてはいけないのだろうか。そんなサポーターに支えられたクラブがどれほどまでに凋落し、いずれは消滅するだろうという想像力すら、この人は働かせることもできないのだろうか? この新聞社は確か「ジャーナリスト宣言」というものを高らかに宣言しているはずだ。 しかしどこまでも上に立った目線でしか物事を書かず、最後に「心を入れ替えろ」だなんて捨て台詞を吐く、この記事がもっとも「ジャーナリズム」とかけ離れているように感じる。 地に足のついた記事が読みたいと思っているだけなのに、札幌でも、日本でも、なんでこんなに読み手の心とかけ離れた記事ばかりが紙面やネットを埋め尽くしているのだろう。本当に読みたいと思うこと、読んで良かったと思う記事はいつになるのだろう、どこにあるのだろう、と不安と同時に悲しく思う。 そしてこの記事を書いた記者氏が、最後で >そんな「12番目の選手」ならいらない。 と書いているのなら、自分もこう言うことにしよう。 そんなくだらないジャーナリズムなら、いらない。
「東京」とフットボール。
2007年02月12日
昨日のエントリで極私的な「東京」への思いをぶちまけて収拾のつかないまま無理矢理に終わらせてしまって(文章としては最低の終わり方だ)、なんとなくもやもやしたまま起きた今日。激しく雪が積もる外を見て出かける意欲を早々になくした僕は、書棚の整理なんかを始めることにした。もともと家にあるのと同サイズ同色で買い増しして設置していたカラーボックスがきれいに(まるで三浦フットボールにおける4バックのラインのように!)並んでいるのだから、中身もきちんと並べようと。そうしてせっせと単行本や文庫本を並べ替えているときに、ある本を持っていたことを思い出した。それが今回のエントリを書くきっかけになった『フットボール都市論』だ。この本で舞台となっているのはパリ、マルセイユ、香港、そして東京。そんなわけで、この本をきっかけとして昨日の「東京」の話を再びしてみたい。今度は個人的な側面からでなく「フットボール」と「都市」という側面から。 周知の通り、東京には二つのJクラブがある。FC東京と東京ヴェルディ。この2チームと、その周辺(いわゆる「首都圏」「郊外」という言葉でくくられる地域)を軸にして「東京」というのはどういう街なのかということを書いておきたい。 まずFC東京と東京ヴェルディにおける「東京性」の差異から。 東京ヴェルディは等々力競技場をホームスタジアムとする「ヴェルディ川崎」として発足した。前身の読売クラブ時代から日本代表を数多く擁して多くのタイトルを獲得してきたのだが、2001年の東京移転初年度にJ2降格の危機に瀕する。かろうじて残留に成功した後、2004年の天皇杯で優勝するものの翌2005年のシーズンではJ2に降格し、今年2シーズン目のJ2を戦うことになっている。 それに比するFC東京は、旧JFL所属の東京ガスサッカー部を母体として創立されたチーム。当初は東京ガス時代から引き続いて深川のグランドで練習し、江戸川陸上競技場や夢の島競技場、西が丘サッカー場などをホームとして戦ってきた。1999年、J1へ昇格すると2004年に初のタイトルとなるヤマザキナビスコカップ優勝を果たす。 この2クラブのプロフィールを比較してみると、J1/J2といったリーグにおける存在位置以前にもっと対照的な点が浮かび上がってくる。日本のフットボールにおける黄金時代を築いたヴェルディと、下町の企業サッカー部からトップリーグまで上がってきたFC東京。歴代の日本代表を多く輩出したヴェルディはテクニックとセンスで魅せるのに比べて、FC東京は知名度にそれほど高くない選手がほとんどで、「部活サッカー」と揶揄されるほどに愚直で運動量のあるゲーム運びをする。なぜ同じ「東京」を掲げるチームが、こんなにも大きく違うのだろう?
まず、一つにはそのクラブそれぞれが生まれ育った土地性があるのではないか。ヴェルディはJ発足当初こそ「川崎」であったが、その前の読売クラブ時代は「東京」のクラブである。当時のニュータウンにおけるシンボル的な存在であったよみうりランドに天然芝4面(!)の練習場を持ち、外国人監督やブラジル人選手を積極的に呼び寄せレベルアップを図った。一方のFC東京は江東区深川というまさに「下町」のグラウンドから企業のサッカー部として設立され、社員選手を中心にして戦ってきた。この「ニュータウン」と「下町」という地域性こそがまず互いのクラブにおける決定的な差異といえる。ニュータウンの先進的なスタイルと、下町の表すいい意味での「江戸っ子」なスタイル。この違いが、そもそもの出発点ではないだろうか。 もうひとつは「都心」の経験だ。 ヴェルディは国立競技場というまさに「都心」の地域で多くのタイトルを獲得してきた経験を経て、東京の調布へと移転した。それに引き替えFC東京は国立は国立でも古き良き東京情緒たっぷりの「国立西が丘」を経て同じ調布へと移転した。そして当然、表舞台のフットボールとそこに立てなかったクラブのフットボールも大きく異なる。J1とJ2のフットボールが違うように。 「ヴェルディ=読売クラブ」が「聖地」で華やかなフットボールを体現して勝つために求めたものは、多少わがままなプレーであっても高い技術を持つブラジル人や日本代表選手の存在であり、それを受け継いで新たな日本代表選手を生み出そうとするシステム。 一方の「FC東京=東京ガス」は、無名であってもチームのために貢献できる粘り強い選手、走れる選手、それを理解して安い年棒でもプレーしてくれる外国人。 東京ど真ん中、千駄ヶ谷に位置する国立霞ヶ丘というまさに「都心」の場所において、国内の「フットボールの中心」を経験したかということそのものが、クラブの歴史とプレースタイルにくっきりと浮き出ていると思う。 象徴的な例として「フットボール都市論」でも触れられていた、2001年2ndステージの東京ダービー、ヴェルディ側のホームで迎えた東京スタジアム(当時はまだ「味の素スタジアム」ではなかった)での試合を挙げておきたい。ヴェルディは当時、北澤豪、小倉隆史、三浦淳宏、武田修宏、前園真聖、永井秀樹といった元日本代表プレーヤーを多く抱えていながらも結果を出せないどころか「2部落ち」の崖っぷちに立たされていた。監督も松木安太郎から小見幸隆へ交代してもなかなか結果を出せないなかで、クラブが選択したのは元ブラジル代表のエジムンドをレンタルで獲得するという「スタープレイヤーのさらなる追加」だった。この選択があまりにも「ヴェルディ的」であるのに対して、FC東京はこの試合をアマラオ、ケリー、サンドロのブラジルトリオを欠く「純国産」メンバーで望んだ。結果的にはヴェルディが勝利してその年の残留を決めたのだが、この状況はFC東京と東京ヴェルディという二つの「東京」を際立たせるには、あまりにも対比的で象徴的な試合ではなかっただろうか。 前述『フットボールの都市論』では、パリ・サンジェルマンをこう評している。 「首都に拠点を置くチームが罹る病気。それは、国家を『代表』するチームになる、と言う幻想である。ナショナリズムとリージョナリズム……言い換えれば、地域主義が曖昧な形で、しかも強く国家主義と連携してしまうのだ。」(P160) この言説は、まさに東京ヴェルディにも言えるのではないだろうか。 そしてFC東京は2004年にナビスコカップを、東京ヴェルディは同じく2004年に天皇杯を獲得したわけなのだが、「東京」と「フットボール」というつながりはここをピークとして弱くなりつつあるのではないだろうか、というのを考えている。それは「郊外」におけるフットボールが強大化して、「東京」を浸食し始めているという現象である。つまりは浦和、千葉、横浜、川崎、柏といった「東京」に対する「郊外」をホームとするチームの台頭である。 この現象はすでに2002年から現れていると考えている。 まず、ワールドカップの決勝は「聖地・国立」ではなく、新横浜という新時代のニュータウン地域に建つ「横浜国際総合競技場(現・日産スタジアム)」であったということ。2002年と2003年にJリーグを連覇したのは首都圏のチームでも、磐田や鹿島といった古参でもなく「横浜F・マリノス」であったということ。さらにはワールドカップだけでなく、世界クラブ選手権(トヨタカップ)決勝戦も国立から横浜国際での開催に移行される。そして2004年には浦和レッズがナビスコカップ制覇、2005年にはジェフユナイテッド市原(当時)の同タイトル制覇、2006年の浦和レッズのリーグ優勝、さらにはタイトル制覇こそならなかったものの川崎フロンターレの大躍進といった事象を通じて、「郊外チームの強大化」が進んでいった。 それと入れ替わるようにFC東京はガーロ監督によるポゼッションサッカーへの転換を図ったが失敗し、降格の危険を感じるほどまでに低迷する。さらに東京ヴェルディは降格、2006年からJ2での戦いを強いられることになる。この入れ替わりが「東京」という街におけるフットボールの力が弱体化していることを表すと同時に、同じ「東京」ブランドのチーム同士の差異に加えて「東京-郊外」という差異も表されたのではないだろうか。 そういった「東京-郊外」という差異は過去の歴史から続く「都市機能を肥大化させる一方の東京都心から人が消え、その都心へ通勤する労働力の供給源」という位置づけであったものだが、近年における「郊外」が持ち出した「新都心」や「新ニュータウン」という、東京をスルーしても生きていける都市の力そのものの上昇とも無関係ではないと思う。「郊外」が十分に主役足り得る機能を持つ都市として完成されたからこそ、そこに注ぎ込まれる経済の恩恵と、そこに住む人々の地元帰属意識の上昇こそが地元のフットボールに大きな影響を与えたのであり、「郊外」のチームが台頭した要因ではないかという思いがある。 それでは「東京」のクラブが再びクローズアップされるにはどうすればよいのだろうかと考えたとき、思い至るのはやはりそれぞれのクラブにおける「ローカリズム」のさらなる追求ではないかと思う。今まで培ってきたクラブの方向性をとことんまで突き詰めてそれぞれのクラブがもつフットボールのスタイルを体現すること、それ以外ないと思う。東京におけるローカリズムの強化。それは秋葉原が一方向(つまりは「萌え」方向に)に大きく突出してローカリズムの成長を遂げたように、ベッドタウンという存在以外にもっと何か突出した存在がなければ地域は成長できないということでもある。「フットボールの街」以外の何かによって地域が成長すれば、そこに根付くフットボールも面白くなっていくものだと思っている。いびつに発達すればするほど、フットボールは逆に面白くなっていく。「いびつであること」を恥じず、その意識をローカリズムに変えて。 最後に、前述書からもうひとつの文章を引用したい。 フットボールは言葉では語り尽くせない。フットボールにとどまらず、どんな言葉であっても世界を正しく語ることはできない。だからこそ言葉があり、語ることがあるのだ。 言葉は、ゴール裏で狂うことと同じくらい大事なことなのだ。 「私たちはハンドの判定の声などに消されることのない強度を持った言葉を見つけなければならない。もしかすると、私がフィールドを眺め続けているのは、そんな言葉を探しているからなのかもしれない。」(P157) ※参考資料・神野俊史著『フットボール都市論』(2002年、青土社) ・東京ヴェルディ1969オフィシャルサイト ・FC東京オフィシャルサイト
Mes que un club
2007年02月03日
ちょっと昔の話になるが、FCバルセロナ(以下バルサ)が、ユニセフに年間数万ドルの援助を行う提携をしたというニュースがあった。もはやバルサはフットボールクラブを超えた存在であり、その向こうにある貧困や差別をも解消していく――そんなクラブを目指そうとしている。そのスローガンが、「Mes que un club(クラブ以上の存在)」というわけだ。世界の貧困と戦う、というのは確かにフットボールを超えた戦いの場所である。バルサのフットボールに魅了され、ファンとなり、その試合をカンプ・ノウで見ることで利益が発生する、その一部が基金となり、世界中の貧しい国々へ送られる。バルサを見ることが、世界の貧困を救う一つの手段となり得るようになったのだ。おそらく、このようなことができるのはバルサだけだろう。(レアル・マドリーもできそうではあるけれどなあ……) 「クラブ以上の存在」と言っても、言い方によっては大きく解釈が分かれるところではある。「クラブ」よりも規模を拡大し、社会的に「単なるフットボールクラブ」以上の存在になろうとする姿勢が一義。もう一義は、「ファンの一人一人の人生において、そのクラブの存在が何よりも大きくなること」がもう一つの意義だ。ゲームにも練習場にも足繁く通い、勝利の時には全世界が幸福に満ち足りているような思いを、逆に敗れたときには世界が明日にでも9終わってしまいそうな悲しい思いをする人々。こういう彼ら彼女らにとっては、すでにフットボールクラブはその人生を左右するという意味において「クラブ以上の存在」なのである。
さて、ここで札幌は「クラブ以上の存在」たり得ているのか、という疑問が生じる。 バルセロナのような「一般クラブを超えた、社会的な存在」はもとより無理であるのは明白だし、そんなことをするならまずチームとしての人気と、新しいファン層の獲得を行うことが急務であるのは誰の目から見ても明らかだ。介護や食育事業にも力を入れる、ということだけどそれは「社会貢献」のうちの一事業に過ぎない(介護・食育事業への展開を批判しているわけではない。逆にうまく軌道に乗せてほしいと思っている)。 それならば目指す先ははっきりしてくる。J1への昇格と、「魂に訴えかけるフットボール」である。J1に昇格しなければファン層は拡大しない。そしてファン層が拡大できたとはいいえ、そのファンに訴えかけるようなフットボール――僕らの人生に劇的なとまではいかないまでも、ささやかにでもいいから彼らの人生における幸せと落胆、そして「気持ち」をもたらしてくれるものであるだろうか。僕の現段階での回答は「否」である。 前シーズンの柳下監督時代は、明確な意志を持ってはいたがそれが選手個々にまで行き渡っていたかというと疑問が残るし、「ともに喜ぶ」ではなく「ともに苦しむ」ことの方が多かったのではないだろうか。三浦監督が指揮を執ることが決まってから、僕は「ともに戦う」「ともに喜ぶ」チームであってほしい、と思っている。4バックとか、カウンターとか、戦術以前の話ではない。どれだけ一体となって戦えるのか、大きく言ってしまうのならばファンがそこに「生きる意味」を見いだすようなサッカーをしてくれるのか、そのことだけが気がかりだ。 少し、自分自身の話をしたい。 昨年父と会ったときに話していたところ「まだコンサドーレは応援しているのか?」と唐突に聴かれた。嘘をつく必要もないと感じたので、以前と変わらず通っていることを父に話すと父は突然に渋い顔になった。つまりはこうだ――もういい大人なのだから、ゴール裏で飛び跳ねるような酔狂に関わっている場合ではない。コンサドーレからは手を引いて、まっとうな社会人として生きてゆけ――、と。父の話を聞き流すふりをしながら、僕はテーブルの下で煮えたぎる怒りを押し殺していた。大学に合格して、どこにどうやって行けばいいのかもわからなかった97年の春、それでも笠松へJFL開幕戦を見に行ったのは、その当時、札幌のフットボールを見ることが、僕の人生にとって必要だったからだ。札幌のフットボールを見るために遠征して、はじめての土地で友人と出会い、ともに応援し、喜びも苦痛も分かち合い、ともに進める仲間ができたことを父親は「ガラの悪い奴らとつきあっている」としか見ていなかったのだ。軽く、いや、かなり、ショックだった。勉強も大事だけど、時にはそれよりも大事なものを探して、そのために生きていくことが大事なのだということを父親が考えていなかった、勉強してどこかの堅い職業に就いてほしいのだというのが父の本音だったようだ。でもそれを僕は裏切った。父の思いがわかっているのにも関わらず、裏切った。アウェーに行きまくり、最前列でリードをとった。 なぜならその当時の僕にとって、そして今の僕にとっても、札幌のフットボールは何よりも大切なものなのだったのだ。札幌のゴールは僕の生きる源だった。札幌の敗戦は僕の勝ちを全否定するほどのどん底をもたらした。そうして、僕にとっての札幌はすでに「Mes que un club」であったのだ。手に抱えきれないほどの愛とプライドを持って、僕はゴール裏へ足を運び続けた。 でもいま、それだけの情熱を、どれだけの人が持ち得ているだろうか(自分も含めて)? 情熱は伝えるもの。喜びは分かち合うもの。誰彼問わず、スタジアムにいる全員で分かち合うものだ。そうして僕らは札幌が「Mes que un club」であり続けるように、精一杯の声援を今年も送る。人生の喜びを、人生以上の価値をこのクラブに――と、心の中で思いながら。
ジャンルカ・トト・富樫、急逝
2006年02月08日
なんで今、なのだろう。
フットボールに魅せられた彼の命が、
ワールドカップのこの年に散ってしまったというのが、
もしフットボールの神様の仕業なのだとしたら、
それはあまりにも、あまりにも、残酷すぎやしないだろうか。
フリージャーナリスト・石川保昌氏のブログにもこのエントリがある。
>後輩諸君に言っておく。
>サッカーの暦は4年ごと、2年ごとに進んでいく。
>いまの君の仕事に甘んじるな。君がもし30だとしたら、
>あと何回、W杯に立ち会えるかい。
>そんなに多くはないぜ。
>98年のときより2002年、2002年のときより2006年、2006年の
>ときより2010年と、明確に自分がやりたいこと、やらないと
>いけないことを見据えてほしい。
>自分に足りないものはなにか。どうすればそれは補いがつくのか。
>自分はそのために自己啓発してきたか。
>時間はあるようでそんなにない。
富樫氏や石川氏のようなライターの人だけにこの言葉は当てはまらない。
ひとりの人生に残された時間は思ってみればあまりにも短いし、
歳を取るごとに時間の過ぎる速度は加速度をつけて速まっていくばかりだ。
だから、自分はもうちょっと行き急いでもいいと思う。
富樫氏のご冥福を、心よりお祈り致します。
アンチ・クライマックス。
2006年01月29日
JSPORTSで放送されている「フットボール・アンチ・クライマックス」という番組がある。内容をかいつまんで言うのなら、Jリーグの一試合を90分という限られた時間の中ではなく、トレーニング、ゲーム前、ゲーム後の表情から丹念に追いかけ、選手やコーチのコメントを引き出しながらその試合を再構築する番組、というところだろうか。月に一度の間隔で、一試合をピックアップして構成している。(ちなみに札幌は02年厚別での対FC東京戦を第2回に放送されている)
今回の放送(第41回)は、今までの監督の言葉を集めた「監督の言葉」。そのなかで横浜FC監督(当時)の信藤健仁氏が語っていた言葉。
「必要以上のリスクマネジメントは怯えだ」
前後の文脈を補完すると、たとえば相手が一人しか上がってきてないのに、味方の選手はいつも3人守りに行っているような戦術の型にはまった守り方しかできていない。リスクマネジメントは必要だが、フットボールはリスクを背負ってゴールを決めなければ勝てない。ときにはリスクを冒して点を取りに行くことが必要だし、必要以上のリスクマネジメントをするのは点を取りに行くという意識が低いということ≒「怯えの意識」の表れだ、ということ。
フットボールはゴールがなければ成り立たないスポーツだ。ゴールを決めなければ勝利のないスポーツだ。ゆえに、守備の場面であっても意識をゴールに向けていなければならない。ゴールのために相手のボールを奪う、そのためにマークにつく、プレスをかける、ポジショニングを保つ。すべてはゴールに向かっているべきプレー・・・ということができるのだが、すべからくリスクを冒してチャンスをものにするプレーが見られるというわけではない。札幌の例でいうと去年の最終戦、西谷選手がチャンスに横パスを選択して怒った柳下監督に交代させられたというシーンがあったのだけれど、柳下監督はまさにこのとき、「リスクを冒さないプレー」に怒りをあらわにしたのではないだろうか。先述した論に倣うのなら、西谷選手はゴールのために「パス」という確実性の高い選択をしたけれども柳下監督はそこで「シュート」というリスクを冒してほしかった、と言い換えられる。ゴールに一番近いプレー。それを求めるのがサッカーだし、そのために戦術や戦略がある。
ちなみに、横浜マリノス監督の岡田武史氏も「腰の引けたサッカーだけはしたくない」というコメントをしている。信藤氏の言葉をメンタルなニュアンスを交えて翻訳すれば、こういう言葉になるだろう。もっとニュアンスで読み替えてしまえば、元・FC東京監督の原博美氏が言う「シンプルに入れちゃえば1番いい」になるのかなと思うけど、さすがにこれは意訳しすぎか。
そして今、札幌に足りないものも「リスクマネジメントの意識」ではないかと思う。「必要以上にリスクマネジメントの意識を持ちすぎている」ところがあるんじゃないだろうかと。それは運動量とか、戦術ということではない。もっと深い、根っこのところにある、「ゴールへの意識」や「勝利への執着心」に繋がる意識だ。メンタルマネジメント、と広義に表現してもいいかもしれない。真の意味での「戦う集団」としてシーズンを戦い抜くために、キャンプで「ゴールへの意識」を十分高めてきてほしい。
プロフィール
生まれ:1978年旭川市生まれ。 育ち:道内あちこち。その後横浜、川崎を経て再び札幌。 観戦暦:1996年・対日本電装戦が初応援。翌年より道外への進学に伴いアウェー中心に応援、1998年よりアウェイコールリーダーとなる。2003年春に札幌へUターンし、現在ホームゴール裏で応援中。 サッカー以外の趣味:音楽と活字。
最新のエントリー
コメント
検索