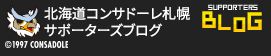なぜ札幌を愛してしまったのか――魂の故郷、という話
2007年05月27日
笹さんのところで始まったこの話。 理由を話そうとすればするほど、やっぱり自分語りになっちゃうなあ。 再びの自分語りになりますが、どうかご容赦を――。 なぜ札幌を愛するようになったのか、ということにもっとも深く関わっているのは「自分の生い立ち」じゃないだろうかと思う。 このブログのプロフィールにも書いているけど、僕は北海道の各地を転々と引っ越してきた。営業マンだった父は地方営業所のてこ入れを任されるようなポジションにいたため、最初は小さな街から僕と僕の家族の生活が始まった。2歳までは浜頓別、5歳の途中までは旭川、11歳の秋までは中標津、中学は室蘭、高校は札幌……というように、道南と十勝以外のところを時計回りに回ってきた。ちなみに今の実家(つまり帰省先)というのは旭川の隣にある東神楽町で、僕は高校の後に横浜、川崎、再び札幌と流浪している。この「流浪」が、むしろ僕が札幌を愛することになるきっかけになっている。
こんな風に自分の生まれ育ちの話を他人にすると、「じゃあ、札幌っていうより北海道全部が好きなんじゃないの?」とよく言われる。だけど本当はその逆。あちこち引っ越しすぎたがためにいろんな土地にいろんな思いがあってまとめきれないし、北海道がホームだという考えを持つには思いが散らばりすぎていた。 それに中学生くらいまでの時期なんて、自分の行動や意識が及ぶ範囲というのは自分の住む街と隣町、そして一番大きな都市のことくらいだろう。生活している範囲のことと学校のこと、塾のこと、部活のこと、友人や(ちょっとだけ)女の子のことなどなど、あまりにも濃密な時間が流れる思春期にはそれくらいしか自分の意識は及ばないし、その範囲をぐるぐる回る、あるいは振り回されることだけで精一杯だ。 だからそのころの僕にとって、「ホーム」という意識を持つには北海道はあまりにも大きすぎて、そして僕はあまりにも幼すぎた。 ちなみに盆と正月の帰省は父母の実家がある旭川だったんだけど、定期的とはいえ遠いところから片道4時間も5時間もかけて年に2回帰るだけの場所は見慣れた風景であれ、そこは「ホーム」ではなかった。だから僕は生い立ちをこう話す。「浜頓別生まれ、旭川と中標津と室蘭育ち、札幌在住」と。 札幌に引っ越してきてコンサドーレに出会っても、サポーターになりたての頃は「ホーム」という意識を持つことができなかった。大好きな「チーム」ではあったけど、そのときは目の前の試合を応援することに夢中でそんなこと考えもしなかったし、考える余裕もなかった。そういうことを意識するようになったのはむしろ北海道を出てからのことだ。北海道を出て、見知らぬ街で暮らし、不安だった頃に僕はけっこう大がかりな決意をして笠松へ開幕戦を見に行った。分厚い時刻表を買い、サッカー雑誌の隅にある競技場までのアクセスを調べ、最寄り駅から歩くことにして競技場まで約3キロの道のりを歩いた。競技場に着いても初めてのアウェイに単身乗り込んできたわけなんだから、知った顔の人なんていない。けれどもその知らない人たち同士で固まり、「サッポロ!サッポロ!サッポロ!」とコールを発した瞬間に「俺は地元のチームを応援している、故郷のチームを応援している」という実感がわいてきた。遠く離れて北海道の土地の名を呼ぶ、そのことに感動して体を電流が駆けめぐった。そして、僕はアウェイゲームをメインの活動場所にするサポーターになった。 それから試合を応援するたびに、声を出すたびに、僕は「ホーム」への意識を募らせていった。場所が遠ければ遠いだけ、チームを愛する気持ちは強くなっていった。そうして夏休みになって帰省がてら厚別のゴール裏に行ったとき、僕は今立っているこここそが「札幌」という土地であることを深く意識した。そうして札幌というチームを応援できる喜びを改めて心の中でかみしめた。まさに「遠くにありて」初めてわかったというわけだ。 その後もアウェイに遠征していても年に一度か二度、厚別に帰ってくるたびにこのチームとともに戦うことができることを誇りに思った。と同時に、このチームは北海道を象徴しているチームなんだ、という自覚も目覚めてきた。チームの名前こそ「札幌」だけど、毎週北海道の遠くにいても応援しに厚別へ通ってくる人がいる。北海道にある唯一のプロフットボールチームだということを。そのことを知り、このチームは「北海道」の誇りを持って戦っているんだ、という思いや意識が強くなっていった。 一方、別の思いは僕の中で未だ解決されずにいた。 引っ越しを繰り返してきたせいで、ほんとうの「故郷」と呼べるような土地は存在しなかった。帰省する旭川であっても、そこは「祖父母の住む街」という存在でしかなかったし、近い将来札幌に住んでいる家族は父の定年退職に伴って東神楽へ移住することも決まっていた。つまり、故郷がまた別の街になることが決まっていた。 肉体的な故郷は東神楽になったとしても、僕に取ってはその土地は「新しい引っ越し先」でしかなかった。精神的な「故郷」はどこにあるんだろう、と思った。僕にとって不変の、本当の故郷はどこなんだろう、と思っていた。 だから、故郷に強い思い入れと誇りを持つ人たちを見て、うらやましかった。 そんな中で帰省してきた夏休みの日、僕は厚別で気づいた。 厚別(や福住や室蘭入江や宮の沢)は、変わることのない札幌のホーム。 遠いところから帰ってきても、ゴール裏があることは変わらない。札幌を応援する場所は変わらない。そのことを理解したとき。 ここが故郷なんだ。ゴール裏が、僕の故郷だ。 出生地や、住んだ土地のことを考えると故郷は「北海道」という意識をもてるものの、いつでも帰りを待っていてくれて、いつでも温かく迎えてくれる場所はどこだろうとずっと考えてきた。地縁や血縁ではない、僕が最も誇りを持っていられる場所。そんな「魂の故郷」を探していた。そしてそれは、ゴール裏にあった。 「僕の魂の故郷は、厚別のゴール裏だ」 「僕の魂の故郷は、アウェイでも札幌を応援するサポーターとともに戦う場所だ」 僕の頭の中でふわふわと浮いていた「故郷」という最後の1ピースが、北海道の形をしたジグソーパズルにぴったりとはまる。 僕は故郷を見つけた。絶対に揺るがない、熱く温かい故郷。 自分にとって北海道のすべてを代表する場所。誇りを持てる場所。それが故郷。それがゴール裏。 そう思った瞬間、堰を切ったようにあふれ出てきた熱い思いがあった。 こんなに俺は札幌のことを愛している、この故郷をこんなにも愛している。 誰にも言えなかった「愛している」っていう言葉を、故郷には真顔で言えた。 もしも僕が死んだときには、遺骨を粉にして厚別と宮の沢に撒いて欲しい。それができなければ宮の沢の土の片隅にでも、僕の骨片を入れた小さなカプセルを埋めておいて欲しい。墓なんかいらない。そんなことを本気で思った。 やっと、やっと見つけた――。 その後、夏休みの帰省が終わって横浜へ帰っても、アウェイの応援でどんな土地のゴール裏に行っても、そこが僕の「故郷」になった。 あのときに厚別で、僕の魂の故郷が見つかったから、それを教えてくれたから、僕は札幌を愛している。札幌というチームを、心の底から愛している。 これが、僕が札幌を愛している理由。
人生に必要なことはだいたいゴール裏の芝生で学んだ
2007年05月24日
文化系トークラジオ「Life」 「おまえ、本当にいいのか?」 と担任教師がちょっと怖い目つきで確認してきたけど、僕は無言で頷いた。こんなことなんてめったにないことだろうけど、僕はそれで良かったのだ。 センター試験が終わって一息ついた頃だったと思う。その冬の日に僕が断ったのは、卒業間近のお約束こと卒業アルバムの購入申し込みだった。卒業アルバムを断るやつなんて滅多にいないだろう。現に僕の所属していたクラスでは僕以外いなかった。350人以上いたであろう3年生全体でも僕以外の誰かが買わなかったかも知れないが、それは正確にはわからない。
ともあれ、なぜ僕が断ったか。 結局はクラスに思い入れがなかった、と言ってしまえばそれだけだった。 そもそも高校に入学した時からクラスにはなじめない毎日だった。もっとも、中学卒業のタイミングで室蘭から札幌に引っ越してきたので中学時代の見知った友人がいないというハンデはあったのだが、「友達なんていなくてもいい、ひとりでも生きていける」という間違った諦念を抱えていたので、それを自分から曲げてしまうのは当時の僕にとっては受け入れがたいことだった。要はガンコでひねくれていたのだ。 そんなガンコな性格をしている以上、高校での学校社会では友達と呼べる人間も想い出も少なかった。女子を誘ってお花見に行くだとか、クラスみんなでジンギスカンパーティーをしようだとか、ほいほいとイベントを企画したり実行したりしているフットワークの軽いクラスメイトにはついて行けなかった。本能的に「ああ、こいつらとはウマが合わないんだろうな」という予感はしていたけど、それは予感以上の孤立となって学校生活に襲いかかってきた。今これを書いていてどんどんと黒歴史が頭の中で渦を巻き始めているんだけど、それはこのエントリの主旨とはかなり縁遠くなってしまうので割愛。 高校時代だけにあらず、僕は中学時代(このときは卒業アルバムは買った。念のため)から友達は少なかったし、もっと言えば幼い頃から「ひとりでいるのが好き」だった。部活(剣道部)には所属していたもののけっこうのんべんだらりとした毎日だったし、部活でもしゃべる人いないし、同じ部活に所属していた弟の方が強かったし。そんな感じで、僕はそのころからひとりで楽しめるモノ、詳しく言えば音楽(テクノ)と本と深夜ラジオにのめりこむ生活だった。 それでも中学時代には救いがあって、週に3回バスで30分かけて通う進学塾は面白かった。授業自体もクラスに集まる人間も刺激的だったし、なによりそこでは「進学校に合格する」という目標を共有できたから、というのもある。でもそうした縁は僕が引っ越したことで切れてしまい、自主的に友人関係を築くことにはいささか億劫で面倒な気持ちになってしまった。もういいやと諦めていたその矢先、クラスメイトの付き添いで入部した弓道部があまりにもしっくりきたので驚いた。どうにも一癖ある先輩と同級生が(特に男子に)多く、そのいびつっぷりがうまく自分のいびつさと馴染んでしまった。そんなわけで放課後は延々と部室に居座り続けることになり、ダラダラと雑談しながら夜遅くまで(そして練習はろくにしないで)過ごしたことを憶えている。弓道部の部室は独立して建っていたので(矢が飛んで危ないから)居心地もよかったし、格好のサボりスポットでもあった。ヒマでヒマでしょうがない学校祭のときに、サボりに行った別の場所でほかの部員とばったり、なんてこともあった。 高校を卒業して10年以上も経った今、同じクラスだった人とはほとんど交流はしていない。だけど、部活の同期や後輩とは卒業後もずっとつながりがあって(盆暮れに飲みに行くとか)、mixiでコミュニティまで作っている。それだけ「濃い」そして「安心できる」場所だったのだ。そういえば一つ上の先輩が卒業したとき、部室にあった日誌に「私にとって部活は精神安定剤のようなものだった」と書いていて、それに僕はどうしようもできないくらい共感した。永遠であるかのように繰り返される学校生活は退屈で、部室が唯一の場所だった。クラスの中では陸にあがった魚のように苦しかったけど、部室では柔らかな光のさす水族館で泳ぐように過ごすこともできた。 でも、結局部活という居場所であってもそれは「学校」というくくりの中でしかないわけで、部室も所詮は大海ではなく、水族館の水槽もしくは養殖用のいけすなんじゃないか、ということを部活を引退する間際に思ってしまった。そう思ってしまったが最後、僕は部室にいることにさえ閉塞感を憶えていた。僕が僕であっても誰にも文句をいわれない場所、もっと広くて夢中になれる場所、そういうのを探していた。そうして出会ったのが、厚別競技場のゴール裏だった。 初めて行った厚別のゴール裏はまだ芝生で、サポーターの数だってずっと少なかった頃の話だ。まだ一条館の端にあった丸井のオフィシャルショップでTシャツを買って、それを着て出かけた。ゴール裏の真ん中にはいるのは正直言って勇気がいった。TVでJリーグの中継を見るたびに絶え間なく聞こえる大音量の歌とコールの嵐を見るにつけ、「ゴール裏は体育会系の人ばかりで恐い場所」だとずっと一方的に思いこんでいたフシがあったので、タスキを出して陣取っている一団に入るのをちょっと躊躇った。ちょっと離れたところでお弁当と敷物を広げている家族連れとは空気の断層が、流れる空気の濃さが見えるようで「自分なんかが入っていいのだろうか」と一瞬思ったけれど、その時はなぜだか座ってのんびり見ていようとは思わなかった。ただとにかく、チームのために応援をしたかった。 初めて声を出したときのことを憶えている。翌日には声がカスカスになってしまっていたのも憶えている。膝で泥臭く押し込んだ川合のVゴールも憶えている。でもいちばん憶えているのはもっと前に出て応援したいと思ったことで、「柵に登ってみなよ」とある人に背中を押された勢いで柵に登って必死に声を出し続けていたことだ。ただただチームに勝って欲しくて声を枯らしたことだ。Vゴールの瞬間、歓喜が炸裂して僕の体のなかを爆風のように通り過ぎて行って、あらゆる負の感情を薙ぎ倒していったことだ。そして厚別のゴール裏から初めて見上げた空はも、あらゆるものを薙ぎ倒したように青い空をしていた。学校の外にはこんな世界があっただなんて、17歳の僕は思っても見なかった。 その後続けて厚別のゴール裏に行くようになり、レプリカも買い(半袖は売り切れていたが、そのときどうしても手に入れたくて長袖を買った)、そうして周囲の幾人かと知り合いになることができた。最初に仲良くしてくれたのは「柵に登っちゃえよ」と僕を煽った人で、10歳近く年が離れていたけど自然と溶け込むことができた。ゴール裏で知り合う人たちはまず僕より年上だったけどこれ以上ないくらいにすんなりと馴染むことができた。そのあとゴール裏での友人も増えていき、それは横浜の大学に進学したことでアウェイのサポーターとなった後でも全く同じだった。笠松からの帰りの電車でさっき知り合ったばかりの人と話し込み、愛鷹でスタメンとベンチメンバーを合わせたよりも少ないサポーターで応援したり、刈谷で突然タイコを持って応援に混ざってきた人に駅まで送ってもらったり、話したり、遊んだり、言い争いになったり、一緒に他のチームを見に行ったり。そうやって遠征と応援を繰り返していると、相手チームのサポーターとも仲良くなったりすることもあった。ゴール裏は体育会系なんかではなくファナティックと呼ぶにふさわしい雰囲気ではあったがその裏にあるものは体育会系のノリではなく、むしろ文化系の思考。サッカーから派生した、もしくは想起される音楽や文学、理論、それ以外のマニアックな話のほうが多かった。応援を通じてカルチャーを理解する、そういうことが多々あった。 そういうわけで僕の「友達」は常にどこかのスタジアムのゴール裏にいて、そして人生で必要なたいていのことはゴール裏で学んだ。同い年の人にはまず出会わなくて、みんな年上だったからなおさらだったのかもしれない。そこでは面倒くさいと思うようなしきたりもあったけれどそれ以上に僕が得るものは大きかったし、学校や職場という「閉じた」空間では決して出会うことのない友達と、濃密な空気の流れる時間を共有することができた。そして、今でも友達でいてくれている人たちの多くは、いつかのあの日、どこかのスタジアムで、一緒に応援していた人たちだ。そして、今でも交流を持ってくれている友達に感謝している。離れていった人たちも、僕になにがしかの教訓と示唆を与えてくれた。 そう考えてみると、友達っていうのは「閉じて」いたらできないものなんだ、と思う。学校や会社といった「閉じた」世界にいてただ孤立しているより、ほんのちょっとだけでいいから「開いて」みれば、窓から新鮮な空気が流れ込んでくるように人生が濃密になり、そして広がっていくのではないだろうか。だから「友達」というのは自分で作るものでもあり、自分が広げた向こうにある「場所」が作るものでもある。閉じたままでいても閉じた中での友人関係というのはあるだろうが、開けた先の「場所」で出会う友達は誰よりも大事な人になる、そんな可能性が広がっている。だから今「閉じて」しまっている人は針先くらいの大きさでいい、それくらいの穴でいいから、今閉じこもっている場所のどこかに穴を「開けて」みよう。下に穴を開けたならば土の匂いが、上に開けたなら小さく青く光る青空の一片が、横に開けたなら、これからたぶん友達になるであろう誰かの姿が見えるはずだ。そのただひとつ開けた先が、僕にとっては「ゴール裏」だった、ということなのだ。そこから僕がどのように開いていって、どのように「友達」ができたのか、というのは前述の通り。だから後は自分に必要なのは「穴を開けるささやかな勇気」そして「自分の世界を開く勇気」。自分のいちばんの拠り所がネットであっても、閉鎖的な学校社会であっても、「行動」を起こすこと。ネットで騒ぐだけじゃなく、オフをやってみるのもいい。僕がゴール裏に行ったようにリアルの世界で自分から出向いていって言葉を交わすのだってかまわない。自分が動かなければ、新たな「場所」は生まれることはないのだから。そういった、多少なりとも「外へ出てみる」「外を見てみる」ことがないと、そうして人と人とがリアルに存在していることをその眼で確認しないと、対話をしてみないと、本当の意味での「友達」というのはできる可能性が低くなるんじゃないか、と思う。 だから今、「閉じている」ひとへ。 ほんのちょっとだけ「開いて」みよう。少しの勇気でいいから。 もし君にもっと勇気があるのなら、その「開いた」先へ思い切って飛び込んでいこう。 きっと、その向こう側には、自分が自分で居られることをもっと満喫できて、そこには新たな友達が待っているはずなのだから。 今回のエントリは、「文化系トークラジオ Life」で4月22日に放送されたテーマ「友達」に触発されて書いたものです。 最新回のテーマは「文化系と貧乏」。これも思うところがいろいろがあるので、しばらく経ってから書いてみようと思います。 その前に、なぜ「ゴール裏は文化系なのか?」ということも自分なりに説明をしておかなければならないな、とも。
プロフィール
生まれ:1978年旭川市生まれ。 育ち:道内あちこち。その後横浜、川崎を経て再び札幌。 観戦暦:1996年・対日本電装戦が初応援。翌年より道外への進学に伴いアウェー中心に応援、1998年よりアウェイコールリーダーとなる。2003年春に札幌へUターンし、現在ホームゴール裏で応援中。 サッカー以外の趣味:音楽と活字。
最新のエントリー
コメント
検索