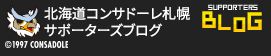僕らは失う機会すら与えられなかった-(その2)
2007年02月22日
昨日の話の続き。なんだか朝日批判チックになってきていて本筋とは逸れてしまいそうな勢いですが。 昨日の話では自分もそのど真ん中に所属しているとされる「失われた世代」のことを朝日新聞が特集して点で、「誰が」「どのように」「何を」失ったのかという焦点がぼやけたまま、間違った方向で印象を与えてしまっているということを書いた。 で、この特集にはもうひとつ欠けている点がある。それは「格差社会」という観点だ。 格差があるのはどの国も街も一緒だ。だけどその格差があまりにも広がりすぎていて、富がごくわずかの層に大きく集中しすぎているのが今の日本。だってそうでしょう?企業は大きくその利益を伸ばしているけど、一般社員ですらその恩恵にはあずかれない。企業側が「バブルとその崩壊の時代」の経験をトラウマにしているせいなのか分からないけど、富の再分配は行われていない。そういう全社会的な「格差」を含んで考えなければ、「失われた世代」へのアプローチはうまくいかないのではないか。
そんな風に考えているときに、2月18日の社説にこういう記事が載っていた。 '「格差是正 失われた世代に支援を」 (前略) 格差そのものは、どの時代にもある。努力を怠った結果であるなら、自己責任を問われても仕方がない。そのうえで生活保護など最後の安全網を整えるのが政府の仕事となる。 では、政治が最優先で取り組むべき格差問題は何か。正社員と非正規の働き手との間に横たわる賃金や契約期間など処遇での差別こそが焦点だ。正社員なら若い時期から会社の負担で能力を高められる。得意技や専門知識が身につけば、転職しての再チャレンジも難しくない。一方の非正規雇用は最初から不利な立場に置かれる。 私たちの社会には、こうしたハンディを理不尽な形で負わされた仲間がいる。就職氷河期といわれた90年代に就職活動をした25歳から35歳ぐらいの層だ。「ロストジェネレーション(失われた世代)」ともいわれる。 バブル崩壊による不況のなか、企業はリストラを急いだ。過剰な設備や借り入れだけでなく、社員の採用も削り込んだ。本来なら若手社員に任す仕事を派遣や業務請負などが埋めた。身軽になり、競争力を取り戻した企業は、いま高収益を享受している。だが、就職にあぶれた人々は取り残された。 経済協力開発機構(OECD)の対日審査報告書は「格差拡大の主な要因は労働市場における二極化の拡大にある」とし、その固定化に強い懸念を表明した。問題は本人だけにとどまらない。消費の落ち込みや、社会保障の担い手の不足、中堅や熟練労働者の減少など、社会に様々なひずみを生む。 神戸の大手アパレル、ワールドはパート約6千人のうち5千人ほどを正社員に登用した。年22億円のコスト増だが、「一生の仕事として取り組む人材を確保する」という将来をにらんだ戦略だ。 こうした企業を増やし、低賃金の非正規雇用にあぐらをかく経営者に転換を迫ることで、失われた世代を支える仕組みを社会全体で考えたい。(後略)' 果たして、この社会は個人が生み出してしまったものなのだろうか?「バブル以後の不況に耐えきれなかった世代」が生んでしまった鬼子なのだろうか?この文章を読む限り、すべてとは言わないけれど責任の多くは個人にある、とでも言いたげだ。そして「私たちの社会には、こうしたハンディを理不尽な形で負わされた仲間がいる」と呼びかける文章へと繋いでいる。 仲間? 俺たちはいつから朝日新聞の仲間になったんだ?誰があんたたちの仲間にして欲しいと頼んだ?そもそもフリーター世代にとって「仲間」っていう言葉は、自分たちにとっては嫌いな方に入っている言葉だだろう。新聞で呼びかけられる薄っぺらい「仲間」という名前の御都合主義な連帯よりも、あんたらが薄っぺらだと決めつけている自分探しで見つけた「仲間」の方がよっぽど大事だ。それを自分から大声で叫ばなければ、本当の意味での「格差是正」にはならない。 自分は「失われた世代」の一員として、何を失ってきたか、そしてこれから何を手に入れられるのかを考えたい。未来は無限ではない。無限とはほど遠い、数えるくらいの「有限」の中から考え抜いて選んで、それをメシの種にして乗り切っていくしかない。それが今の時代の現実。そうやって思っていくと、自分が失ったのは「未来」という名の希望であり、選択肢であり、場所である。所得階層を自分の力で勝ち取る自由すらも失ったと言っても過言ではないと思っている。そして失ったのは、自らの過失ではない。もっと言うなら、自分は「失う」ということの社会的体験、失うことの悲しみや挫折感や悔しさすらも感じることさえ奪われてしまったのではないか。学生時代には失ったものはある。それは人間関係であり、志望校への入学だったり。だけど社会に出て仕事に就くようになったとき、すでに失うべきであったものは失われ尽くされていた。これ以上失うことを会社は許さず、わずかに採用された新人には荷が重い仕事だったような気がする。たぶんそんな一時期を乗り切る力があったとしたら、今頃はかなり会社人間(いい意味で)として成長できていたんじゃないかと思うこともあるけど、それはもうどうしようもない話。気がついたときには「失うこと」すらすでに失っていた「失われた世代」は、このままよくてワーキングプア、ともすればホームレス寸前のワンコールワーカーみたいになってしまうのだろうか。これ以上失うものがない自分から、社会は何を奪おうとするんだろう? どこにも答えを見いだせなくて暗闇を這いずり回る感覚の下に、この項、了。 ※参考資料 朝日新聞2/18付社説「格差是正 失われた世代に支援を」 官邸による「成長力底上げ戦略」(PDF) 官邸による「成長力底上げ戦略」の主な論点(PDF)
僕らは失う機会すら与えられなかった-(その1)
2007年02月21日
ちょっと昔の話になるけど、朝日新聞が元旦から「ロスト・ジェネレーション」という特集を組んでいて、その新聞記事があまりにもお粗末で矮小化されたものだったので社会学系ブログなんかで思いっきり炎上して、それから「ロスト・ジェネレーションってなんなんだ?」という話題が出てきたことがあった。その話題は今となってはすっかり鎮火しているに等しいのだけど、ここでちょっとぶり返してみたい。個人的にまとめたい(でもって憤りたい)だけなんだけど。 そもそも、「ロスト・ジェネレーション」という言葉は何を意味しているのかというところからはじめたい。この言葉が出てきたのはヘミングウェイやフィッツジェラルドといった小説家の生まれた世代、1920年代から30年代という二つの世界大戦のちょうど「戦争の風穴」のような時期に青年時代を過ごし、その後の第二次大戦のにより文化的、情緒的に異質なものをもたらした人々を指す言葉だ(かなり要約)。 それをふまえた上でまず朝日新聞の第1回のリード文を読んでみると、そもそも定義からしてかなりいびつにされている。 今、25歳から35歳にあたる約2千万人は、日本がもっとも豊かな時代に生まれた。そして社会に出た時、戦後最長の経済停滞期だった。「第2の敗戦」と呼ばれたバブル崩壊を少年期に迎え、「失われた10年」に大人になった若者たち。「ロスト・ジェネレーション」。第1次大戦後に青年期を迎え、既存の価値観を拒否した世代の呼び名に倣って、彼らをこう呼びたい。(1月1日)
呼ばれたくもねぇよと毒づいてからちょっと膝詰めで小一時間問い詰めたい感じがするのだが、そこはぐっとこらえて。 今25歳から35歳に当たるということはだいたい1970~80年くらいに生まれた人々のことなんだけど、確かにその時代というのはバブル崩壊前後に就職を迎えた世代である。バブル期には大幅な売り手市場であった企業の正社員枠は0に近くなり、派遣社員や契約社員、アルバイトといった非正規雇用に就くか悪質商法、ニートにならざるを得ない人々が続出していた時代でもある。また、学校を卒業しても就職できるアテもないし技能もない、ということで専門学校への入学者が激増した時代でもある。 では、その時代のあと、彼ら(彼女ら)はどうなったのか?正規社員として、正規な労働契約の下に、完全とはいえないまでもそこそこ満たされた労働環境の中で働けているのか? 答えは否である。完全に。 非常に残念なことに、この国の社会構造は正社員になれなかったフリーターやニートを救済する構造は持ち合わせていない。フリーターはフリーターのまま、悲惨な生活状況のまま死ななければならないのがこの国だ。そうした就職氷河期の時代を経ての現在、再び雇用状況は改善し、新卒求人も増えてはいるが中途採用などは今でも数は少なく、フリーターから正社員など望むべくもない。そういう労働的な観点から見たなかで、どん底に落とし込まれて、雇用主のいる層からは見ないフリをされているのがこの世代なのである。 ……というようなことを、いささかあるいはかなりの偏光メガネ具合で「下流」の人間ばかりをどうにも収まりの悪い形で特集したのがこの特集。 で、朝日新聞の記事のどこが問題なのかというと、こういった世代を例える表現である。「失われた世代」というのは、いったい「誰が」「何を」失った十年だったのか、ということが全く明示しないまま、ただもともとの「ロスト・ジェネレーション」を矮小な取材記事に貶めてしまったことだ。 自分は今年29歳。この「失われた世代」で定義するところのど真ん中の世代だ。その時代に生きている自分にとって、「誰が」というのは答えが出る。それは「私たち」以外の何者でもない。自分たちの前には高度成長期から途切れることなく続いてきた道があり、後の世代にはITを取り込んで復活した企業が道を作ろうとしていた。でもその合間の部分は断絶して、これからも独力で登り上がることなどできないただ落ちるだけの道がある。で、その断絶の崖の底でひとり上を見上げながら、思うのだ。「俺たちが何かを失ったように言ってるけど、本当は『社会が俺たちから何かを奪い取った』んだろ!」そう怒鳴ってみると、返ってきたのは抑揚のない役人声。「そんなこと今更言ったって、その昔、自分探しがしたいと後先考えずに飛び出していったのはキミたちじゃないか」「後先考えなかった訳じゃない!あの時の社会のことなんて、考えても意味がなかったに決まっているだろう!それでやっぱり頑張らなくちゃって思って帰ってきたら役立たず扱いで知らんぷりかよ!」 そして、同特集1月3日のリード文。 「失われた十年」の間に正社員としての道が閉ざされ、社会からはじき出されてしまった若者たちは今、どんな日々を送っているのか。ロスト・ジェネレーションが仕事、そして自分自身と向き合っている現場を、同世代の記者が訪ねた。 正社員でなければ人間ではないとでも言いたげな、この文。「社会からはじき出された」ときっちり文章にして、フリーターや契約社員は「余計者」であるかというようなこの文。コレが日本を代表にする大企業に勤める正社員こそ「人間」と、自らの立つ労働社会の構造問題とあやうさを慮ることもなく、労働的に下層に位置する人間を「自分探し」などと揶揄して、まるで根無し草のように扱っている。それにも我慢がならないのだ。「自分探し」という言葉に乗っかった人たちは、少なからず感じているのだ。いくら世界を巡って「自分探し」をしようが、自分にとって大切な者はその程度じゃ見つからない、ということを。そう考えることで、この特集で朝日新聞側がこの特集を組んだ意図というか、「失われた十年」をどう思っているのかがわかる。つまり、「失われた十年」とは「一定の世代に育って社会に出た人間がバブルの苦境に負けて自分探しに走り、結果フリーターやニートが増えた十年」と目線を下に置いた(もっと悪い言葉で言えば「嘗めた」)ところから「ほらほらこの人はこんなに下賤な生活なんですよ、気をつけましょうね」という意味でまとめたのがこの記事である。ふざけんな! で、コレに続く話をこないだ2月18日の社説で見つけたのが、その話は次エントリに。 ※参考資料 文化系トークラジオ Life:「失われた10年~Lost Generation?」 「Life」にサブパーソナリティとして出演されている仲俣暁生氏のブログより、今回の問題について言及されているエントリ。 「ロスト・ジェネレーション」について ふたたび「ロスト・ジェネレーション」について こちらで記事の抜粋と筆者コメントが読めます。 別所二郎のジタバタ漂流日記
恥を知れ!しかるのち死ね!――極私的書評『夜は短し歩けよ乙女』
2007年02月20日
森見登美彦『夜は短し歩けよ乙女』 本屋でその装丁に惹かれて買っていこうかなと思っていたらとんでもない人気らしくたちまち消えてしまっていて、重版になってやっと並べられた「夜は短し歩けよ乙女」をようやく買い求めることができた。 そんで一気に読み終わって一言目の感想。なんてキュート! 間違えば完璧にストーカーとして引っ立てられるであろう(いや、すでにそうかもしれない)主人公の「先輩」が、片思いの彼女の気を引くべく、なるべくできるだけ多く彼女の目にとまろうとすべく京都の町を駆け回る。夜の木屋町から先斗町で、夏の盛りの下鴨神社で開かれる古本市で、晩秋も深い学園祭の大学構内で、風邪の風吹く真冬の高野川で、北白川で、今出川通で、四条河原町で。主人公が追いかけるのは黒髪でひよこ豆のような後輩の彼女。けれども主人公とちょっと天然っぽい彼女はすれ違うばかりで……という、四季それぞれの京都を舞台とした連作小説。果たしてこの本をどのようにジャンル分けすべきか。作者がデビューしたジャンルであるファンタジーか。すれ違いの平行線を歩み続けるボーイミーツガールの恋愛小説か。どうにもこうにも分けられることができないが、なんとしても面白いことだけは確かである。
たとえば第四章「魔風邪恋風邪」で、主人公は彼女と自分のことをこう思う。 「冷たい雨の中を駆ける一匹の濡れ鼠がある。それはもちろん私のことだ。私は晴天の下へ出ようとしている。だが目前に見えているその晴天は、まるで夏の陽炎のごとく逃げ去り続ける。その陽光の中に立つのは、我が意中の黒髪の乙女だ。彼女のまわりは温かく、静謐であり、神様の好意に満ち足りて、たぶん良い匂いがする。それに引き替え、我が身はどうだ。私のまわりは神様の好意どころか若気の至りに充ち満ちて、この身を濡らすのはぶきっちょに奮闘する己を嘆く涙、吹きすさぶのは恋風の嵐である。」(P225) ああ、なんと報われそうもない片思い!なんと不器用な片思い! そんなトホホな「先輩」は彼女への思い焦がれて輾転反側、まずは恋愛的外堀を埋めるべく行動を開始するも思いっきり埋めすぎるか見当違いの墓穴を掘るばかり。その間違った方向に全力疾走する「先輩」の思いに彼女は微塵も気づくことなく「あら、奇遇ですねえ!」と受け流し、彼女は彼女で自分の思った道をずんずんと進んでいく。それを慌てて追いかける「先輩」の道すがら現れるのは、これまた奇妙なサブキャラクター。自称天狗の先輩「樋口」。奇妙奇天烈な高利貸し「李白」。主人公よろしく片思いの塊を間違った方向にフルスイングしている「パンツ総番長」。個性という枠にはとどまらないどころかはみ出して枠が見えなくなってしまうくらいのキャラクターだし、ストーリー展開もこれまた奇妙奇天烈きわまりない。 夜の先斗町で李白と彼女が借金をかけて「偽電気ブラン」なるものの飲み比べ対決をする表題作、古本市で自分だけの一冊を追い求めて主人公諸々が駆けずり回る「深海魚たち」、カオス極まる学園祭に忽然として登場する「韋駄天コタツ」とゲリラ演劇「偏屈王」に巻き込まれる(いや、進んで巻き込まれているような気がしないでもない)二人を描いた「御都合主義者かく語りき」、風邪のウイルス吹きすさぶ真冬の京都を彼女がお見舞いに渡り歩く「魔風邪恋風邪」。どれをとっても不思議な物語なのに、どれもがすとんとエンディングに落ちていくストーリーテリングはすばらしいものがある。 とりわけここで挙げたいのは、主人公「先輩」が彼女への恋の病に取り憑かれて思い煩う心理描写。四畳半の古びた下宿で答えのでない問いを延々と繰り返し、脳内会議を開催し、正攻法で歩めないばかりに外堀だけをやたらと埋めようとして、至る結論は 「恥を知れ!しかるのち死ね!」(P138) の境地。おそらく「好きだ」と言ったり言われたりしようものならメルトダウン必至の主人公がもたらす妄想と行動はどこまでも「非モテ男」のそれである。モテないことに忸怩たる思いを抱える男子が何とかして彼女を作りたい、好きな女の子に思いを伝えたい、と空回りしてオーバーヒートの末に「モテ男」への偏見と自己嫌悪にまみれて「非モテ」をよりいっそうこじらせる主人公。読めば読むだけ思い出す過去が恥ずかしく、照れくさく、馬鹿らしく、体くねらせて頭抱えてしまう男子が続出することだろう。そんな視点から本書を定義するのなら、「非モテ男子と不思議ちゃん女子のすれ違いエンタテインメント」って言う具合になるのだろうが、そんな定義などモロッコに吹きすさぶ砂塵のように無意味だ。それほどに面白い。 一歩進んで本書を手にとってはじめの数ページかを読んでしまえば、虜になること請け合いである。そして読み終わったときにはお願いせずにはいられない。 願わくば「先輩」と彼女の幸せが永く続きますように!なむなむ!
許される街、秋葉原。
2007年02月19日
ちょっと前から引きずっている、東京話のつづき。 「東京と言えばどこ?」という質問ほど、その時代の移り変わりを示すものはないんじゃないかと思う。その昔、東京が「東京」であることをはじめた頃の回答は「浅草十二階」だったろうし、「帝都」と呼ばれた時代もあったし、戦後のそれは「東京タワー」から「サンシャイン60」を経て「お台場」が代名詞となってきた。だが今同じ質問をしたときに、勢力を伸ばしつつあるように思える回答が「秋葉原」だ。かつて電気街として繁栄し、やがてマニア/オタク(マニアとオタクは別の意味です)の聖地となったこの土地は、昔自分たちが社会科の授業なんかで思っていた未来よりもちょっといびつでサイバーで、なんだか「萌え」という単語の乱立する明るいカオスの街、「アキバ」になった。
ちょっと前までは「秋葉原に行く」というのは勇気のいる時代で、行き先は隠して秋葉原駅で降りるような恥ずかしさがあった。今でもそんな恥ずかしさは場所によっては残っている/別の意味でもっと気恥ずかしくもなっているけど、以前よりはずっとオープンな街になったとは思う。少なくとも、パソコンのパーツをふらっと買いに行き、メイド喫茶の店先を冷やかす程度には。でも中央通りから奥へと進むたびにまだまだディープでカオスで、それが今でも人を引きつける力になっていると思う。 例えて上げれば汐留/お台場/六本木ヒルズ。今東京で話題性のあるスポットといえばこのあたりか。これらの街で、秋葉原と決定的に異なっている点がひとつ=「時代性が薄い」ということだ。都市再開発の流れで作られたこれらの土地は、まっさらなところに(六本木はそうでないかもしれないけど)突如として生えてくるビルと堰を切って進出するアミューズメントチェーン、ITとメディア企業がこぞって進出する街になった。まるで巨大な箱庭を突然、どんと目の前に置かれたような光景が広がっている。そこに通り一辺倒の「面白さ」や「目新しさ」はあっても、2回3回と通ううちに新たな発見などは無くなっていく。そのうち興味もなくなってきたころに、新たな箱庭がどこかにできて今度はそこに人々が押し寄せて……という図式が、ここ十数年で繰り返されているように思える。今や東京の真ん中はハメコミ合成の箱庭だらけでスカスカになってきているような気さえする。都市としての歴史的地理的な厚みや、奥へ奥へと入り込める面白さを求めるのなら新宿か秋葉原か。あるいは下北沢くらいしかないんじゃないのかなあ。 自分が秋葉原に行ったときは、一番華やかな中央通りから順番に、S字を逆からたどるように奥へと歩くのが通常ルートだった。まず中央通りを秋葉原駅から地下鉄末広町の方向にずっと歩く。大通りは、まずはその街のリアルタイムな流行を知るのにちょうどいい。大型電器量販店の店頭や、ゲーム専門店なんかをのぞき見しながら流して歩く。末広町近くでいったんその町並みはとぎれるので、そこで折り返して反対側の歩道をまた秋葉原方向に向かって歩く。だいたい僕はその途中で腹が減って疲れて一休みしたくなってくるので、立ち食いそばだったり土日に軒を並べる出店でドネルケバブ(トルコ料理。羊肉をパンでサンドしたようなもの)を食べたり。 再び歩き出して秋葉原駅前まで来たらもう一回折り返して今度は中央通りの一本奥、パソコンの中古専門店やパーツショップなんかのある通りへ。ここでなにか出物があったりするので、じっくりと店を眺めるのが恒例だ。ちょっと型落ちのCPU/ちょっとレアなPDAのアクセサリ/ちょっと面白いUSB接続のグッズ。手にとって眺めながらまた末広町方向へ。それでもってまたまた折り返し、もう一本奥へと向かうと秋葉原本来の持つディープさがむき出しになって見えてくる。くたびれたメモリ/IBMのマウスだけ詰め込んだ段ボール/一台500円のジャンクなPC-98NOTE。知識の薄い自分には使いこなせるわけなんてないんだけど、その「何が何だかわからない感じ」がなんだかわくわくさせる。違法なものに手を出すことさえしなければ、好奇心をこんなに満たしてくれる街はない。 一方の汐留やお台場には、そんな場の力もなく、どことなく嘘くさいエンターテインメントの匂いがする。でも、そんな嘘くささの混じった箱庭は、それはそれでなんというか別の意味でテクノでサイバーなんじゃないかと思うんだけど。 そんな「別の意味でのサイバーさ」=いわゆる顔のない「箱庭」的な街を闊歩するには、人はそれぞれ個性を押し殺して薄っぺらい顔をしなければならない。もしくはおのぼりさんの顔を無理矢理作って無邪気に見上げることがよしとされる。なぜなら、「箱庭」はそれ自体で完結する底の浅い街の物語で、歴史的な地層の厚さなんて誰もそこに求めないし、その地層の厚さによって生じる迷路的なわくわくも物語性も求めない。求めるのは目新しさと嫉妬の混じった羨望だけだからだ。だけど、秋葉原にはそんな心配はいらない。歴史性/地理性の深い場所では、「箱庭」でみんなと同じ一般人のふりをして顔のない顔をしている必要はない。欲しいものには目を輝かせ、好奇心のおもむくままにうろついていられる自由がある。友人に話すのはちょっとためらわれるような好みでも、この街ではそれを堂々と表に出して歩ける。そして日常で潜めていた自分を許してくれる街でもある。無線が好きならそれでいい。クロックアップに命をかけるならそれでもいい。もちろん萌えちゃっても大歓迎だ。アホで/オタクで/サイバーな、そんな街などここだけだ。ネットじゃ見えないリアルな人と物が溢れて、どこにもない「自分だけのもの」が見つかる街。でっかい量販店のビルが建っても、TXが通っても、やっぱりそこは変わらずに面白い街が「アキハバラ」。
「東京」とフットボール。
2007年02月12日
昨日のエントリで極私的な「東京」への思いをぶちまけて収拾のつかないまま無理矢理に終わらせてしまって(文章としては最低の終わり方だ)、なんとなくもやもやしたまま起きた今日。激しく雪が積もる外を見て出かける意欲を早々になくした僕は、書棚の整理なんかを始めることにした。もともと家にあるのと同サイズ同色で買い増しして設置していたカラーボックスがきれいに(まるで三浦フットボールにおける4バックのラインのように!)並んでいるのだから、中身もきちんと並べようと。そうしてせっせと単行本や文庫本を並べ替えているときに、ある本を持っていたことを思い出した。それが今回のエントリを書くきっかけになった『フットボール都市論』だ。この本で舞台となっているのはパリ、マルセイユ、香港、そして東京。そんなわけで、この本をきっかけとして昨日の「東京」の話を再びしてみたい。今度は個人的な側面からでなく「フットボール」と「都市」という側面から。 周知の通り、東京には二つのJクラブがある。FC東京と東京ヴェルディ。この2チームと、その周辺(いわゆる「首都圏」「郊外」という言葉でくくられる地域)を軸にして「東京」というのはどういう街なのかということを書いておきたい。 まずFC東京と東京ヴェルディにおける「東京性」の差異から。 東京ヴェルディは等々力競技場をホームスタジアムとする「ヴェルディ川崎」として発足した。前身の読売クラブ時代から日本代表を数多く擁して多くのタイトルを獲得してきたのだが、2001年の東京移転初年度にJ2降格の危機に瀕する。かろうじて残留に成功した後、2004年の天皇杯で優勝するものの翌2005年のシーズンではJ2に降格し、今年2シーズン目のJ2を戦うことになっている。 それに比するFC東京は、旧JFL所属の東京ガスサッカー部を母体として創立されたチーム。当初は東京ガス時代から引き続いて深川のグランドで練習し、江戸川陸上競技場や夢の島競技場、西が丘サッカー場などをホームとして戦ってきた。1999年、J1へ昇格すると2004年に初のタイトルとなるヤマザキナビスコカップ優勝を果たす。 この2クラブのプロフィールを比較してみると、J1/J2といったリーグにおける存在位置以前にもっと対照的な点が浮かび上がってくる。日本のフットボールにおける黄金時代を築いたヴェルディと、下町の企業サッカー部からトップリーグまで上がってきたFC東京。歴代の日本代表を多く輩出したヴェルディはテクニックとセンスで魅せるのに比べて、FC東京は知名度にそれほど高くない選手がほとんどで、「部活サッカー」と揶揄されるほどに愚直で運動量のあるゲーム運びをする。なぜ同じ「東京」を掲げるチームが、こんなにも大きく違うのだろう?
まず、一つにはそのクラブそれぞれが生まれ育った土地性があるのではないか。ヴェルディはJ発足当初こそ「川崎」であったが、その前の読売クラブ時代は「東京」のクラブである。当時のニュータウンにおけるシンボル的な存在であったよみうりランドに天然芝4面(!)の練習場を持ち、外国人監督やブラジル人選手を積極的に呼び寄せレベルアップを図った。一方のFC東京は江東区深川というまさに「下町」のグラウンドから企業のサッカー部として設立され、社員選手を中心にして戦ってきた。この「ニュータウン」と「下町」という地域性こそがまず互いのクラブにおける決定的な差異といえる。ニュータウンの先進的なスタイルと、下町の表すいい意味での「江戸っ子」なスタイル。この違いが、そもそもの出発点ではないだろうか。 もうひとつは「都心」の経験だ。 ヴェルディは国立競技場というまさに「都心」の地域で多くのタイトルを獲得してきた経験を経て、東京の調布へと移転した。それに引き替えFC東京は国立は国立でも古き良き東京情緒たっぷりの「国立西が丘」を経て同じ調布へと移転した。そして当然、表舞台のフットボールとそこに立てなかったクラブのフットボールも大きく異なる。J1とJ2のフットボールが違うように。 「ヴェルディ=読売クラブ」が「聖地」で華やかなフットボールを体現して勝つために求めたものは、多少わがままなプレーであっても高い技術を持つブラジル人や日本代表選手の存在であり、それを受け継いで新たな日本代表選手を生み出そうとするシステム。 一方の「FC東京=東京ガス」は、無名であってもチームのために貢献できる粘り強い選手、走れる選手、それを理解して安い年棒でもプレーしてくれる外国人。 東京ど真ん中、千駄ヶ谷に位置する国立霞ヶ丘というまさに「都心」の場所において、国内の「フットボールの中心」を経験したかということそのものが、クラブの歴史とプレースタイルにくっきりと浮き出ていると思う。 象徴的な例として「フットボール都市論」でも触れられていた、2001年2ndステージの東京ダービー、ヴェルディ側のホームで迎えた東京スタジアム(当時はまだ「味の素スタジアム」ではなかった)での試合を挙げておきたい。ヴェルディは当時、北澤豪、小倉隆史、三浦淳宏、武田修宏、前園真聖、永井秀樹といった元日本代表プレーヤーを多く抱えていながらも結果を出せないどころか「2部落ち」の崖っぷちに立たされていた。監督も松木安太郎から小見幸隆へ交代してもなかなか結果を出せないなかで、クラブが選択したのは元ブラジル代表のエジムンドをレンタルで獲得するという「スタープレイヤーのさらなる追加」だった。この選択があまりにも「ヴェルディ的」であるのに対して、FC東京はこの試合をアマラオ、ケリー、サンドロのブラジルトリオを欠く「純国産」メンバーで望んだ。結果的にはヴェルディが勝利してその年の残留を決めたのだが、この状況はFC東京と東京ヴェルディという二つの「東京」を際立たせるには、あまりにも対比的で象徴的な試合ではなかっただろうか。 前述『フットボールの都市論』では、パリ・サンジェルマンをこう評している。 「首都に拠点を置くチームが罹る病気。それは、国家を『代表』するチームになる、と言う幻想である。ナショナリズムとリージョナリズム……言い換えれば、地域主義が曖昧な形で、しかも強く国家主義と連携してしまうのだ。」(P160) この言説は、まさに東京ヴェルディにも言えるのではないだろうか。 そしてFC東京は2004年にナビスコカップを、東京ヴェルディは同じく2004年に天皇杯を獲得したわけなのだが、「東京」と「フットボール」というつながりはここをピークとして弱くなりつつあるのではないだろうか、というのを考えている。それは「郊外」におけるフットボールが強大化して、「東京」を浸食し始めているという現象である。つまりは浦和、千葉、横浜、川崎、柏といった「東京」に対する「郊外」をホームとするチームの台頭である。 この現象はすでに2002年から現れていると考えている。 まず、ワールドカップの決勝は「聖地・国立」ではなく、新横浜という新時代のニュータウン地域に建つ「横浜国際総合競技場(現・日産スタジアム)」であったということ。2002年と2003年にJリーグを連覇したのは首都圏のチームでも、磐田や鹿島といった古参でもなく「横浜F・マリノス」であったということ。さらにはワールドカップだけでなく、世界クラブ選手権(トヨタカップ)決勝戦も国立から横浜国際での開催に移行される。そして2004年には浦和レッズがナビスコカップ制覇、2005年にはジェフユナイテッド市原(当時)の同タイトル制覇、2006年の浦和レッズのリーグ優勝、さらにはタイトル制覇こそならなかったものの川崎フロンターレの大躍進といった事象を通じて、「郊外チームの強大化」が進んでいった。 それと入れ替わるようにFC東京はガーロ監督によるポゼッションサッカーへの転換を図ったが失敗し、降格の危険を感じるほどまでに低迷する。さらに東京ヴェルディは降格、2006年からJ2での戦いを強いられることになる。この入れ替わりが「東京」という街におけるフットボールの力が弱体化していることを表すと同時に、同じ「東京」ブランドのチーム同士の差異に加えて「東京-郊外」という差異も表されたのではないだろうか。 そういった「東京-郊外」という差異は過去の歴史から続く「都市機能を肥大化させる一方の東京都心から人が消え、その都心へ通勤する労働力の供給源」という位置づけであったものだが、近年における「郊外」が持ち出した「新都心」や「新ニュータウン」という、東京をスルーしても生きていける都市の力そのものの上昇とも無関係ではないと思う。「郊外」が十分に主役足り得る機能を持つ都市として完成されたからこそ、そこに注ぎ込まれる経済の恩恵と、そこに住む人々の地元帰属意識の上昇こそが地元のフットボールに大きな影響を与えたのであり、「郊外」のチームが台頭した要因ではないかという思いがある。 それでは「東京」のクラブが再びクローズアップされるにはどうすればよいのだろうかと考えたとき、思い至るのはやはりそれぞれのクラブにおける「ローカリズム」のさらなる追求ではないかと思う。今まで培ってきたクラブの方向性をとことんまで突き詰めてそれぞれのクラブがもつフットボールのスタイルを体現すること、それ以外ないと思う。東京におけるローカリズムの強化。それは秋葉原が一方向(つまりは「萌え」方向に)に大きく突出してローカリズムの成長を遂げたように、ベッドタウンという存在以外にもっと何か突出した存在がなければ地域は成長できないということでもある。「フットボールの街」以外の何かによって地域が成長すれば、そこに根付くフットボールも面白くなっていくものだと思っている。いびつに発達すればするほど、フットボールは逆に面白くなっていく。「いびつであること」を恥じず、その意識をローカリズムに変えて。 最後に、前述書からもうひとつの文章を引用したい。 フットボールは言葉では語り尽くせない。フットボールにとどまらず、どんな言葉であっても世界を正しく語ることはできない。だからこそ言葉があり、語ることがあるのだ。 言葉は、ゴール裏で狂うことと同じくらい大事なことなのだ。 「私たちはハンドの判定の声などに消されることのない強度を持った言葉を見つけなければならない。もしかすると、私がフィールドを眺め続けているのは、そんな言葉を探しているからなのかもしれない。」(P157) ※参考資料・神野俊史著『フットボール都市論』(2002年、青土社) ・東京ヴェルディ1969オフィシャルサイト ・FC東京オフィシャルサイト
近くて遠い街。
2007年02月11日
TBSラジオで現在放送されている番組に「文化系トークラジオ Life」というのがあって、ここ半年ばかり毎週聴いている。とはいえ北海道の地上はラジオではネットしていないので、Podcastで聴いている。ラジオで流れたトーク部分がまるまる聴ける上に、Podcastでしか聴けない「外伝」なんかもあったりしてなかなか面白い。内容はと言えば、「戦争とサブカルチャー」のような堅いテーマから「モテる技術」なんていうユルいテーマまでを「文化的側面(体育会系とは真逆に位置する、サブカルや社会学系なところ)」から、メインパーソナリティーの鈴木謙介氏と編集者・ライター・批評家などのサブパーソナリティーがあれこれと語るというトーク番組。自分もどっぷりと文化系な人間なので、トークに共感したり笑ったりうなずいたり。ほんとうに面白いので、是非一度聴いてみてください。 で、2月3日の放送は「東京」というテーマだったのでいつもよりもじっくりと聞き耳を立てていた次第。なんで「東京」というテーマにぴんと来たのかというと、大学時代に卒論を書いたテーマが「大正政治史における関東大震災の復興計画について」なんていうものだったからだというのもあるし、東京という存在そのものが自分にとってものすごく興味を惹かれるものであると同時に、いろんな感情や思い出のある街でもあるからだ。 そもそも「東京」という存在に興味を持ったのは大学で都市論の講義を聴いたり、ゼミで江戸時代の文化や東京の近代建築について調べたりしたのが最初のことで、そこから日本政治史を専攻にしたということもあって「東京の都市計画」という話と「大正時代の政治」を組み合わせて研究(というにはおこがましいが)していたことから、というのが表向きな話になる。ただもっと個人的な話に限定していうと、高校時代にまで興味のきっかけは遡る。
高校時代、僕は大学進学を考えていたもののどこに行くかは考えていなかった。親からは「地元の北大に行け」とは言われていたものの、大学にまで北海道で過ごすのはなんだかもったいないとぼんやり思っていた。せっかく進学するのだから、首都圏か阪神圏の大学に行きたいなあと考えて調べてみると横浜の某国公立大学が自分のレベルにあてはまった。合格レベルで言うとC判定プラスくらいだったかと思う。その大学に狙いを定めて「私立には行かないんだから道外に出てもいいじゃん」と親を説得して、無事に合格できた。そのときの僕は 「あこがれのトーキョーライフ!」 という考えでいっぱいで、前途洋々とした新生活にわくわくしていたのだ。だけど、この時点で地方の人間が陥りやすい一つの罠に嵌っている。それは「1都3県みんな首都圏」という間違った思いこみである。たとえ住むのが横浜だとしても、行けば高円寺や下北沢みたいなサブカルチャーの匂いがするちょっぴり刺激的なキャンパスライフを送れるものだと信じ込んでいたのだった。後にそれはものの見事に夢と砕け散り、それゆえに「東京」という街そのものへのねじれたコンプレックスを持つことになってしまったのだけど。 そうやって無邪気にわくわくして上京して横浜での新生活を始めた僕は愕然とした。横浜は横浜でも、僕の通っていた大学はかなりの横須賀寄りに存在するのに伴い、住むところも必然的にそっちの方向に引っ張られることになった。京浜急行の「屏風浦(びょうぶがうら)」というなんだかそこどこよ(横浜のみなさんすいません)、というような小さな駅から坂を上って15分のところにある6畳一間のアパートで理想とはかなりかけ離れたうらぶれた生活だった。僕が抱いていたアーバンでクールなシティライフはどこへ行ったんだ!と思いながらもそこは学生、なおかつアウェイ遠征で常に金のない身には引っ越しなどできるはずもない。近くには横浜一荒れていると噂の高校もあり、かなり窮屈だった。東京(首都圏)ってこんな街じゃないよなあ、と万年床の上で思い続けていた。後に屏風浦はとあるロックバンドが出したアルバムの中の曲名にもなってちょっと溜飲を下げたような気もしたけれど、やっぱり東京という街への妄想的な憧れや、一方的な思いこみに近いコンプレックスは消えなかった。 その大学を卒業した後、僕は東京に勤務地のある会社に就職したのだが、そこでもまた「自分の思い描いていた東京」とはかけ離れた世界にがっかりしてしまうことになる。 一つめが職場。面接は渋谷の宮益坂(この地名だけでなんだかときめく)をちょっと登ったところにあるオフィスだったのに、いざ配属となってみると「五反田」。なんだよそれ!とひとり憤慨してしまった。東急の地下で昼ご飯を買ってきたり会社帰りにHMVに入り浸ったりとかできないじゃん!俺の思い描いていたアーバンで(略)なトーキョーライフはどこへ!そうしてさらなるがっかりを得つつ五反田のオフィスで働くことになったのだけど、ここもなかなか僕の想像とは逆方向に濃いところだった。夜遅くまでやってるのは飲食チェーン店か本屋が一軒くらいのもので、昼ご飯を食べるのは居酒屋がやってる高めなランチメニューか、もしくは古い店構えで安いけど微妙な味の料理を出す中華屋くらいしかなかった。駅の向こうにはあやしげな飲食店と風俗店ばかりがギラギラとネオンを光らせていた。せめて東京で働いてるときくらい、かっこいいトーキョーライフ……なんていうのはもはや夢物語でしかなかった。 さらに追い打ちをかけたのがその当時住んでいた借り上げ社宅で、こともあろうにアーバンとはほど遠い南武線沿線にある川崎市の某所(川崎市のみなさんすいません)にあるマンション。仕事が終わって最寄り駅に降りるとコンビニの灯り以外は真っ暗な街で、仕事で失敗した時に帰るときなんかは暗さで悲しみが増幅されて余計に落ち込んだりした。そうして落ち込んだままの何もない休日なんかには、ひとりマンションの裏にある川べりにいってため息をついていた。その僕のため息を流していたのが、多摩川だった。川の向こうは東京の狛江で、渡ってしまえば昔思い描いていた生活にちょっとだけ近づける。けれどそのわずか先にある「川向こう」へ行くだけで家賃は1万上昇し、暮らしはなんとも心許なくなる。どうしても手が届きそうで届かない東京という街。もどかしさを抱えながら僕は川向こうを見つめることしかできなかった。そのもどかしさをどうにかして抑えようと、自分は東京の町並みを散歩することがひとつの趣味になっていった。冬の日にゆりかもめでひとり有明に降り立ち、海から叩きつけてくる強風に身を任せてさまよっていたり、深夜の新宿から皇居までひたすら歩き続けてみたり、休日に用もないのに出かけては都内のビジネスホテルに泊まってみたり、そんなことを延々繰り返した挙げ句に僕はいろんな事情で仕事を辞めて札幌に帰ることになってしまった。 札幌へ帰ることになった時の気持ちを今でもよく憶えている。どうにか川向こうまで近づいた東京から、こんどは海峡ひとつ隔てた地元へ出戻りになるという惨めさ。地元へ逃げ帰るような悔しさ。僕は荷物をまとめながら、東京への憧れが一部分で逆流して心のどこかで憎しみへと変質していくのがありありと感じられた。大学へ進学を決めたあのとき、僕は確かに「故郷」を心の中からどこかへ捨てる覚悟でここまで来たはずだったのだ。どこでもない、「東京」で自分は生きていく覚悟を決めたはずだったのだ。室生犀星の言うとおりに「故郷は遠くにありて思うもの」で、盆と正月の帰省に「とらや」の羊羹なんかを手みやげにして帰り、東京の話をすることがささやかな夢だったのだ。それがただの見せびらかしであったとしても、自己満足であったとしても。東京に暮らしてもフットボールは故郷を応援するという、二律背反のような思いを持っているとしても。 それから幾星霜、今も僕はいったん捨てたはずの札幌で冬を越している。どうして僕はここにいるのだろう――そんな思いを抱きながら。今夜みたいな真冬の夜には、特にそう思う。僕は今でも、東京への思いを捨てきれずに、いつか必ず住んで、あそこで生きてやるとずっと思い続けている。その思いは、フットボールとは全く別のところにある、僕自身がどこまでも拘泥していることだ。 僕だけにとどまらず、東京について語るべき思いを持つひとはたくさんいる。それが憧れであれ、はたまたどうしようもないほどの嫌悪であれ。その街並、社会性、様々な文化の発信拠点、「東京」という街の名前を聞くとどうしてか思いを巡らせずにはいられないのは僕だけではない。ラジオでいろんな人がいろんな東京を語る声に耳を傾けつつ、なんでこんなに東京は「語りたい街」なのだろうかと思いめぐらせつつ、なんだか思っていたよりも違う愚痴っぽい方向にいってしまったこの文章に苦笑いしつつ。
君のスロットに僕のメモリをインサート
2007年02月08日
Happy Hacking Keyboard Lite2 USB JP 黒 Windows Vistaも発売され、自分もPC使って10年超えてきたわけですが。 ここまでネットが普及して、その真偽はともかくとしてとりあえずの情報はネットの中で手に入るだなんて思ってもいなかった。95発売ブームに乗せられてうちでも富士通のPCを買ったはいいが、高価なフリーセルとマインスイーパ専用マシンと化してしまった。 でもこれが最初のコンピュータ経験というわけでもなくて、その前にはこれまたその時代には高価だったパナソニックのワードプロセッサー(あえて正式名称で呼んでみる)をいじっていた。今にして思うと父はこういう新しいものが好きだったんだろうなー。それだけじゃなくMSXも持っていて、ひとしきり文字を打ち込むには苦労はしなかった。ワープロはさいしょかな入力だったのを無理矢理ローマ字入力に矯正してがしがし打ち込んでいたし。何を書いていたのかは忘れてしまったけれど、たんたんたんとリズムよくキーボードをたたき文字を打ち込んでいく作業は僕にとってはすごく楽しい時間だった。打鍵音とともに画面に映ってゆく文字列をえんえんと増やすのは子供ながらに快感だった。
大学に進んでさっき言った富士通のパソコンも「レポート作成用に」と頼んで持ってきてもらって、1年目はその付属キーボードをかたかた言わせながらレポート作成にいそしんでいた。レポートのパフォーマンスが良かったのかはまた別の話だけど……。 で、3年目にそのパソコンが壊れちゃって、先輩からCOMPAQのパソコンを譲り受けることになった。こいつはデカかった。前に使ってた富士通の1.5倍くらいあった。CRTには奇妙な出っ張りがあってそこにスピーカーを引っかけるようにできていたのでデカかった。本体もなぜだか妙にでかかった。そしてなにより、キーボードが病的にデカかった。当時の僕の机はパソコン本体が半分を占めていたんだけど、それに加えて付属のキーボードをつけるのはレイアウトから見てどうみても不可能だった。いや、不可能ではないだろうがイヤだった。そんなわけで出かけたのだ、初めてのアキハバラシティへ。 初めて電気街に足を踏み入れたとき、どこに何があって、どこへ行けばいいのかさっぱりわからなかった。 魔都だここは。 そうにちがいない。 そう思いながらもダンジョンを探検するような緊張感で大通りから一本裏の道へ入るととたんにそのレベルが上がった。何に使うのかもわからないパーツだらけ。むき出しにされて売られているメモリ、店頭に飾られている茶こけたPC、すすけた筐体、謎の電源スイッチみたいなもの。何が何だかわからないまま、自分がほしいのは省スペースのキーボードであるというのも忘れそうになるままパニック状態で歩くと、ジャンク屋や中古屋や怪しげな中華料理屋なんかが並ぶ通りに一軒の店が見つかった。その店はキーボードだけを売っていた。 まさに天恵。 まさに奇跡。 ねんがんの アイスソードを てにいれたぞ! そういう店に行きたかったのだ。そういう店で自分の部屋にぴったりサイズのキーボードを探したかったのだ。そうして魔都秋葉原から帰還した僕は、1枚のキーボードを手にしていたのであった。テンキーもなくノートPCのキーボードのような形をしていたそれは、自分の机にあるスペースを有効に使うにはもってこいの品だった。もっとも、ストローク(キーを押し込む深さ)が浅いせいで幾度か突き指のようになったりとか(それは単純に自分の押圧が高いせい)しながらもほぼ2年半、卒論を書き上げるまでの相棒になったり、ながながとしたメーリングリストの返信に使ったりした。そうして社会人になってお金ができると、今度はもっと打ち心地のいいキーボードを探しに秋葉原に行くようになった。もっと重厚感のあって、押しごたえのあるやつをと思ってみつけたのはFILCOのメカニカルキーボードだった。押してみるとじゃきん、という音がする。続けて打ってみる。じゃきじゃきじゃきじゃき。その重厚感というか、「機械っぽさ」に惚れて買い求めた。後にしてそのキーボードが「名機」と呼ばれているのを噂に聞いて得意げになったものだ。札幌に戻った後もがしゃがしゃがしゃがしゃとこのキーボードを使いまくり、隣室の弟から使用禁止令が出るくらいまでになった。それでもちょっとやそっとじゃ壊れないのはタフな証拠だ。主キーボードが壊れたときの代替機として待機してもらっている。 そして、その「名機」をサブ扱いにしてまで、今使っているのは「Happy Hacking Keyboard Lite2(略称HHK)」だ。キータッチはほどよい打鍵感をもたらしながら、しっかりとしたストロークが中途半端なキー入力も逃さない。そしてなにより小さい。文庫本を縦に2冊並べたくらいの横幅しかスペースを必要としないこのキーボードは、小さい分無用に指を広げる必要もなくリズムを刻んでくれる。実はこのHHK、2代目だったりもする。初代はコーヒーをこぼして動作不良になり、泣く泣く現在の2代目を注文したのだった。同じキーボードじゃないと打てないってところがガンコっていうかマニアっていうか。 そんなわけで、このブログもHHKで書いてます。こいつと一緒にどんだけ文章が書けるのか、楽しみです。
ななめ上から見上げるフットボール――小田島隆「サッカーの上の雲」
2007年02月06日
サッカーの上の雲―オダジマタカシサッカ~コラム大全 司馬遼太郎の本ではありませんよ(挨拶)。 小田島隆という人は生粋のサッカー畑ではなくていろんなコラムを書いている人なんだけど、この人がサッカーを語るとこんなに面白いのかと爆笑しながら読んでました。 だって2つめのコラムのタイトルがいきなり 「伸二の食生活が心配だ!」 ですよ。 小田島氏は浦和サポなので当然浦和系の話が多いんだけど、その合間に挟まれるいろんな選手のことを主に妄想をネタにして書いてます。たとえば伊東輝悦が年に一度見せるか見せないかの長距離ドリブル(ただし20メートルくらい)の美しさとか、服部年宏のニヤつき具合とか、大熊清の大声とか。そういう「ななめ上からだけ見えるフットボール」について語っていて、読んでいると思わずニヤニヤしてしまう。かしこまった「〇〇戦記」とか、プロのスポーツライターの書いたルポなんかもじっくりと読むのもいいけど、小田島氏でしか書けないであろうこのコラムも一読の価値あり。 (どうでもいいが、「伊東輝悦」も「服部年宏」も一発で変換できた。すごいぞATOK!)
考えてみればこういう「妄想系」って、友人とサッカー系バカ話をしてるときの感覚によく似てる。飲み会とかアウェーの帰りとか、そういう時にしたことありませんか、バカ話。旬なところでいえば札幌のキャンプ、こないだのオフに曽田選手が熊本城に行ったなんて記事がありましたけど、 「熊本城って籠城戦向きの城だよな」 「籠城戦のために銀杏とか植えてあったらしいぞ」 「銀杏くさいDFはイヤだよね」 「あと仁丹くさいDFもキツイよね」 「水戸の選手が全員納豆くさいとかな」 「でも熊本城って落とされなかったんでしょ?」 「そうだけど、結局原因不明の失火で焼けたんだよね」 「オウンゴールかよ」 「しかも曽田さんですよ」 「そうですか」 「そうですよ」 みたいな。 そういうことを延々と語り続けられるひとにおすすめです、この本。 けれど、もっとも読んでほしいのは最後にあるコラム「浦和をビッグクラブと呼ぶ日」である。『Number」667号「超浦和主義。」』に掲載されたコラムだけど、浦和一色のこの特集の中にあって小田島氏のこのコラムだけは異彩を放っていた。小田島氏だけが書けるであろう、ちょっとひねくれた愛情とひたむきな狂気(もちろん、いい意味での「狂気」だ)が彼の過去のエピソードと一緒に語られている。ベストエンドを目前に控えたチームを見続けてきたプライドと、一足早い歓喜と、それをクールさで押しとどめようとする理性のぶつかり合い。頭の中が混沌として「どうすんのよ、オレ」みたいになっちゃう、そんな気持ちが手に取るようにわかってニヤニヤしながらしみじみしてしまう。 このコラムだけは、何よりもオススメです。 最後に、小田島隆氏著作のおすすめをもうふたつほど。 「イン・ヒズ・オウン・サイト-ネット巌窟王の電脳日記ワールド」 「テレビ標本箱」 いずれもサッカー関係ではないコラム集ですが、お手にとってみては。
極私的スガシカオ論――カタルシスのないパレード
2007年02月04日
スガシカオ-ALL SINGLES BEST 別冊カドカワ(総力特集)スガシカオ スガシカオを初めて聴いたのはたしか19才の夏。父親の運転する車に乗っているとき、ラジオ(たぶんノースウェーブだ)から流れてきた「ヒットチャートをかけぬけろ」だった。その頃の僕はとりたてて現状に問題のない大学一年生で、のんびりと帰省を楽しんでいるところだった。気にしていたことと言えば彼女がいないこととぼんやりした将来への不安ぐらいだった。そんなユルい空気の中で聴いた、何かいじけたような歌詞の乗ったメロディーを、乾いたようなざらついたようなギターとボーカルが歌うその曲は、なぜだかどうしようもなく僕を焦燥に駆り立てた。そして僕はすぐさまレンタル屋に行き、デビューアルバム「Clover」を借りてきて聴き込んだ。スガシカオの歌と向き合うようになったのは、ここからだ。でも19才でなんて、今にして思うとなんてスガシカオ的なんだ(「19才」という名曲がある)。
「Clover」を初めて通して聴くと、今まで僕が聴いてきたものとは全く異質で、でもどうしようもなく心をかき立てられる彼の音楽に吸い込まれていった。高校時代テクノばかり聴いていた僕は現実問題として彼女をつくるよりも早く、スガシカオの音楽に取り込まれてしまった。「ドキドキしちゃう」で心のリズムを乗せられ、「イジメテミタイ」でじらされて、「黄金の月」で泣かされた。ちなみに「黄金の月」はそのあともいろいろあって自分にとってはとても大事な曲になって、一時期スガシカオ楽曲で最多の再生回数を誇ったあと大事になり過ぎてほとんど聴かない(聴けない)曲にまでなってしまった。 そんな僕の情熱さめやらぬ「Clover」を聴き込んだすぐ後にアルバム「FAMILY」がリリースされたとき、当然ながら僕は飛びついた。それからアルバムとシングルを繰り返し繰り返し聴き続けながら僕は年をとり、スガシカオは相変わらずざらついたクールな声とうねるようなファンクをベースにしたリズムで歌い続けてくれていた。その彼の10周年を記念した「ALL SIGLES BEST」が発売されたときも僕は当然のように買い求めた。毎日会社に行くときにスポーツ新聞を買い求めるサラリーマンのような感覚で手に入れて、でもスポーツ新聞にはないはやる気持ちを抑えながらiPodに転送して、イヤホンを耳につっこんで、再生。最新シングルの「午後のパレード」からリリースを遡るようにして収録されている曲を聴きながら、スガシカオがこうまでして僕(と僕ら)を虜にしてしまうのか、と自己嫌悪みたいな気持ちになった。 スガシカオの歌詞は身の回りの物事についての痛みと弱さをえぐり出して見せている。それはたとえば「夜明けまえ」のような日常に潜む空虚さであり、「ストーリー」のようなあやうい世界に立っているギリギリさであり、時には「あまい果実」のような内蔵が裏返しになってしまうような愛情表現だったりする。そしてそういうところが行き着いた先にある乾いた笑いのような投げやりな感情だったり、「もういいや」というようなあきらめの感情であったりする。そういった歌詞のひとつひとつが小さな棘になってちくちくと僕の体を刺していく。それがまた快感であるのだから始末に負えない。そりゃあ歌詞だけみればただの大人になりきれないおちゃらけた感じだったり、自己嫌悪とやりきれなさの混合されたどろどろした液体だったり、どうしようもないドSだったりするのだが、これがリズムに乗ると一気に変化する。うねりを持ってもっとどうしようもない感じになったり、時にはぐっとシリアスにもなって聴くものを引き込んでゆく。それをさらにスガシカオ自身の時に乾いた、時に湿ったようにも聞こえるざらっとした声が引き立てる。そこでリスナーが耳にするのは澄み切った声ではない、ポップなメロディでもない。それどころかどの曲を聴いても通底して感じる「違和感」こそが最大の魅力なのである。けれども、そこで感じる「違和感」の正体は誰もが持っているのであろう「孤独」「自分の弱さ/無力さ」「すれちがいの感情」みたいなありふれたものだ。そういったものを改めて音楽として提示されたとき、人はそれを「違和感」として処理しようとするけれども、そうできないわだかまりがある。なぜならその「違和感」が自らのうちにあるものだということに気づいているからこそ、見逃せない/聴き逃せないのだ。そうしてるうちに彼の音楽は遅効性の毒みたいに全身に回ってしまって、離れられなくなる。 さらに、スガシカオの音楽にはもうひとつの特徴があるように思う。それは「カタルシスがない」ということ。最近の曲、たとえば「奇跡」や「午後のパレード」なんかは明るい曲調であるにせよ、歌われているのは「奇跡が起こりそうな予感にドキドキしているけど、その未来の薄っぺらさも感じている自分」(「奇跡」)だったり、「未来へずっと続いていくようなんだけど、どことなくうさん臭さを感じさせるようなパレード」(「午後のパレード」)だったりする。そして「奇跡」と「午後のパレード」の間にひょいと出てくる「真夏の夜のユメ」では「孤独で嘘つきな自分を自己嫌悪する僕」というような、闇がべったりと塗りつけられたりするような音楽が出てきたりする。そんなふうにスガシカオの曲は聴いている人に「はっきりとした答え」を明示しない。明快なメッセージを送らない。違和感を違和感としてとらえ、歌っているのだ。たとえば「こんな僕でも人を好きになっちゃってもいいんですか?いいんです!大好きです!愛してます!」と歌っているポップス(僕がそういうのを嫌いだというわけでは決してない)とは対照的にスガシカオは「僕は人を好きになってもいいのかなあ、好きになって『愛してる?』とか言われてもどう答えていいかわからないしなあ」っていう感じである。そしてそんなうだうだしたようなうじうじしたような流れの中で音楽は終わる。答えはない。確信に満ちた決意もない。当然、リスナーがカタルシスを感じることがない。でもだからこそスガシカオなのだ。カタルシスは他のアーティストに任せておいて、「カタルシスがないまま放っておかれるいやらしさ」を味わい、リスナーがその青臭さや泥臭さに身もだえする音楽こそがスガシカオなんだと思う。 最近出版された「別冊カドカワ」のなかでスガシカオは「自分の音楽は懺悔や自分の救済である」と語っている。自分が他人よりも音楽の才能を持って生まれて、選ばれて歌っていることへの懺悔であり、その懺悔を通じて他人を救済することによって自分も救済されるというサイクルがモチベーションである、と。そういった彼の思いがそのまま歌になって、リスナーはそれを聴いて「カタルシスがないことの事実確認」をしてある意味で安心する。そういうものが「スガシカオの音楽」なんだろう。
Mes que un club
2007年02月03日
ちょっと昔の話になるが、FCバルセロナ(以下バルサ)が、ユニセフに年間数万ドルの援助を行う提携をしたというニュースがあった。もはやバルサはフットボールクラブを超えた存在であり、その向こうにある貧困や差別をも解消していく――そんなクラブを目指そうとしている。そのスローガンが、「Mes que un club(クラブ以上の存在)」というわけだ。世界の貧困と戦う、というのは確かにフットボールを超えた戦いの場所である。バルサのフットボールに魅了され、ファンとなり、その試合をカンプ・ノウで見ることで利益が発生する、その一部が基金となり、世界中の貧しい国々へ送られる。バルサを見ることが、世界の貧困を救う一つの手段となり得るようになったのだ。おそらく、このようなことができるのはバルサだけだろう。(レアル・マドリーもできそうではあるけれどなあ……) 「クラブ以上の存在」と言っても、言い方によっては大きく解釈が分かれるところではある。「クラブ」よりも規模を拡大し、社会的に「単なるフットボールクラブ」以上の存在になろうとする姿勢が一義。もう一義は、「ファンの一人一人の人生において、そのクラブの存在が何よりも大きくなること」がもう一つの意義だ。ゲームにも練習場にも足繁く通い、勝利の時には全世界が幸福に満ち足りているような思いを、逆に敗れたときには世界が明日にでも9終わってしまいそうな悲しい思いをする人々。こういう彼ら彼女らにとっては、すでにフットボールクラブはその人生を左右するという意味において「クラブ以上の存在」なのである。
さて、ここで札幌は「クラブ以上の存在」たり得ているのか、という疑問が生じる。 バルセロナのような「一般クラブを超えた、社会的な存在」はもとより無理であるのは明白だし、そんなことをするならまずチームとしての人気と、新しいファン層の獲得を行うことが急務であるのは誰の目から見ても明らかだ。介護や食育事業にも力を入れる、ということだけどそれは「社会貢献」のうちの一事業に過ぎない(介護・食育事業への展開を批判しているわけではない。逆にうまく軌道に乗せてほしいと思っている)。 それならば目指す先ははっきりしてくる。J1への昇格と、「魂に訴えかけるフットボール」である。J1に昇格しなければファン層は拡大しない。そしてファン層が拡大できたとはいいえ、そのファンに訴えかけるようなフットボール――僕らの人生に劇的なとまではいかないまでも、ささやかにでもいいから彼らの人生における幸せと落胆、そして「気持ち」をもたらしてくれるものであるだろうか。僕の現段階での回答は「否」である。 前シーズンの柳下監督時代は、明確な意志を持ってはいたがそれが選手個々にまで行き渡っていたかというと疑問が残るし、「ともに喜ぶ」ではなく「ともに苦しむ」ことの方が多かったのではないだろうか。三浦監督が指揮を執ることが決まってから、僕は「ともに戦う」「ともに喜ぶ」チームであってほしい、と思っている。4バックとか、カウンターとか、戦術以前の話ではない。どれだけ一体となって戦えるのか、大きく言ってしまうのならばファンがそこに「生きる意味」を見いだすようなサッカーをしてくれるのか、そのことだけが気がかりだ。 少し、自分自身の話をしたい。 昨年父と会ったときに話していたところ「まだコンサドーレは応援しているのか?」と唐突に聴かれた。嘘をつく必要もないと感じたので、以前と変わらず通っていることを父に話すと父は突然に渋い顔になった。つまりはこうだ――もういい大人なのだから、ゴール裏で飛び跳ねるような酔狂に関わっている場合ではない。コンサドーレからは手を引いて、まっとうな社会人として生きてゆけ――、と。父の話を聞き流すふりをしながら、僕はテーブルの下で煮えたぎる怒りを押し殺していた。大学に合格して、どこにどうやって行けばいいのかもわからなかった97年の春、それでも笠松へJFL開幕戦を見に行ったのは、その当時、札幌のフットボールを見ることが、僕の人生にとって必要だったからだ。札幌のフットボールを見るために遠征して、はじめての土地で友人と出会い、ともに応援し、喜びも苦痛も分かち合い、ともに進める仲間ができたことを父親は「ガラの悪い奴らとつきあっている」としか見ていなかったのだ。軽く、いや、かなり、ショックだった。勉強も大事だけど、時にはそれよりも大事なものを探して、そのために生きていくことが大事なのだということを父親が考えていなかった、勉強してどこかの堅い職業に就いてほしいのだというのが父の本音だったようだ。でもそれを僕は裏切った。父の思いがわかっているのにも関わらず、裏切った。アウェーに行きまくり、最前列でリードをとった。 なぜならその当時の僕にとって、そして今の僕にとっても、札幌のフットボールは何よりも大切なものなのだったのだ。札幌のゴールは僕の生きる源だった。札幌の敗戦は僕の勝ちを全否定するほどのどん底をもたらした。そうして、僕にとっての札幌はすでに「Mes que un club」であったのだ。手に抱えきれないほどの愛とプライドを持って、僕はゴール裏へ足を運び続けた。 でもいま、それだけの情熱を、どれだけの人が持ち得ているだろうか(自分も含めて)? 情熱は伝えるもの。喜びは分かち合うもの。誰彼問わず、スタジアムにいる全員で分かち合うものだ。そうして僕らは札幌が「Mes que un club」であり続けるように、精一杯の声援を今年も送る。人生の喜びを、人生以上の価値をこのクラブに――と、心の中で思いながら。
プロフィール
生まれ:1978年旭川市生まれ。 育ち:道内あちこち。その後横浜、川崎を経て再び札幌。 観戦暦:1996年・対日本電装戦が初応援。翌年より道外への進学に伴いアウェー中心に応援、1998年よりアウェイコールリーダーとなる。2003年春に札幌へUターンし、現在ホームゴール裏で応援中。 サッカー以外の趣味:音楽と活字。
最新のエントリー
コメント
検索