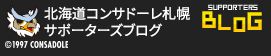「フットボールを読む」夏の10冊・前編
2007年07月11日
夏。 読書感想文の課題を出されて悩む夏。 まあそんな(自分にとっては)10年以上昔の話は置いといて、夏はそういった学生たちの需要を当て込んでいろいろな出版社が「夏の100冊」みたいなフェアを出す季節でもある。以前は戦前の作品や海外文学、ノンフィクション作品も多く取り上げてきたが、最近はエンターテイメント性の強い作品や、いわゆる「ライトノベル」と呼ばれるジャンルの作品も並べられていて時代なんだなあと思わせられたりしている。まあリアルで読書感想文書く世代の人はがんばってください。 そういったノリで、フットボールにまつわる本をセレクトしてみた。さすがに文庫だけというわけにはいかないのでハードカバーも含めて、それでもって100冊も紹介できないので10冊ということで。今回はその前編、ということで5冊を紹介。今日の5冊は「熱い」5冊として、考えさせられるというよりも思わず気持ちを動かされるような本を選んでみた。
・ニック・ホーンビィ(著)/森田義信(訳)『ぼくのプレミア・ライフ』(新潮文庫) とにもかくにも、まずはこの作品を挙げておきたい。英国で100万部を超えるベストセラーにしてニック・ホーンビィの初著作。愛するアーセナルのために人生のあらゆる時間を犠牲にしてハイバリーに通い、週末のホームゲームの予定を邪魔する者には唾を吐き、フットボールに狂い続ける男の一代記。 フットボールがそんなに好きだなんて理解できない!という人にこそこれを読ませたい。昔(60年代以降)のプレミアリーグの雰囲気や歴史を知りたいという人にもおすすめ。
・野沢尚『龍時01-02』(文春文庫) 現在盛り上がっているU-20ワールドカップやこれから迎える北京五輪最終予選に向けて、日の丸を付けた若者の物語を……と思って選んだ一冊。この「龍時」は「01-02」とサブタイトルがあるように、「02-03」「03-04」とシリーズで続いている。著者の急逝によりこのシリーズは未完となってしまったが、高校のグランドで、代表のピッチで、スペインリーグの舞台で右サイドを突破し続ける主人公の成長物語はいつ読んでも爽快で疾走感とライブ感に溢れている。フットボールを知らない人にとっても純粋なエンターテイメントとしても面白く読める。お子さんがサッカー部なんていう人は夏の読書感想文の宿題のために読ませてみるのもいいんじゃないでしょうか。
・最相葉月『東京大学応援部物語』(集英社) フットボールじゃないところから一冊。 東京六大学野球のスタンドで、東大がどんなに負けても応援を止めない一団、東京大学応援部。どうして彼らは厳しく理不尽な「応援」の世界に飛び込んだのか?そこまでして熱くなりたい理由は何なのか?すべてが応援のためにあるとまで言えるような毎日の生活の中で、合宿まで行い、時には倒れ、去る者がありながらも、それでも硬派に生きて母校を応援し続ける彼らの背中からは何が見えるのだろうか? 応援するって何だろう、サポーターって何だろう、ということを考えている人にいちばん読んで欲しい。そこまでして応援する人々の「理由」が知りたい人にも。
・吉崎エイジーニョ『オレもサッカー「海外組」になるんだ!』(PARCO出版) 今回取り上げる本の中ではいちばんの新刊。 スポーツライターの吉崎エイジーニョ30歳は突然唯一の雑誌連載を打ち切られ、東京を脱出した著者が何もかも(家電も住まいさえも!)を投げ捨ててドイツの10部リーグでゴールを決めるべく奮闘する。『Number』での連載「突撃!エイジーニョ」の書籍化、というと知っている人も多いだろう。 デビューまでの苦悩、ゴールへの焦り、そしてこの物語を通してリアルに描き出される「30男がなりふりかまわず挑戦する姿」が、どこか滑稽でありながらも励まされる。仕事に疲れたときに読みたい本。
・ティム・パークス(著)/北代美和子(訳)『狂熱のシーズン―ヴェローナFCを追いかけて』(白水社) ヴェローナというと今ではキエーボ・ヴェローナのほうが有名だけど、もう一つのヴェローナFC(=エラス・ヴェローナ)もある。今ではキエーボはセリエB、エラスはセリエC1にまで落ちてしまったけど、この本で語られる00-01シーズンはセリエAで残留を争っていた。そんなシーズンのホーム?/アウェイ全試合をティフォージの荒くれども達と一緒に応援した1シーズンのルポルタージュ。本物の「ティフォージ」っていうのはこういうもんなんだ!と、彼らの破天荒で直情な生き様と生活を叩き込まれるような本。プロヴィンチャがトップリーグで苦闘する姿というのは、札幌(や、地方のクラブ)を応援している人が読んでみればどこかしら通じるものがあると思う。ジェットコースターのような悲喜こもごもの1シーズンには引き込まれてしまう。 それでは「考える」をテーマに選んだ「後編」こと残りの5冊は明日ということで。 「オレはこの本を読ませたい!という方も、トラックバックやコメントで是非。
希望の話をしよう――鈴木謙介「ウェブ社会の思想」
2007年06月11日
久しぶりに書評(っぽいもの)をしてみる。鈴木謙介「ウェブ社会の思想―〈遍在する私〉をどう生きるか」 ここでもさんざん語っているんだけど、著者の鈴木謙介氏というのは新進気鋭の社会学者で「文化系トークラジオ Life」というラジオのパーソナリティーを務めている人で、氏を知ったのもこのラジオから。社会学者なんだということを知って、著書「カーニヴァル化する社会」を読んだのがこの本を読むにいたった経緯、というところか。ちなみに仲俣暁生や津田大介、佐々木敦などのようにこのラジオではじめて知ったり、名前だけ知っていたけれどのちに深く知るようになった評論家や編集者、その書籍というのも多い。 さて、本の中身に戻ろう。 「ウェブ社会の思想」とタイトル(そしてイラストはASIAN KUNG-FU GENERATIONのCDジャケットなどを手がける中村祐介、という素晴らしいセンス!)が付けられているように、ウェブ社会(=情報化社会)によって人間の思想や生活はどう変わっていくのか?というようなテーマだと思ってまずは読んだ。 そしたら不覚にも、読んだあと泣きそうになってしまった。 社会学の本を読んで泣きそうになるなんて、はじめてのことだ。 この本は「ウェブ社会が何をもたらすのか」というテーマの本じゃない。 いまの社会の向こう側にある「希望」をひたすらに求め続ける本だ。僕らの未来にある「希望」を見出すための本。これはそういう本だ。そのために本書は現代の情報化社会の現状と未来、それらがもたらす人間への影響を深く論考している。ユビキタス、バーチャル、それらが招くネットワークの変化の波を抜けた向こうに見えるであろう「希望」が、この本のテーマだ。
そして社会学的にいうのならば、本書におけるメインテーマは「情報社会における『宿命』の前景化」ということだ。情報化社会によって蓄積された情報が、たとえばAmazonのレコメンドやiTunes Storeのように個人が動くと「情報そのもの」が勝手に先回りして現れるようになるということ、つまり「人が自分の人生に関する未来を選択すること、それが宿命のように、前もって決められていた事柄として受け取られる」(p17)ことで、人間は「自分が選んできた人生は、こういう結末しか有りようのなかったものなんだ。けれども、それでいいんだ」(p17)と自分を納得させることで「宿命」を受け入れながら生きていくということだ。しかし、どうしてその「宿命」は出現してしまったのか、閉じられた「宿命」の外に出る術はないのか。宿命を打ち破る「希望」はどこにあるのか、そうしたテーマについて社会学的問題を挙げながら述べていく、という本である。 著者はこの情報化社会での一つの大きな流れとして、まず「ユビキタス社会」を挙げる。現代および現代から向かう未来は個人に関するあらゆる情報が蓄積され、管理され、運用される社会であり、それは究極的には「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」コミュニケーションができる」という「ユビキタス社会」であると定義づけている。 しかし、この流れの中で人は本来その人本人が持っていた情報を「あちら側」に持っていかれたため、個人は「自己責任」と「判断性」が奪われてしまう。 そこで、そのふたつを補完するものが「宿命」という仕組みだ。上記のような社会というのは、つまりは「ある選択肢がシステムによってはじめからなかったことにされる=ある選択肢が開かれると同時に、別の可能性が選び得ないものになる」という現象が起きる社会である。当然ながら人間は一つだけしか示されていない選択肢を前にして「このまま進んでいいのだろうか」と悩むことになるだろう。それに対して「この選択肢でよかったんだ」後押しするのが「宿命」という考え方だ。「これは宿命だよ」と根拠がなくても後押しすれば、人はその選択肢の中に取り込まれる=「宿命」を受け入れる、「宿命の中で生きることを受け入れる」ことができる。 「宿命」はそこで最適に情報化されたデータを持って人の前に現れる。そして目の前にいる人に対してこう諭す。いまキミがいること、選ぼうとしていること、すべてが「宿命」であり、キミはその「宿命」を受け入れて生きていくほかないんだよ、と。そうやって人は「宿命」を受け入れる。そこは繭の中のように閉鎖的で、だけど安心できるような場所。何もしなくていい、これからは「宿命」が僕を運んでくれる――そんな幻想を「宿命」は僕らの前に見せてくる。 でも、その「宿命」をどうしても受け入れがたい場合、僕らはどうすべきなのだろう?どこへ向かって、何を探せばよいのだろう?「宿命を受け入れる」ということは、是なのか非なのか? そういったことを非常にシンボリックに書いているマンガを著者は挙げていて、それが古谷実の「ヒミズ」と「シガテラ」だ。「ヒミズ」は「自分は特別だと思っていたのに、特別ではないという『宿命』に悩まされ、自死という方法で宿命から逃れようとする」話だが、「シガテラ」は「自分にかかわる人間はみんな不幸になるという『宿命』の外へ飛び出そうとし、その結果として『オマケ』の人生を穏やかに暮らすことになる」といった対極にある話だ。また、西尾維新の小説「戯言シリーズ」(特にその最終盤)では、その小説の中で「『宿命』を受け入れることを断念することを『断念する』」ということによって、「宿命」の外へと生きていくことを決断する。 つまり、「宿命」から外に行くことはできるのだ。「断念を断念する」という手法を使って。だけど、「宿命」の外に何があるかは語られない。それは個人によって異なるからだ。「セカイ」を断ち切って「宿命」の外へ出るには、まず「宿命化されている」と自分の感じているような関係そのものをとらえ直し、自分が変わらなければ何も変わることがないからだ。その方法もまた、皮肉にも社会が盛んに言い立てる「自己責任」で見つけるよりほかないのだ。 では、宿命化する社会をとりあえず僕らはどのように生きていけばいいのか?僕らは「宿命」という決められた選択肢の中で生きているにもかかわらず、社会はそこから「オンリーワンになれ」「成長し続けろ」と、矛盾した言葉を絶えず言い続ける。耳をふさいで、そんなのできない、と叫べば社会は甘い言葉で「キミはもともと特別なオンリーワン」なのだと囁くだろう。そうやって僕らは「宿命」に押し込められていく。この状況を解決するにはただ一つ。「宿命的に自分は特別なのだ」と無理に思いこむこと、根拠なき断定を力強く行うこと。そんな無茶な方法で生産したモチベーション(著者の定義する「カーニヴァル」という現象)だけを頼りにその日を生きていくこと、それしかない。そうやってこの「宿命」から逃れるために考えて、いつか飛び越えた先にワーキングプアとか下流とかそんなものは別次元にある「希望」が見えてくるのだ。 現実を破らなければ希望も未来も見えてこない。僕らを取り巻く社会は、ユビキタスとバーチャルで得たデータベースを武器にして、まるで牧羊犬が羊の群れを追い込むように「宿命」の中に僕らを囲い込もうとしている。そうして囲っておいて「キミはもともと特別なオンリーワン」だと教え込んでいこうとしている。でもちょっと待って欲しい。選択肢は一つじゃない。ひょっとしたらそれは「宿命」でないかもしれない。そう思った人は、自分が思う「希望」への道が見えているはずだ。この小さな「セカイ」と飛び抜けた向こうにある、と。 だから、これが運命だとか、決まったことだとか、言わないで欲しい。昔見ていた「希望」は、すすけていても汚れを取り戻せばまた輝いて見える。いまの状況を観察してみよう。そうして、この時代にある「希望」を探してみよう。宿命の外に出たからと、孤独をおそれず、孤立をおそれず、ただ自分が見定めて信じる「希望」に向かえ。それが窮屈な情報社会の破り方だ。 ※参考文献とか「文化系トークラジオ Life」 イラスト・中村祐介氏のHP「檸檬通り」
鈴木謙介「カーニヴァル化する社会」
古谷実「ヒミズ」
古谷実「シガテラ」
西尾維新「ネコソギラジカル(下)青色サヴァンと戯言遣い」
恥を知れ!しかるのち死ね!――極私的書評『夜は短し歩けよ乙女』
2007年02月20日
森見登美彦『夜は短し歩けよ乙女』 本屋でその装丁に惹かれて買っていこうかなと思っていたらとんでもない人気らしくたちまち消えてしまっていて、重版になってやっと並べられた「夜は短し歩けよ乙女」をようやく買い求めることができた。 そんで一気に読み終わって一言目の感想。なんてキュート! 間違えば完璧にストーカーとして引っ立てられるであろう(いや、すでにそうかもしれない)主人公の「先輩」が、片思いの彼女の気を引くべく、なるべくできるだけ多く彼女の目にとまろうとすべく京都の町を駆け回る。夜の木屋町から先斗町で、夏の盛りの下鴨神社で開かれる古本市で、晩秋も深い学園祭の大学構内で、風邪の風吹く真冬の高野川で、北白川で、今出川通で、四条河原町で。主人公が追いかけるのは黒髪でひよこ豆のような後輩の彼女。けれども主人公とちょっと天然っぽい彼女はすれ違うばかりで……という、四季それぞれの京都を舞台とした連作小説。果たしてこの本をどのようにジャンル分けすべきか。作者がデビューしたジャンルであるファンタジーか。すれ違いの平行線を歩み続けるボーイミーツガールの恋愛小説か。どうにもこうにも分けられることができないが、なんとしても面白いことだけは確かである。
たとえば第四章「魔風邪恋風邪」で、主人公は彼女と自分のことをこう思う。 「冷たい雨の中を駆ける一匹の濡れ鼠がある。それはもちろん私のことだ。私は晴天の下へ出ようとしている。だが目前に見えているその晴天は、まるで夏の陽炎のごとく逃げ去り続ける。その陽光の中に立つのは、我が意中の黒髪の乙女だ。彼女のまわりは温かく、静謐であり、神様の好意に満ち足りて、たぶん良い匂いがする。それに引き替え、我が身はどうだ。私のまわりは神様の好意どころか若気の至りに充ち満ちて、この身を濡らすのはぶきっちょに奮闘する己を嘆く涙、吹きすさぶのは恋風の嵐である。」(P225) ああ、なんと報われそうもない片思い!なんと不器用な片思い! そんなトホホな「先輩」は彼女への思い焦がれて輾転反側、まずは恋愛的外堀を埋めるべく行動を開始するも思いっきり埋めすぎるか見当違いの墓穴を掘るばかり。その間違った方向に全力疾走する「先輩」の思いに彼女は微塵も気づくことなく「あら、奇遇ですねえ!」と受け流し、彼女は彼女で自分の思った道をずんずんと進んでいく。それを慌てて追いかける「先輩」の道すがら現れるのは、これまた奇妙なサブキャラクター。自称天狗の先輩「樋口」。奇妙奇天烈な高利貸し「李白」。主人公よろしく片思いの塊を間違った方向にフルスイングしている「パンツ総番長」。個性という枠にはとどまらないどころかはみ出して枠が見えなくなってしまうくらいのキャラクターだし、ストーリー展開もこれまた奇妙奇天烈きわまりない。 夜の先斗町で李白と彼女が借金をかけて「偽電気ブラン」なるものの飲み比べ対決をする表題作、古本市で自分だけの一冊を追い求めて主人公諸々が駆けずり回る「深海魚たち」、カオス極まる学園祭に忽然として登場する「韋駄天コタツ」とゲリラ演劇「偏屈王」に巻き込まれる(いや、進んで巻き込まれているような気がしないでもない)二人を描いた「御都合主義者かく語りき」、風邪のウイルス吹きすさぶ真冬の京都を彼女がお見舞いに渡り歩く「魔風邪恋風邪」。どれをとっても不思議な物語なのに、どれもがすとんとエンディングに落ちていくストーリーテリングはすばらしいものがある。 とりわけここで挙げたいのは、主人公「先輩」が彼女への恋の病に取り憑かれて思い煩う心理描写。四畳半の古びた下宿で答えのでない問いを延々と繰り返し、脳内会議を開催し、正攻法で歩めないばかりに外堀だけをやたらと埋めようとして、至る結論は 「恥を知れ!しかるのち死ね!」(P138) の境地。おそらく「好きだ」と言ったり言われたりしようものならメルトダウン必至の主人公がもたらす妄想と行動はどこまでも「非モテ男」のそれである。モテないことに忸怩たる思いを抱える男子が何とかして彼女を作りたい、好きな女の子に思いを伝えたい、と空回りしてオーバーヒートの末に「モテ男」への偏見と自己嫌悪にまみれて「非モテ」をよりいっそうこじらせる主人公。読めば読むだけ思い出す過去が恥ずかしく、照れくさく、馬鹿らしく、体くねらせて頭抱えてしまう男子が続出することだろう。そんな視点から本書を定義するのなら、「非モテ男子と不思議ちゃん女子のすれ違いエンタテインメント」って言う具合になるのだろうが、そんな定義などモロッコに吹きすさぶ砂塵のように無意味だ。それほどに面白い。 一歩進んで本書を手にとってはじめの数ページかを読んでしまえば、虜になること請け合いである。そして読み終わったときにはお願いせずにはいられない。 願わくば「先輩」と彼女の幸せが永く続きますように!なむなむ!
ななめ上から見上げるフットボール――小田島隆「サッカーの上の雲」
2007年02月06日
サッカーの上の雲―オダジマタカシサッカ~コラム大全 司馬遼太郎の本ではありませんよ(挨拶)。 小田島隆という人は生粋のサッカー畑ではなくていろんなコラムを書いている人なんだけど、この人がサッカーを語るとこんなに面白いのかと爆笑しながら読んでました。 だって2つめのコラムのタイトルがいきなり 「伸二の食生活が心配だ!」 ですよ。 小田島氏は浦和サポなので当然浦和系の話が多いんだけど、その合間に挟まれるいろんな選手のことを主に妄想をネタにして書いてます。たとえば伊東輝悦が年に一度見せるか見せないかの長距離ドリブル(ただし20メートルくらい)の美しさとか、服部年宏のニヤつき具合とか、大熊清の大声とか。そういう「ななめ上からだけ見えるフットボール」について語っていて、読んでいると思わずニヤニヤしてしまう。かしこまった「〇〇戦記」とか、プロのスポーツライターの書いたルポなんかもじっくりと読むのもいいけど、小田島氏でしか書けないであろうこのコラムも一読の価値あり。 (どうでもいいが、「伊東輝悦」も「服部年宏」も一発で変換できた。すごいぞATOK!)
考えてみればこういう「妄想系」って、友人とサッカー系バカ話をしてるときの感覚によく似てる。飲み会とかアウェーの帰りとか、そういう時にしたことありませんか、バカ話。旬なところでいえば札幌のキャンプ、こないだのオフに曽田選手が熊本城に行ったなんて記事がありましたけど、 「熊本城って籠城戦向きの城だよな」 「籠城戦のために銀杏とか植えてあったらしいぞ」 「銀杏くさいDFはイヤだよね」 「あと仁丹くさいDFもキツイよね」 「水戸の選手が全員納豆くさいとかな」 「でも熊本城って落とされなかったんでしょ?」 「そうだけど、結局原因不明の失火で焼けたんだよね」 「オウンゴールかよ」 「しかも曽田さんですよ」 「そうですか」 「そうですよ」 みたいな。 そういうことを延々と語り続けられるひとにおすすめです、この本。 けれど、もっとも読んでほしいのは最後にあるコラム「浦和をビッグクラブと呼ぶ日」である。『Number」667号「超浦和主義。」』に掲載されたコラムだけど、浦和一色のこの特集の中にあって小田島氏のこのコラムだけは異彩を放っていた。小田島氏だけが書けるであろう、ちょっとひねくれた愛情とひたむきな狂気(もちろん、いい意味での「狂気」だ)が彼の過去のエピソードと一緒に語られている。ベストエンドを目前に控えたチームを見続けてきたプライドと、一足早い歓喜と、それをクールさで押しとどめようとする理性のぶつかり合い。頭の中が混沌として「どうすんのよ、オレ」みたいになっちゃう、そんな気持ちが手に取るようにわかってニヤニヤしながらしみじみしてしまう。 このコラムだけは、何よりもオススメです。 最後に、小田島隆氏著作のおすすめをもうふたつほど。 「イン・ヒズ・オウン・サイト-ネット巌窟王の電脳日記ワールド」 「テレビ標本箱」 いずれもサッカー関係ではないコラム集ですが、お手にとってみては。
プロフィール
生まれ:1978年旭川市生まれ。 育ち:道内あちこち。その後横浜、川崎を経て再び札幌。 観戦暦:1996年・対日本電装戦が初応援。翌年より道外への進学に伴いアウェー中心に応援、1998年よりアウェイコールリーダーとなる。2003年春に札幌へUターンし、現在ホームゴール裏で応援中。 サッカー以外の趣味:音楽と活字。
最新のエントリー
コメント
検索