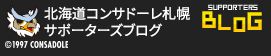天国のフットボール
2007年07月10日
6月からこのかた体調を崩しっぱなしで、5月末に引いた風邪が扁桃腺に巣を張って喉の痛みで水も飲めないくらいの日々が何日か続いた。ラジオに出る予定があったので(三角山放送局のあの番組です)抗生物質で何とかして1時間の生放送を乗り切ったら痛みが再発してまた別の抗生物質を飲むことになってしまい、それを治すのに6月をまるまる使ってしまった。で、7月に入ってからの自分はだるさやら微熱やら頭痛やらといった不定愁訴に悩まされている。これは毎年のこと。 自分は7月生まれなんだけど、小さいときから誕生日近辺にかならず体調を崩していた。逆に誕生日前後は絶好調というひとも見かけることがあって、自分の「誕生日前後は調子悪い説」がこの歳になっても続いているのはそういう星回りだからなんだろうとあきらめている。誕生日を存分に楽しめないのは少し寂しいけど、それでもフットボールを見ている時だけはなんとか気を紛らわすことができた。
以前に「死んだら灰は厚別か宮の沢に撒いて欲しい」と書いた。 やっぱりあの地は自分にとってはそれほどの思いを持った故郷、っていうか「自分が生きていることを実感した場所」だよなあと思う。18歳のあの頃、フットボールがそばになかったらと思うと本当に恐ろしい気持ちになる。笑い話ではない。当時の自分は切実に何かと深く関わることを必要としていたし、熱狂をぶち撒ける場所を必要としていたし、学校社会ではなくもっと開かれた場所を必要としていた。そういう鬱屈した何もかもなんて思春期特有のアレだと言ってしまえば元も子もないのだけれど。そしてあのときにフットボールに出会えたことを感謝しているし、ずっと感謝し続けるのだろう。他のスポーツではなく、フットボールであったことにも。 フットボールは、攻めることがはっきりとわかりやすいスポーツだ。そして、攻めることの多様性については何よりもずば抜けているスポーツでもあると思う(もちろん、すべてのスポーツは「攻めて」「勝つ」ために存在するのだけど)。速攻、遅攻、セットプレー、中央突破、サイドアタックに古いところではキック&ラッシュ、システム、フォーメーション、ありとあらゆる名前のつけられた戦術と、名前のつけようもないほどの膨大なプレーの数と、名前ではとうてい表すことなどできない「気持ち」というファクターが組み合わされてゴールが生まれる。すべてのゴールはありとあらゆる事象の詰まったひとつの奇跡で、自分とみんなは試合のたびになにがしかの奇跡を眼にしていることになる。テレビが片手間に流す三流のマジックショーにかじりつくより、スタジアムで美しくて泥臭くもあるゴールと、そこに至る軌跡を見る方がよっぽどいい。そしてそのために声を嗄らすほうが、人生においてずっと幸せだと、そう思っている。そういったシンプルな「攻める」ことを眼に見ること、それをまっすぐに目指して声を出して後押しすることはあの混乱の時期にあった自分にとってはなによりも重要だった。ごちゃごちゃに絡まった自意識を解きほぐしてくれたのは紛れもなくフットボールだった。そんなことがあったからあの場所に遺灰を撒いてくれと、そう思っている。それくらいの感謝と畏敬を持っている。 だけど最近の調子が悪い僕はこうも考えるのだ。 そんなにフットボールを人生になぞらえて考えるのは、生きることとシンクロさせて考えるのは、死を直視したくないからじゃないだろうかって。死んだあと、天国にフットボールが存在するのかというのは知らない。死んだ人が生き返って教えてくれるわけでもない。日常生活は想像できても、フットボールなんてあるかどうか想像もつきそうにないからこそ熱狂しているのじゃないだろうかと考えるもうひとりの自分がいる。うーん、自分で思うよりよっぽど自分は生に執着しているんだろうな。でもまあ、死んだ後の楽しみが増えるのか。天国のフットボールが存在するのかどうか、っていう疑問を解決する楽しみが。 とりあえずここにあることはぜんぶリアルで、生きているからこそ見られたり味わえたりするものごとであるということは知っている。自分は生きる意欲に溢れてキラキラしているような性格はしていないけれど、それなりに人生は悲しくも面白いと思っているのだ。自分のまわりにめぐらされているリアルとどうつきあうのかということと、自分の手でリアルを変えていくことの楽しみを。
私的な戯言――雪道の歩き方
2007年04月30日
バスからゆっくりと降りた老婆が杖を突いて歩き出す。 その杖の先は金属で尖っていた。すこしでも冬道に滑らず歩けるよう、杖の先に錐状の金具を取り付けている。 こういった金具をここ何年かでよく目にするようになった。錐のようでなくても、スパイクのようなものを取り付けて歩いている人もいる。みんな、雪道に足をとられないようにしているのだ。そういえば僕の子供の頃も、滑り止めのついた靴を履いていた。靴底に折りたたみ式のスパイクがついていて、4つついてたら「4WD」なんて名前をつけて売られていた。当時の子供たちにとってはそんな冬靴が憧れだった。雪道でどんなに遊んでも滑らないことが誇らしかった。 あの頃より確実に雪は少なくなり、ある程度除雪のできている街に住んではいるが、湯道で滑ることは何十年たっても相変わらずだ。でこぼこに氷の張った歩道の上をおそるおそる進んでゆく。ずるっと滑りそうになるところで踏ん張って体を支え、次の一歩を踏み出す。こうして歩き続けていて、やっと冬道の歩き方にコツのようなものを見つけることができたのは最近のことだ。
まず一歩を踏み出すとき、どこに足をおいたらいいのかを考える。なるべく地面の露出しているところに一歩目を出すように気をつける。そして二歩目、三歩目となるべく踏みしめやすいような場所を選んで歩く。真っ平らに凍った道より、少しでもでこぼこができているほうがかえって歩きやすいのだ。誰かの歩いた後がそのまま凍っていたり、逆に一部分だけ盛り上がっていたり。氷ばかりが平面的に広がっているところではなくて、雪が上に乗っているところのほうが踏みしめやすい、とか。下を見てそういうところがないかどうか確認しながら、ひょいひょい……とまではいかないけど、歩いていく。そうして結構な回数の冬を過ごしてきて、やっと冬道の歩き方がわかってきた。 そういえば冬道を歩くのが下手だった時代は生きるのも下手だったんじゃないか、とも思う。東京で就職したけれども2年ぎりぎり保たずに辞めてしまって、実家に逃げるようにして帰ってきた数年前の3月、千歳空港に降り立ったときの冬の寒さと、堅く凍てついた道が歩きにくくてとても困ったことを覚えている。そして春までほとんど僕は外には出なかったし、雪かきをするのも嫌だった。雪と冬、というもの自体が嫌いだったと言っても良かったのかもしれない。雪の降らない東京から、いまだ雪深い札幌へ。なんだか自分自身が東京という土地に負けて北へ敗走してしまったような気がして、冬将軍に耐えきれず敗走したドイツ軍のような気がして、つまりは世間の負け犬になってしまったような気がして、滅入ったままただただ春を待っていたことを思い出す。 だからそのときは雪が解け、氷がゆるみ、道が乾く季節を何もできないまま待っていた。自分の足で歩くこと、雪や雨風に逆らって歩くことに自信も持てなかった。生きることを諦めてしまいそうになるほど部屋に閉じこもって、鮮やかな緑に彩られた道を誰かが用意してくれることだけをやみくもに信じているだけだった。だけど、そんな道などなかった。僕の前には途方もない荒野だけがあり、緑のあふれる場所にするためには僕自身の努力以外方法がないということにがっくりと気を落としていた。このまま雪に埋もれてしまいとさえ思っていた。 あれから何年かが過ぎて、僕はようやく冬道を平気に歩けるようになった。平気を通り越して、冬道を歩くことが好きになってきた。ただ平坦な道を歩き続けるだけではなく、でこぼこでつるつるな道の中でどこがいちばん歩きやすいかを探しながら一歩一歩を踏みしめていくことに楽しみを見いだすようにもなった。 それは僕の中で大きな変化だったんだろう、と思う。昔は冬道を歩き続けることなど苦行以外の何物でもないと思っていた自分自身の心が、それこそ春が来て雪解けが訪れるようにゆるんでいった。不器用な歩き方でも、それが楽しいのだと、それが僕の歩く道のりのひとつなのだという自覚も持つようになった。生き方は相変わらず不器用だけど、その「不器用である」ということそのものをやっと自分自身の中で受け入れて、それを楽しみに変化させて生活ができるようになった。平坦な道はつまらない。でこぼこしていて、滑りやすい、真っ暗な寒い夜の道のほうが、むしろ楽しい。そしてそういう道をたくさん歩けば歩くほど、緑あふれる遊歩道にもたどり着くことができる。歩かなければ先はないし、その先には新しい道があって、新しい道も、そのために今歩く道も、楽しいものなんだと考えられるようになった。未来は僕の手の中にあるのではなく、次の一歩にこそある。 生きていくことでも、実際に足を動かすこともどっちも同じ。 どんな道でも歩く(か走る)以外に方法なんてないし、抜け道や回り道をして楽に先へ行ってやろうということしか考えていない人間は、力が足りずに結局は道を走りきることができずに途中で脱落するものだ。地味にこつこつと歩いたり走ったりして、その足を止めないこと。どんなぬかるみでも、濁流でも、雪道であっても、前へ進むということを止めないこと。むしろそれを楽しむような気持ちになれたなら、まわりの誰かにどんな汚い言葉をかけられても、小突かれたりされようとも、歩き続けることができる。どれだけ歩くのが遅くても、水たまりを楽しそうによけて歩く子供のような心を持っていけばたどり着くところはきっとある。そう思えるからこそ、これからもこの冬道を楽しさをもって歩くことができるのだ……そう思って、僕は今日も靴を履いて玄関を出てゆく。 もう、桜の咲く季節である。札幌の街は、緑と花が一気に輝く季節である。 僕の歩く道にタンポポの一輪でも咲いていれば、それだけで十分、次の一歩を踏み出せる気持ちになるのだ。さあ、僕はもう一つのスタートを切るときだ。
フェジョアーダを煮込む。
2007年03月21日
「しまふく寮通信」を読んでフェジョアーダが食べたくなったので、作ってみた。 関東在住時代にCOPA TOKYOという店に連れて行ってもらって食べたのがはじめてのフェジョン。シュラスコ食べ放題のコースなのに、フェジョアーダばっかり食べていた記憶がある。 ちなみにこの「COPA TOKYO」というお店、Jリーグ各チームのブラジル人がこぞって集まる店としても有名。エントランスには選手のサインがびっしりと! そんなわけで作ってみる。 調べてみると地域によって使う豆が違うらしいけど、今回はブラジルでポピュラーな黒豆(黒いんげん豆=「フェジョン・ペレット」)で。 作り方については、こちらを参考にしました(簡易版のほう)。 そうそう、できればご飯も炊いておいてくださいね。
こちらが今回使った豆。 乾燥の黒豆はなかったので、輸入食材店(具体的に言うとESTAの地下です)で黒豆の水煮の缶詰を買ってきた。水煮とは言っても塩と砂糖である程度の味付けがされているらしい。 黒ばっかりだと色合いもアレなので、ひよこ豆の水煮(こっちは純粋に水煮)を加えました。どっちも400g(豆のみだと250gくらい)入りで250円~300円程度で売ってます。レンズ豆の水煮でも良さそうですね。
ここに、豆だけでなくベーコンとソーセージも加えます。 ベーコンは薄切りではなく、存在感のあるブロックがいいでしょう。 ソーセージは、ほんとうは「リンギッサ」と呼ばれる太い生ソーセージやチョリソーを使うそうなんだけど、リンギッサはないのでふつうのソーセージで代用。といっても、ほんとうはどんなのでもいいらしいけど。 それでは調理開始。 まずはニンニクを細かく刻み、オリーブオイルで香りが出るまで炒める。 そのあとみじん切りにしたタマネギを加え、透き通るまで炒める。 バターだけでもいいらしいけど、今回は水煮缶の缶詰臭さ(個人的に缶詰特有のあの匂いが苦手)が出ることを考慮してニンニク+オリーブオイルで臭みを消すように考えました。 そのあとで水煮缶を投入。黒豆は味がついていたので汁ごと、ひよこ豆は煮汁を捨てて。ここで黒豆缶の味見をしてみたのですが、「ほんのり甘くてちょっとしょっぱいおせちの黒豆」といったような感じでした。ぐつぐついってきたところでまた味見。もうちょっと塩っ気があってもいいかなあ、でも塩だけじゃちょっとなあ、と思ってコンソメキューブを投入。 その一方、ベーコンとソーセージは果たして。 ベーコンは1センチ角か、もうちょっと大きめにカットしてベーコンの存在がわかるようにする。ソーセージもベーコンと同じくらいの大きさに。 豆を煮ている脇でフライパンを熱して、まずはベーコンを弱火でじっくり炒めてうまみと香りを引き出します。ソーセージは焼き色をつける程度でいいかな。 そしてぐつぐつと煮えている豆のところにベーコンとソーセージを投入。
ここで水加減と味を整える。 仕上がりは豆がふっくらした感じになるように中火で、蓋をしないで(←ここ重要)煮ていくのでそれを考えた水加減と塩加減にします。煮詰まってしまうとしょっぱくなってしまうので、塩加減には注意! あとは(あれば)月桂樹の葉を入れて、そのまま中火で煮ていきます。ときどき鍋をかき回しながら30分程度でしょうか。 煮ている間にこぼれ話を。 このブラジルの郷土料理「フェジョン」「フェジョアーダ」は、もともと南米の農園で働いていた黒人奴隷が、農園主からもらった肉の切れ端や耳、内臓の部分などを豆と煮込んで食べたものがルーツだそうです。また、「しまふく寮通信」の文中にもあるように、フェジョンは各家庭ごとに味が異なります。つまりは「おふくろの味」ってやつですね。イタリアで言えばマンマのパスタ、日本で言えば千昌夫が「おふくろの味」で歌う「母ちゃんの味噌汁」みたいなものですね。別に千昌夫じゃなくてもいいけど。ちなみにうちの実家では、味噌は地元東神楽町特産の手作り味噌、「食べてみそ」を使ってます。具はジャガイモが好みです。 ここら辺で味見をしましょう。あとまめにかき回さないと鍋底が焦げるので注意。 もう少し時間があるのでフェジョンとコンサにまつわるこぼれ話を。 ブラジル留学や、ブラジル人選手のすすめでフェジョンが好きになった日本人選手は数多くいます。札幌に在籍していた選手にも、フェジョンを毎日にように食べるという選手がいました。現在イタリアでコーチ修行をしている元札幌DF・村田達哉氏がその人です。彼は読売時代からフェジョンが好きだったそうなんですが、札幌に移籍してきてからも同時期に加入したペレイラ氏の奥さんがつくるフェジョンを分けてもらい、冷凍しておいたのを温め直して毎日のように食べていたそうです。うーん、おそるべしフェジョンの魔性。 さてそろそろ煮上がったころでしょうか。黒豆がほっこり、スープにとろみがついたころがベスト。味見をして、最後に塩黒こしょうで味を整えて完成。炊きあがったほかほかのご飯にかけて食べましょう。本場ブラジルでは米以外にも「ファリーニャ」と呼ばれるキャッサバの粉を煎って味付けしたものや、青菜の塩炒めを付け合わせにするのですがそれはそれぞれできる範囲でということで。 さて、こちらもできあがったあつあつのフェジョアーダをひとくち。 うん、黒豆がふっくらしていてほんのり甘く、塩加減もちょうどいい! ベーコンとソーセージのそれぞれの脂がスープに行き渡っていて深みがあるし、ひよこ豆も黒豆とは違ったアクセントをつけている!生まれて初めてフェジョアーダを作ったにしてはかなり上出来です。ごはんと一緒に食べるとこれまたおいしい。もちろんパンでも大丈夫そう。カリッとトーストしたパンにのせて食べるのもいいかもしれません。フェジョンそのものも、味付けやソーセージなどの肉類は調整できるので少なめでも大丈夫でしょう。 さて、ここまで読んで「おいしそうだけど料理苦手だし・・・」という方々もいらっしゃることでしょう。そんなときは通販で手に入れることもできます。 「Latin yamato」というHPでは、リンギッサや乾燥豆などのほかに、レトルトのフェジョン/フェジョアーダも販売を行っています。 ブラジル人のソウルフードであり、スタミナ源でもある「フェジョン」「フェジョアーダ」。ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。
僕らは失う機会すら与えられなかった-(その2)
2007年02月22日
昨日の話の続き。なんだか朝日批判チックになってきていて本筋とは逸れてしまいそうな勢いですが。 昨日の話では自分もそのど真ん中に所属しているとされる「失われた世代」のことを朝日新聞が特集して点で、「誰が」「どのように」「何を」失ったのかという焦点がぼやけたまま、間違った方向で印象を与えてしまっているということを書いた。 で、この特集にはもうひとつ欠けている点がある。それは「格差社会」という観点だ。 格差があるのはどの国も街も一緒だ。だけどその格差があまりにも広がりすぎていて、富がごくわずかの層に大きく集中しすぎているのが今の日本。だってそうでしょう?企業は大きくその利益を伸ばしているけど、一般社員ですらその恩恵にはあずかれない。企業側が「バブルとその崩壊の時代」の経験をトラウマにしているせいなのか分からないけど、富の再分配は行われていない。そういう全社会的な「格差」を含んで考えなければ、「失われた世代」へのアプローチはうまくいかないのではないか。
そんな風に考えているときに、2月18日の社説にこういう記事が載っていた。 '「格差是正 失われた世代に支援を」 (前略) 格差そのものは、どの時代にもある。努力を怠った結果であるなら、自己責任を問われても仕方がない。そのうえで生活保護など最後の安全網を整えるのが政府の仕事となる。 では、政治が最優先で取り組むべき格差問題は何か。正社員と非正規の働き手との間に横たわる賃金や契約期間など処遇での差別こそが焦点だ。正社員なら若い時期から会社の負担で能力を高められる。得意技や専門知識が身につけば、転職しての再チャレンジも難しくない。一方の非正規雇用は最初から不利な立場に置かれる。 私たちの社会には、こうしたハンディを理不尽な形で負わされた仲間がいる。就職氷河期といわれた90年代に就職活動をした25歳から35歳ぐらいの層だ。「ロストジェネレーション(失われた世代)」ともいわれる。 バブル崩壊による不況のなか、企業はリストラを急いだ。過剰な設備や借り入れだけでなく、社員の採用も削り込んだ。本来なら若手社員に任す仕事を派遣や業務請負などが埋めた。身軽になり、競争力を取り戻した企業は、いま高収益を享受している。だが、就職にあぶれた人々は取り残された。 経済協力開発機構(OECD)の対日審査報告書は「格差拡大の主な要因は労働市場における二極化の拡大にある」とし、その固定化に強い懸念を表明した。問題は本人だけにとどまらない。消費の落ち込みや、社会保障の担い手の不足、中堅や熟練労働者の減少など、社会に様々なひずみを生む。 神戸の大手アパレル、ワールドはパート約6千人のうち5千人ほどを正社員に登用した。年22億円のコスト増だが、「一生の仕事として取り組む人材を確保する」という将来をにらんだ戦略だ。 こうした企業を増やし、低賃金の非正規雇用にあぐらをかく経営者に転換を迫ることで、失われた世代を支える仕組みを社会全体で考えたい。(後略)' 果たして、この社会は個人が生み出してしまったものなのだろうか?「バブル以後の不況に耐えきれなかった世代」が生んでしまった鬼子なのだろうか?この文章を読む限り、すべてとは言わないけれど責任の多くは個人にある、とでも言いたげだ。そして「私たちの社会には、こうしたハンディを理不尽な形で負わされた仲間がいる」と呼びかける文章へと繋いでいる。 仲間? 俺たちはいつから朝日新聞の仲間になったんだ?誰があんたたちの仲間にして欲しいと頼んだ?そもそもフリーター世代にとって「仲間」っていう言葉は、自分たちにとっては嫌いな方に入っている言葉だだろう。新聞で呼びかけられる薄っぺらい「仲間」という名前の御都合主義な連帯よりも、あんたらが薄っぺらだと決めつけている自分探しで見つけた「仲間」の方がよっぽど大事だ。それを自分から大声で叫ばなければ、本当の意味での「格差是正」にはならない。 自分は「失われた世代」の一員として、何を失ってきたか、そしてこれから何を手に入れられるのかを考えたい。未来は無限ではない。無限とはほど遠い、数えるくらいの「有限」の中から考え抜いて選んで、それをメシの種にして乗り切っていくしかない。それが今の時代の現実。そうやって思っていくと、自分が失ったのは「未来」という名の希望であり、選択肢であり、場所である。所得階層を自分の力で勝ち取る自由すらも失ったと言っても過言ではないと思っている。そして失ったのは、自らの過失ではない。もっと言うなら、自分は「失う」ということの社会的体験、失うことの悲しみや挫折感や悔しさすらも感じることさえ奪われてしまったのではないか。学生時代には失ったものはある。それは人間関係であり、志望校への入学だったり。だけど社会に出て仕事に就くようになったとき、すでに失うべきであったものは失われ尽くされていた。これ以上失うことを会社は許さず、わずかに採用された新人には荷が重い仕事だったような気がする。たぶんそんな一時期を乗り切る力があったとしたら、今頃はかなり会社人間(いい意味で)として成長できていたんじゃないかと思うこともあるけど、それはもうどうしようもない話。気がついたときには「失うこと」すらすでに失っていた「失われた世代」は、このままよくてワーキングプア、ともすればホームレス寸前のワンコールワーカーみたいになってしまうのだろうか。これ以上失うものがない自分から、社会は何を奪おうとするんだろう? どこにも答えを見いだせなくて暗闇を這いずり回る感覚の下に、この項、了。 ※参考資料 朝日新聞2/18付社説「格差是正 失われた世代に支援を」 官邸による「成長力底上げ戦略」(PDF) 官邸による「成長力底上げ戦略」の主な論点(PDF)
僕らは失う機会すら与えられなかった-(その1)
2007年02月21日
ちょっと昔の話になるけど、朝日新聞が元旦から「ロスト・ジェネレーション」という特集を組んでいて、その新聞記事があまりにもお粗末で矮小化されたものだったので社会学系ブログなんかで思いっきり炎上して、それから「ロスト・ジェネレーションってなんなんだ?」という話題が出てきたことがあった。その話題は今となってはすっかり鎮火しているに等しいのだけど、ここでちょっとぶり返してみたい。個人的にまとめたい(でもって憤りたい)だけなんだけど。 そもそも、「ロスト・ジェネレーション」という言葉は何を意味しているのかというところからはじめたい。この言葉が出てきたのはヘミングウェイやフィッツジェラルドといった小説家の生まれた世代、1920年代から30年代という二つの世界大戦のちょうど「戦争の風穴」のような時期に青年時代を過ごし、その後の第二次大戦のにより文化的、情緒的に異質なものをもたらした人々を指す言葉だ(かなり要約)。 それをふまえた上でまず朝日新聞の第1回のリード文を読んでみると、そもそも定義からしてかなりいびつにされている。 今、25歳から35歳にあたる約2千万人は、日本がもっとも豊かな時代に生まれた。そして社会に出た時、戦後最長の経済停滞期だった。「第2の敗戦」と呼ばれたバブル崩壊を少年期に迎え、「失われた10年」に大人になった若者たち。「ロスト・ジェネレーション」。第1次大戦後に青年期を迎え、既存の価値観を拒否した世代の呼び名に倣って、彼らをこう呼びたい。(1月1日)
呼ばれたくもねぇよと毒づいてからちょっと膝詰めで小一時間問い詰めたい感じがするのだが、そこはぐっとこらえて。 今25歳から35歳に当たるということはだいたい1970~80年くらいに生まれた人々のことなんだけど、確かにその時代というのはバブル崩壊前後に就職を迎えた世代である。バブル期には大幅な売り手市場であった企業の正社員枠は0に近くなり、派遣社員や契約社員、アルバイトといった非正規雇用に就くか悪質商法、ニートにならざるを得ない人々が続出していた時代でもある。また、学校を卒業しても就職できるアテもないし技能もない、ということで専門学校への入学者が激増した時代でもある。 では、その時代のあと、彼ら(彼女ら)はどうなったのか?正規社員として、正規な労働契約の下に、完全とはいえないまでもそこそこ満たされた労働環境の中で働けているのか? 答えは否である。完全に。 非常に残念なことに、この国の社会構造は正社員になれなかったフリーターやニートを救済する構造は持ち合わせていない。フリーターはフリーターのまま、悲惨な生活状況のまま死ななければならないのがこの国だ。そうした就職氷河期の時代を経ての現在、再び雇用状況は改善し、新卒求人も増えてはいるが中途採用などは今でも数は少なく、フリーターから正社員など望むべくもない。そういう労働的な観点から見たなかで、どん底に落とし込まれて、雇用主のいる層からは見ないフリをされているのがこの世代なのである。 ……というようなことを、いささかあるいはかなりの偏光メガネ具合で「下流」の人間ばかりをどうにも収まりの悪い形で特集したのがこの特集。 で、朝日新聞の記事のどこが問題なのかというと、こういった世代を例える表現である。「失われた世代」というのは、いったい「誰が」「何を」失った十年だったのか、ということが全く明示しないまま、ただもともとの「ロスト・ジェネレーション」を矮小な取材記事に貶めてしまったことだ。 自分は今年29歳。この「失われた世代」で定義するところのど真ん中の世代だ。その時代に生きている自分にとって、「誰が」というのは答えが出る。それは「私たち」以外の何者でもない。自分たちの前には高度成長期から途切れることなく続いてきた道があり、後の世代にはITを取り込んで復活した企業が道を作ろうとしていた。でもその合間の部分は断絶して、これからも独力で登り上がることなどできないただ落ちるだけの道がある。で、その断絶の崖の底でひとり上を見上げながら、思うのだ。「俺たちが何かを失ったように言ってるけど、本当は『社会が俺たちから何かを奪い取った』んだろ!」そう怒鳴ってみると、返ってきたのは抑揚のない役人声。「そんなこと今更言ったって、その昔、自分探しがしたいと後先考えずに飛び出していったのはキミたちじゃないか」「後先考えなかった訳じゃない!あの時の社会のことなんて、考えても意味がなかったに決まっているだろう!それでやっぱり頑張らなくちゃって思って帰ってきたら役立たず扱いで知らんぷりかよ!」 そして、同特集1月3日のリード文。 「失われた十年」の間に正社員としての道が閉ざされ、社会からはじき出されてしまった若者たちは今、どんな日々を送っているのか。ロスト・ジェネレーションが仕事、そして自分自身と向き合っている現場を、同世代の記者が訪ねた。 正社員でなければ人間ではないとでも言いたげな、この文。「社会からはじき出された」ときっちり文章にして、フリーターや契約社員は「余計者」であるかというようなこの文。コレが日本を代表にする大企業に勤める正社員こそ「人間」と、自らの立つ労働社会の構造問題とあやうさを慮ることもなく、労働的に下層に位置する人間を「自分探し」などと揶揄して、まるで根無し草のように扱っている。それにも我慢がならないのだ。「自分探し」という言葉に乗っかった人たちは、少なからず感じているのだ。いくら世界を巡って「自分探し」をしようが、自分にとって大切な者はその程度じゃ見つからない、ということを。そう考えることで、この特集で朝日新聞側がこの特集を組んだ意図というか、「失われた十年」をどう思っているのかがわかる。つまり、「失われた十年」とは「一定の世代に育って社会に出た人間がバブルの苦境に負けて自分探しに走り、結果フリーターやニートが増えた十年」と目線を下に置いた(もっと悪い言葉で言えば「嘗めた」)ところから「ほらほらこの人はこんなに下賤な生活なんですよ、気をつけましょうね」という意味でまとめたのがこの記事である。ふざけんな! で、コレに続く話をこないだ2月18日の社説で見つけたのが、その話は次エントリに。 ※参考資料 文化系トークラジオ Life:「失われた10年~Lost Generation?」 「Life」にサブパーソナリティとして出演されている仲俣暁生氏のブログより、今回の問題について言及されているエントリ。 「ロスト・ジェネレーション」について ふたたび「ロスト・ジェネレーション」について こちらで記事の抜粋と筆者コメントが読めます。 別所二郎のジタバタ漂流日記
プロフィール
生まれ:1978年旭川市生まれ。 育ち:道内あちこち。その後横浜、川崎を経て再び札幌。 観戦暦:1996年・対日本電装戦が初応援。翌年より道外への進学に伴いアウェー中心に応援、1998年よりアウェイコールリーダーとなる。2003年春に札幌へUターンし、現在ホームゴール裏で応援中。 サッカー以外の趣味:音楽と活字。
最新のエントリー
コメント
検索