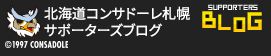極私的スガシカオ論――カタルシスのないパレード
2007年02月04日
スガシカオ-ALL SINGLES BEST 別冊カドカワ(総力特集)スガシカオ スガシカオを初めて聴いたのはたしか19才の夏。父親の運転する車に乗っているとき、ラジオ(たぶんノースウェーブだ)から流れてきた「ヒットチャートをかけぬけろ」だった。その頃の僕はとりたてて現状に問題のない大学一年生で、のんびりと帰省を楽しんでいるところだった。気にしていたことと言えば彼女がいないこととぼんやりした将来への不安ぐらいだった。そんなユルい空気の中で聴いた、何かいじけたような歌詞の乗ったメロディーを、乾いたようなざらついたようなギターとボーカルが歌うその曲は、なぜだかどうしようもなく僕を焦燥に駆り立てた。そして僕はすぐさまレンタル屋に行き、デビューアルバム「Clover」を借りてきて聴き込んだ。スガシカオの歌と向き合うようになったのは、ここからだ。でも19才でなんて、今にして思うとなんてスガシカオ的なんだ(「19才」という名曲がある)。
「Clover」を初めて通して聴くと、今まで僕が聴いてきたものとは全く異質で、でもどうしようもなく心をかき立てられる彼の音楽に吸い込まれていった。高校時代テクノばかり聴いていた僕は現実問題として彼女をつくるよりも早く、スガシカオの音楽に取り込まれてしまった。「ドキドキしちゃう」で心のリズムを乗せられ、「イジメテミタイ」でじらされて、「黄金の月」で泣かされた。ちなみに「黄金の月」はそのあともいろいろあって自分にとってはとても大事な曲になって、一時期スガシカオ楽曲で最多の再生回数を誇ったあと大事になり過ぎてほとんど聴かない(聴けない)曲にまでなってしまった。 そんな僕の情熱さめやらぬ「Clover」を聴き込んだすぐ後にアルバム「FAMILY」がリリースされたとき、当然ながら僕は飛びついた。それからアルバムとシングルを繰り返し繰り返し聴き続けながら僕は年をとり、スガシカオは相変わらずざらついたクールな声とうねるようなファンクをベースにしたリズムで歌い続けてくれていた。その彼の10周年を記念した「ALL SIGLES BEST」が発売されたときも僕は当然のように買い求めた。毎日会社に行くときにスポーツ新聞を買い求めるサラリーマンのような感覚で手に入れて、でもスポーツ新聞にはないはやる気持ちを抑えながらiPodに転送して、イヤホンを耳につっこんで、再生。最新シングルの「午後のパレード」からリリースを遡るようにして収録されている曲を聴きながら、スガシカオがこうまでして僕(と僕ら)を虜にしてしまうのか、と自己嫌悪みたいな気持ちになった。 スガシカオの歌詞は身の回りの物事についての痛みと弱さをえぐり出して見せている。それはたとえば「夜明けまえ」のような日常に潜む空虚さであり、「ストーリー」のようなあやうい世界に立っているギリギリさであり、時には「あまい果実」のような内蔵が裏返しになってしまうような愛情表現だったりする。そしてそういうところが行き着いた先にある乾いた笑いのような投げやりな感情だったり、「もういいや」というようなあきらめの感情であったりする。そういった歌詞のひとつひとつが小さな棘になってちくちくと僕の体を刺していく。それがまた快感であるのだから始末に負えない。そりゃあ歌詞だけみればただの大人になりきれないおちゃらけた感じだったり、自己嫌悪とやりきれなさの混合されたどろどろした液体だったり、どうしようもないドSだったりするのだが、これがリズムに乗ると一気に変化する。うねりを持ってもっとどうしようもない感じになったり、時にはぐっとシリアスにもなって聴くものを引き込んでゆく。それをさらにスガシカオ自身の時に乾いた、時に湿ったようにも聞こえるざらっとした声が引き立てる。そこでリスナーが耳にするのは澄み切った声ではない、ポップなメロディでもない。それどころかどの曲を聴いても通底して感じる「違和感」こそが最大の魅力なのである。けれども、そこで感じる「違和感」の正体は誰もが持っているのであろう「孤独」「自分の弱さ/無力さ」「すれちがいの感情」みたいなありふれたものだ。そういったものを改めて音楽として提示されたとき、人はそれを「違和感」として処理しようとするけれども、そうできないわだかまりがある。なぜならその「違和感」が自らのうちにあるものだということに気づいているからこそ、見逃せない/聴き逃せないのだ。そうしてるうちに彼の音楽は遅効性の毒みたいに全身に回ってしまって、離れられなくなる。 さらに、スガシカオの音楽にはもうひとつの特徴があるように思う。それは「カタルシスがない」ということ。最近の曲、たとえば「奇跡」や「午後のパレード」なんかは明るい曲調であるにせよ、歌われているのは「奇跡が起こりそうな予感にドキドキしているけど、その未来の薄っぺらさも感じている自分」(「奇跡」)だったり、「未来へずっと続いていくようなんだけど、どことなくうさん臭さを感じさせるようなパレード」(「午後のパレード」)だったりする。そして「奇跡」と「午後のパレード」の間にひょいと出てくる「真夏の夜のユメ」では「孤独で嘘つきな自分を自己嫌悪する僕」というような、闇がべったりと塗りつけられたりするような音楽が出てきたりする。そんなふうにスガシカオの曲は聴いている人に「はっきりとした答え」を明示しない。明快なメッセージを送らない。違和感を違和感としてとらえ、歌っているのだ。たとえば「こんな僕でも人を好きになっちゃってもいいんですか?いいんです!大好きです!愛してます!」と歌っているポップス(僕がそういうのを嫌いだというわけでは決してない)とは対照的にスガシカオは「僕は人を好きになってもいいのかなあ、好きになって『愛してる?』とか言われてもどう答えていいかわからないしなあ」っていう感じである。そしてそんなうだうだしたようなうじうじしたような流れの中で音楽は終わる。答えはない。確信に満ちた決意もない。当然、リスナーがカタルシスを感じることがない。でもだからこそスガシカオなのだ。カタルシスは他のアーティストに任せておいて、「カタルシスがないまま放っておかれるいやらしさ」を味わい、リスナーがその青臭さや泥臭さに身もだえする音楽こそがスガシカオなんだと思う。 最近出版された「別冊カドカワ」のなかでスガシカオは「自分の音楽は懺悔や自分の救済である」と語っている。自分が他人よりも音楽の才能を持って生まれて、選ばれて歌っていることへの懺悔であり、その懺悔を通じて他人を救済することによって自分も救済されるというサイクルがモチベーションである、と。そういった彼の思いがそのまま歌になって、リスナーはそれを聴いて「カタルシスがないことの事実確認」をしてある意味で安心する。そういうものが「スガシカオの音楽」なんだろう。
プロフィール
生まれ:1978年旭川市生まれ。 育ち:道内あちこち。その後横浜、川崎を経て再び札幌。 観戦暦:1996年・対日本電装戦が初応援。翌年より道外への進学に伴いアウェー中心に応援、1998年よりアウェイコールリーダーとなる。2003年春に札幌へUターンし、現在ホームゴール裏で応援中。 サッカー以外の趣味:音楽と活字。
最新のエントリー
コメント
検索